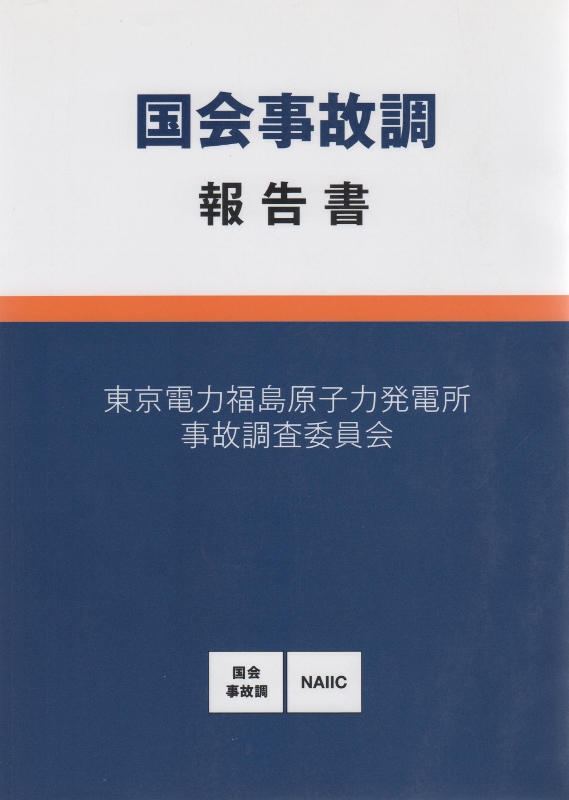
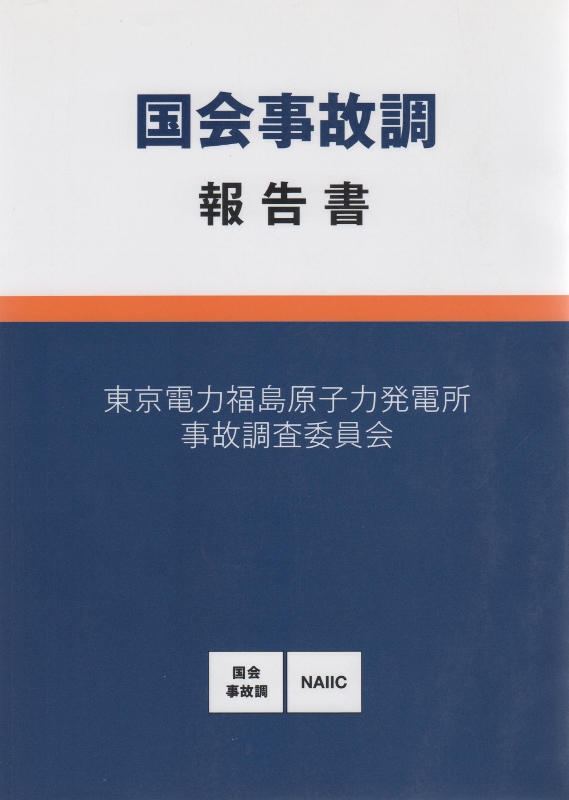
ここに上の図にあげた1冊の本がある。東京電力福島原発事故調査委員会著 「国会事故調 報告書」 徳間書店 (2012年9月30日) には、東電福島原発事故についての、事故原因の全容と概要が書いてある。本書添田孝史著 「原発と大津波-警告を葬った人々」(岩波新書 2014年11月)は、原発津波災害の危険性を警告した地震学者の意見を、原子力ムラ(なかでも経産省資源エネルギー庁と保安院、東電と電事連、そして原子力安全委員会に携わった学者)の人々が原発の利害のためにその警告を過小評価し、修正するよう働きかけ、津波対策を引き伸ばし無作為のまま3月11日午後3時40分を迎えたことに限って責任を追及するものである。そういう意味では東電福島原発事故原因論の一部分をクローズアップすることであった。そこで本書を読む前に「国会事故調報告書」を概観しておこう。2011年10月30日に施行された「東京電力福島電子力発電所事故調査委員会法」に基づき、衆参両議長が任命した10名の委員長と委員が国会の同意を得て発足した。委員会の構成を下に示す。
委員長 黒川 清 (政策研究大学院アカデミックフェロー 元東京大学医学部教授)
委員 石橋克彦 (神戸大学名誉教授 地震学者) 大島賢三(国際協力機構顧問 元国連大使 外務省出身) 崎山比早子(元放射線医学総合研究所主任研究官) 桜井正史(弁護士 元名古屋高等検察庁検事長) 田中耕一(島津製作所フェロー 2002年ノーベル化学賞受賞) 田中三彦(科学ジャーナリスト 元バブコック日立原子炉設計技術者) 野村 修(中央大学法科大学院教授 弁護士) 蜂須賀礼子(福島県大熊町商工会会長) 横山禎徳(社会システムデザイナー 都市計画専攻)
国会事故調・東京電力福島原発事故調査委員会の特徴は、つよい調査権限を有し、協力しない人には「国勢調査権行使」が出来ることであるとされる。黒川委員長の格調高い言葉がある。「福島原子力発電所の事故対応の模様は、日本が抱えている根本的な問題を露呈することとなった」と始める。問題の根源は1960年代の高度経済成長期と1970年のオイルショック後の政界、財界、官界が一体となった国策として原発が推進されたことである。これを「国策民営」という。原発事故を「想定外」といって危機管理をサボってきた事業者と監督規制官庁の「人災」が本事故の本質である。それでも報告書は、①日本のエネルギー政策全般 ②使用済み核燃料処理処分 ③原子炉の実地検証(当面不可能) ④賠償・除染などの事故処理費用 ⑤事業者の賠償支払い能力を超える場合の責任の所在 ⑥原発事業への投資家、株式市場の問題 ⑦原発再稼働 ⑧制度設計(歴代自民党政府の政治政策) ⑨廃炉プロセスなどは扱っていない。この福島第1原発事故を「第2の敗戦」と呼ぶ人もいる。第1の敗戦によって天皇制軍事支配体制が滅んだように、「第2の敗戦」によって日本の政府官僚と議院制内閣政治家と産業・学界・メデイァの支配構造の欺瞞が崩壊し、脱原発を願う人が多数派となった。支配構造(原子力ムラ)は原発再稼働を着々と準備しており、金力とメディアを使って世論を説き伏せようと策動を行なっている。今まさに岐路に立ったリスクに満ちた日本社会の変革が始まろうとしている。「この国は反省のない国」といわれるが、反省しないのは支配者であって、国民ではない。おそら支配者(原子力ムラ)はこの書を葬り去ろうとするだろうし、政府官僚はこの書の提言を都合のいいように骨抜きにかかるだろう。原発事故後すでに1年半が経過したが、見直されたのは「原子力規制庁」が骨抜きにされた「規制委員会」に過ぎない。この国は滅んでしまった方がいいのか、はたまた再建に価するのだろうか、それはこの書を読んだ我々の働き如何にかかっている。 「東電福島原発事故 国会事故調 報告書」は 次のような結論と提言をまとめた。
結 論
1) 事故の根源的原因: 事故の根源的原因は歴代の規制当局と東電との関係において、規制する側と規制される事業者の力関係の立場が逆転することによって原子力安全についての監視・監督機能が崩壊したことに求められる。何度も事前の安全対策を立てるチャンスがあったことを考えれば、本事故は自然災害ではなくあきらかに「人災」である。
2) 事故の直接的原因: 事故の直接的原因について、安全上重要な機器の地震による損傷がなかったとは言えない。むしろ1号機については放射性物質の漏れ状況からして小規模損傷LOCAが起きた可能性を否定できない。しかし未解明な部分が残っており引き続いて第3者による検証が望まれる。
3) 運転上の問題の評価: シビアアクシデント対策がないまま全電源喪失に陥った場合打てる手は限定される。過酷事故SAに対する十分な準備と訓練、機材の点検がなされ、SA緊急時の運転手順があれば、より効果的な事故対応が出来た可能性は否定できない。即ち東電に組織的問題であると認識される。
4) 緊急時対応の問題: 事故の進展を止められなかったこと、あるいは被害を最少化出来なかった最大の原因は、官邸および規制当局を含めた危機管理体制が機能しなかったこと、および緊急時において事業者の責任、政府の責任の境界が曖昧であったことにある。
5) 被害拡大の原因: 避難指示が住民に的確に伝わらなかった点について、これまでの規制当局の原子力防災対策への怠慢と、官邸・規制当局の危機管理意識の低さが今回の住民避難の混乱の根底にある。
6) 住民の被害状況: 被災地の住民にとって事故の状況は続いている。放射線被曝の健康問題と生活破壊、環境汚染状況は深刻である。いまなお15万人が避難生活を余儀なくされている状況の最大の原因は、政府・規制当局の住民の健康と安全を守る意志の欠如と対策の遅れ、被災住民の生活基盤回復の遅れ、さらに被災者の視点を考えない情報公表にあった。
7) 問題解決に向けて: 本事故の根本的原因であった人災を特定の人間のせいと帰結しないで、組織の利益を最優先する組織依存マインドを改め、組織的・制度的問題を解決することなくして再発防止は不可能である。
8) 事業者の組織的問題: 東電のガバナンスは自律性と責任感に欠け、規制を骨抜きにする態度に終始してきた。住民の健康被害と安全をリスクとしないで、既設炉の運転効率低下と訴訟問題を経営リスクと考えていた。法規制された以上の進んだ安全対策を採用せず、つねにより安全な運転を志す姿勢に欠け、緊急時に発電現場の事故対応支援ができない東電経営陣は、原子力事業者として適格性に疑問が持たれる。
9) 規制当局の組織的問題: 規制当局は組織の形態や位置づけを手直しするだけの従前の官僚的対応では国民の安全は守れない。官僚組織の利益(国営益より省益重視)だけを行動指針とする内向きの態度を改め、実態の抜本的転換を行い、国際社会から信頼される規制機関への脱皮が必要である。
10) 法規制: 原子力法規制はその目的、体系を含めた抜本的な改正が必要である。その見直しに当たっては世界の最新の技術的知見を反映し、反映してゆく仕組みを構築すべきである。
提 言
1) 規制当局に対する国会の監視: 規制当局を監視する目的で、国会に原子力に係る常設の委員会を設置する。この委員会は規制当局、利害関係者、学識経験者から意見を聴取・調査を恒常的に行なう。この委員会は最新の知見をもって安全問題に対処するため専門家からなる諮問機関を設ける。この委員会は今回の事故検証で発見された多くの問題について恒常的な監視を行なう。この委員会は事故調査報告について今後の政府の履行状況を監視し定期的に報告を求める。
2) 政府の危機管理体制の見直し: 政府の危機管理体制の抜本的な見直しを行なう。指揮命令関係の一本化を制度的に確立する。放射能の放出にともなうオフサイトの対応は、政府と自治体が中心となって、役割分担を行なう。事故時における発電所内(オンサイト)での対応は、第一義的に事業者の責任とし、政治家の支持介入を防ぐ仕組みとする。
3) 被災住民に対する政府の対応: 被災地の環境を長期的にモニターし住民の健康と安全を守る。長期にわたる健康被害に対応するため、国の負担による継続的検査と健康診断、医療提供の制度を設ける。環境に広く分布する放射性物質は長期的にモニター監視し、汚染拡大防止策を講じる。国は汚染場所の基準と作業スケジュールを明らかにする。
4) 電気事業者の監視: 事業者が規制当局に不当な圧力をかけないよう、事業者と規制当局の接触にルールを設ける。電気事業者間において安全に向けた先進事例紹介と、達成に向けた相互監視体制を構築する。東電に対しては経営管理体制、危機管理体制、情報開示体制を再構築し、高い安全性目標に向かって継続的な自己改革を促す。電力事業者を監視するために立ち入り調査権を伴う監査体制を国会主導で構築する。
5) 新しい規制組織の要件: 規制組織を抜本的に改革する。高い独立性、透明性、専門能力と責任感、一元化、自律性を持った組織を作るものとする。
6) 電子力法規制の見直し: 世界の最新の技術的知見を踏まえ、国民の健康と安全を第1目的とする一元的な法体系を再構築する。安全確保のため第一義的な責任を負う事業者、そして事故の時この事業者を支援する各当事者の責任分担を明確化する。規制当局は世界水準に向けた努力を継続するため、不断の見直しをおこなうことを義務づける。新しいルールは既成の原子炉にも遡及適用(バックフィット)することを原則とし、廃炉または対応が出来る場合の線引きを明確にする。
7) 独立調査委員会の活用: 未解明部分の事故原因の究明、事故収束に向けたプロセス、被害拡大防止策、廃炉の道筋など国民生活に重大な影響を与える問題を調査審議するため、第3者機関として「原子力臨時著プ差委員会(仮称)」を設置する。
「東電福島原発事故 国会事故調 報告書」は「なぜ事故は防げなかったのか?」について次のようなまとめをしている。この部分が本書添田孝史著 「原発と大津波-警告を葬った人々」の扱っている部分に最も近い。2011年3月11日時点で、東電福島第1原発が地震に耐えられる保証は何もなかったこと、又シビアアクシデントに対応できる準備は何もなされていなかったこと、その理由として東電あるいは規制当局が何度もリスクを認識する機会があったにもかかわらず、既設炉の稼働と訴訟問題を恐れて対応を拒み続けてきたことが事故の根源的な原因であった。2006年中越地震による刈羽原発事故を受けて、原子炉の耐震設計審査基準が大幅に改定された。基準振動を600Galとした既設原子炉のバックチェックの実施が求められたが、東電は2009年に最終報告を求められていたが、限定された設備のみを対象とした中間報告を提出でお茶を濁し、それ以降全体的な耐震バックチェックを怠り、最終報告提出をかってに2016年まで延期し、かつ1-3号機の耐震補強工事は全く実施していなかった。保安院は東電の対応の遅れを黙認してきた。したがって古い設計基準で作られた1―3号機が地振動による損傷がなかったかどうか保証の限りでは無い。2006年の段階で、土木学界手法による予測を上回る津波が来たとき、海水ポンプが損傷し炉心損傷に繋がる危険は、保安院と東電は認識していた。そして何も手を打たなかった理由の背景には、保安院の審査や指示が伝統的に非公開で行なわれ状況が外部には分からなかったこと、また土木学界手法による津波高さ予測が正しかったかどうか疑問が残ることである。電力業界は多大の研究費を土木学界に援助し津波評価に深く関与した。そして津波確率を恣意的に「ありえないほど低い確率」とみて対応を実施しなかったことである。これは長時間の全電源喪失を「あり得ないほど低い確率」として考慮しなくていていいとした原子力安全委員会の指針と同根のリスクマネジメントであり、原子力安全神話で自分を騙し続けた自己撞着の結果である。日本のシビアアクシデントSA対策は実効性に乏しかった。それは運転と設計上の内部事象のみしか想定しなかったことによる。1991年原子力安全委員会は、「SA対策は技術的、知識ベースによるもので、安全規制はそぐわない」として自主対応でよいとしてきた。それでも2010年より海外の動向を受けた保安院のSA規制化の流れに対して、東電は電事連を通じて執拗な働きかけを行い、バックフィット(遡及的対応)が既設路炉の稼働率の低下や原発訴訟の口実にならないように、「バックチェック」という言葉に変えて見直しの骨抜きをおこなった。まさに東電の官僚的手法といえようか。こうして確率は低いが破滅的な事象を引き起こす事故シナリオに頬かむりをしてきたことが事故の根源的原因である。 そして事故当事者の組織的問題として次のような指摘をした。事故当事者である東電、規制当局の組織統治能力(ガバナンス)を問題とする。事故の根源的原因は何度も地震・津波のリスクに警鐘が鳴らされたにもかかわらず、東電がシビアアクシデントの原因としての外部事象の発生確率が低いとして地震・津波対策をなおざりにし先送りをしてきた点にある。またそれを許してきた規制当局の責任も重い。やるべきことをやらない、これを行政の不作為という。海外での規制実施を受けて、全電源喪失対策の指針への反映、直流電源の信頼性見直しを検討してきたが、それを考慮する必要は無いと規制を見送った。東電・保安院にとって今回の事故は決して「想定外」ではなく、認識していたのも係らず対策を怠った責任は免れない。電気事業者は耐震安全性見直しのバックフィット、SA対策などの規制強化を拒み続け、電事連を通じて学界や規制当局に規制回避を働きかけた。こうした事業者のロビー活動に規制当局は妥協し、事業者の都合にあわせた指導でお茶を濁してきた。これを「虜の構造」という。東電の経営伝統は自律性と事業の責任感が稀薄で、お国の依頼で原発をやっているから規制を弱めてこちらのわがままを聞いてくれという関係を続けてきた。まさに東電は経産省の一部組織に近い感覚で運営され、お互いに深く依存しあっていた。原子力技術に関する情報格差を武器に、電事連を通じて規制を骨抜きにする試みを続けた。シビアアクシデントの経営のリスクとは、周辺住民の健康や生活に与える影響ではなく、対策を講じる費用や既設炉を停止したり、訴訟上不利となる事をリスクと捉えてきたことである。原子力部門の経営は決して楽ではなく、最近はコストカットや原発稼働率の向上ばかりが重要な経営課題として認識されてきた。「安全第一」は掛け声だけで、利益率最優先の姿勢はどこの企業体とも変わらなかった。扱っている商品事業が極めて危険であることを東電本社は忘れていたのでは無いだろうか。規制当局との伝統的な癒着体質は非公開を原則としてきたため、情報とくに不都合な情報の隠匿は日常茶飯事であった。今回の事故での放射線漏出情報公開は不十分で結果として被害拡大の遠因となった。最後にわが国の規制当局には、国民の健康と安全を最優先と考え、原子力の安全に対する管理監督を確固たるものにする組織的な風土も文化も欠落していた。失われた国民の信頼を取り戻すには、新規制組織は国民の安全を最優先する前提に立たなければならない。そして組織の独立性、透明性を高め、専門能力を持った人材を育成し、国際安全基準に沿ってわが国の規制体制を向上させてゆく「開かれた体質」が必要である。さらに緊急時の迅速な情報共有、意思決定、指令の一元化を図る必要がある。
本書の著者添田孝史氏と「東電福島原発事故 国会事故調」との関係を述べておこう。添田孝史氏は大阪大学基礎工学研究科卒業後、1990年朝日新聞社入社、大阪本社科学部、東京本社科学部などで科学・医療分野を担当し、1997年より原発と自信について取材を続けてきたそうだ。2011年3月東日本大震災と東電福島原発事故が起きた後。5月に自信とは関係なく朝日新聞社を退社しフリーランスになり、現在本人のツイッターによると半農・ライター生活であるそうだ。基本的にサイエンスライターで、東電福島原発事故の国会事故調委員会で協力調査員として津波分野の調査を担当した。日本列島は「地震列島」といわれ、いわば列島全体がプレートという板バネの上に乗っているようなもので、太平洋沿岸の日本海溝に潜り込む板バネに歪が蓄積されればぱちんと弾ける、それが局所なのか広い範囲で連動するのかで津波の規模が決まるのである。本書では実務者レベルの不作為や規制権限の不行使を追及しているが、そもそも原発を地震列島の上に作ることが世界の地震学会の常識に反している。地盤の安定した大陸に日本があるのではなく、いずれは大陸に近づき大陸に吸収される運命にある、移動する日本列島はまさに活動火山や地震活動のメッカといわれる。新潟柏崎刈羽原発、福島第1原発事故と2度も大地震に襲われたのだから、東電はより慎重であるべきはずなのに、もう大地震は来ないだろうと傲慢にも原発の再稼働を狙っている。彼らに原発の運転を任せるのは危険である。地震学者の懸念を無視しリスクは低くなったと強弁する電力会社や規制当局(規制委員会も再稼働のお膳立てが任務である)の姿は事故後も変わっていない。著者の言によると、専門家の言うことを頭から信用するのは危険であることを、1995年の阪神淡路大震災の時に嫌というほど味合わされたという。前年の1994年米カルフォニアノースリッジの地震で高速道路が崩壊した。日本の耐震工学の専門家は「日本の建造物は安全、地震災害に対する知識レベルが違う」と豪語していました。ところが神戸市東灘区の高速道路が600mにわたって横倒しになっていた。すると専門家は関東大震災クラスの対応しかしていなかったと言い訳を始めました。「原発は自信が起きても安全」という専門家の説明の根拠も怪しくなってきます。1997年石橋克彦神戸大学教授が「原発震災」という言葉を論文にすると、班目春樹内閣府原子力安全員会委員長は「原子力学会では聞いたことがない人」と全面否定(人身攻撃)しました。むろん石橋氏は地震学者であって原子力の専門家ではない。地震学の基本となる「プレートテクにクス」が確立したのは1960年代の終わりごろで、そのころには福島原発を始め初期の原発の多くは設計が終了していました。新しく認識されたリスクには備えていなかったのです。直下型地震規模はマグニチュード6.5までしか想定していない。マグニチュード6.5が不十分なことは島崎邦彦東大地震研究所教授、松田時彦東大名誉教授らが指摘するところで、当の原子力安全委員会でも今ではマグニチュード6.5の根拠は分らないという。「わからない」というのは官僚の責任逃れの常套句であって、議事録がない、資料がないというのも隠蔽工作の一環である。これは驚くに当たらない。それでも「原発は地震が起きても安全だ」という神話だけは独り歩きしていた。新知見があれば原発の安全性を見直すのが当然であって、新指針を作り既存原発の耐震性を再確認しなければなら医という原則で動いていると思い込むのはこの原発業界では大きな間違いであった。旧指針による既存原発は旧法による既得権を得たように、新指針を適用することを拒み続けてきた。1つは原発の稼働率を上げること、2つは莫大な対策工事支出を老朽化した原発に掛けたくないという経済性のために新指針に従わなくてもいいような学会工作、経産省規制当局への工作という裏技を繰り返してきたのである。十分とは言えないがそれでも新知見を取り入れて原子力安全委員会が新指針をまとめたのは2006年のことである。東電は一貫して新指針には非協力の態度で計画書提出の引き延ばしを行い、2011年段階でも福島第1原発はほとんど手を付けていなかった。石橋氏が「原発震災」で「強烈な地震動による個別的な機器損傷もさることながら、そのバックアップ機能の同時事故発生が起り、外部電源、ジーゼル発電機が動かず、バッテリーも機能しない事態が起こりかねない」と指摘していた最悪事態が、2011年3月11日東北地方大平洋沖地震で「全電源喪失」が起ったのである。東電の清水社長は2日後「想定を大きく超える津波だった」といった。新たなリスクの想定は13年前に出ていた。東電はどの程度の想定をしていたのか、必要な対策は取っていたのかは口をつむって、天に向かってつばを吐いたのである。2011年12月国会の東京電力福島原発事故調査委員会に就任した石橋教授のもとで著者は協力調査員となって、東電や電事連の内部資料を点検する機会を得たという。それによると津波想定見直しのきっかけは、1993年の北海道南西沖地震で発生した高さ30メートルの大津波で奥尻島の約200人が亡くなったころから、電事連は原発の津波想定が時代遅れであることを知り対策を検討し始めたようである。1997年電事連の各電力会社の原発担当常務クラスの会合があり、津波が原発設置高さを超える恐れがある事が認識された。ところが対策は遅遅と進まなかった。いつ起きるかわからないと嵩をくくって、安全より経済性を重視した姿勢をとった。電力会社は業界に次ごうのいい専門家を集めて、津波想定や対策を検討する。その報告書を受け取った保安院は内容を吟味せず、電力会社の安全は確保されているという主張を鵜呑みにしてきた。東電、電事連、保安院などによる密室の会議、証拠の残らないメールで通知を出すなど証拠隠滅を図って、原発の津波脆弱性への警告は葬られ、それぞれの責任もあいまいにされてきた。原子力ムラ全員が目をつぶって泥舟に乗り込んだのが原発震災であった。
1) 土木学会の退廃東電は1966年福島第1原発1号機の設置許可申請を起きない、わずか4か月後に安全設計に問題ないとして計画が承認され、1967年9月に着工し、1971年3月第1号機の営業運転を開始した。驚くべくスピードで計画が審査され実行された。日本で一番最初の商用原発は、1966年に運転を開始した日本原電東海発電所である。原子力員会は1957年地震対策小委員会を設置し、1958年に耐震設計仕様書を定めた。構造基準法の3倍の大きさの力に耐えることであった(安全率は3という)。安全率に科学的根拠は薄い。東海原発の設計当時、津波については何も考慮されていなかった。福島第1原発でも津波への警戒は、高所に設けることが必要であるとして立地指針に沿い、1960年のチリ津波で観測された3.12m(小名浜検潮所)のデータから、敷地地盤高さは4mで十分であるとされた。そして冷却用海水ポンプを高さ4mに、原子炉建屋を高さ10mに配置した。この福島第1原発から北へ約115Km離れた東北電力女川原発では明治三陸地震で津波高さ14.3mを記録し、昭和三陸地震で10mの津波を記録したことから、豊北電力は敷地高さを14.8mとし、冷却用海水ポンプの設置高さも14.8mにした。東日本大震災では女川原発に13mの津波が襲来したが、被害は少なかった。これは東北電力と東電の経営者の危機意識が大きな差となって現れたものである。津波については従来考慮されることが少なかったが、1983年の日本海中部地震、1993年の北海道南西沖地震でによってこれまでの認識が大きく改まった。しかし当時は、新しい知見に基づいて基準を見直し、それに照らして既設設備が安全かどうかチェックする仕組み(バックチェック)や、原発を新基準に適合するように改修させる(バックフィット)制度はまだ存在していなかった。各電力会社の原発担当常務クラスが月1回顔をあわせる「総合部会」に資料を読むと、電事連が学術団体である土木学会を利用して、想定津波高さを低く抑える工作を繰り返していた経緯や「安全率」を切り下げること、日本海溝沿いの津波地震を想定から外すことに取り組んできたことが示されていると著者は指摘する。1993年の北海道南西沖地震では奥尻島の被害がおおきく、遡上津波高さが30mを超えた。同年10月通産省資源エネルギー庁は原発の津波想定の再検討を電力会社に指示した。福島原発では過去の地震強度から津波高さを計算し最大津波は津一時真津波による3.5mであると報告した。これらの監督庁からの指示、電力会社の解答報告などは一切公開されていない。想定見直しはその後も何回もおこなわれるが「秘密主義」のファイヤーウォールは高く、情報は秘匿されたままである。津波防災に関係する7省庁は1998年3月に「津波防災の手引」を自治体に通知した。1993年の北海道南西沖地震では4.5mの防潮堤を4mも上回った津波が観測された。当時は過去既往最大に備えることが一般的であったが、地震学の成果も取り入れながら、常に安全側の発想で津波を想定する必要性を示した。その手引書は電事連の総合部会で検討された。それによると、現在原発の安全審査における津波は①既往最大津波、②活断層による地震津波であるが、それ以外に③想定しうる最大規模の地震津波(プレート境界線上の地震地体構造の津波)も想定しなければならないということである。地震地体構造とは、手引きを指導した荻原尊禮東大名誉教授によると、全国を25の領域に分け房総半島沖から宮城県沖までの領域では、津波高さは最大13.6mになると予想した。7省庁手引きは2011年の大震災の14年前に今回の地震津波を予測していたことになる。もっと電事連にとって悪材料は、数値解析精度ばらつき)は倍半分もあることである。「安全側に評価しようとすると数値解析結果の2倍の裕度は見なければならない」とする通産省原発技術顧問の首藤東北大教授と阿部東大教授の意見を電力会社は気にしていた。津波の様相は地震の場所・強度を特定できても、どのように海底を隆起させるかの予測によって倍近い誤差が出るのである。電事連はこの顧問らの指摘に応じて「津波に関するプラント影響評価」を2000年2月に総合部会に報告した。想定水位を1.2倍、1.5倍、2倍にみてゆくと、裕度1.2で早くも裕度の極端に低い福島第1原発と島根原発が水没し、裕度1.5倍で東海原発を含め6ヵ所の原発が影響を受け、裕度2倍では11か所(原発基数にして約半分)が影響を受けることが分かった。こうして電事連は土木学会津波評価部会のメンバーでもある首藤東北大教授と阿部東大教授に対する工作を開始した。土木学会津波想定方法がまとめられた2002年には東電の元原子力本部副本部長が土木学会の会長職にあり、その10年前にも東電の原子力建設部長が会長職についているなど、近年は東電の原子力部門との結びつきが目立っている。学会には約30の調査研究委員会があり、津波・地震の調査は原子力土木委員会が行ってきた。そして1999年から2001年にかけて全8回の津波評価部会を開き「原発の津波評価技術」(土木学会手法と呼ぶ)がまとめられた。その評価部会の主査首藤教授は数値誤差を含まない安全率(裕度)1.0とする基準を採用した。「安全側に評価しようとすると数値解析結果の2倍の裕度は見なければならない」と首藤東北大教授は言っていたはずなのだが、いつの間にか東電に取り込まれて東電寄りの発言となった。その結果福島第1原発ではパラメータスタディを実施しても、津波想定は5.7mとなった。7省庁の「津波防災の手引」がいうところの③想定しうる最大規模の地震津波(プレート境界線上の地震地体構造の津波)も想定しなければならないという項目は土木学会手法には折り込まれなかった。こうして土木学会手法は既往最大地震を基に考える旧法に逆戻りし、7省庁の「津波防災の手引」よりも後退した。まさに土木学会が東電に乗っ取られて形で、東電にとって都合のよい指針(つまり何もしなくていい)を学会がお墨付きを与えたことになる。なぜこういう学会乗っ取りができたかというと、評価部会の研究調査費を全額(約2億円)東電が負担し、評価委員30人中17名が東電・電事連社員が占めるという委員会構成にあった。国の各種審議会より露骨な占拠策を講じたからであった。東電は官僚よりさらに官僚的と言われるのはこの辺のやり口にある。東電の独占物として土木学会津波評価部会が乗っ取られたのである。福島第1原発の海水冷却ポンプの裕度は20cmしかなかった。2007年の新潟県中越沖地震で、柏崎刈羽原発は想定外の4倍の揺れに襲われたが、機械類の安全率が高かったために炉心損傷を免れた。想定とはいつも破られる運命にあるので安全率1という土木学会の手法では全く裕度はなかったというべきであろう。
2) 地震本部と中央防災会議の連携失敗まず1995年の阪神・淡路大震災の教訓を振り返ってみよう。神戸市は地震対策のための調査を京大と大阪市立大に依頼し、1974年11月報告書が提出された。その中で神戸市周辺の活断層の危険性が何度も指摘された。1980年には活断層研究の成果である「日本尾活断層ー分布と資料」が刊行され、新幹線新神戸駅を横切る断層など六甲山地周縁に活動度の高い大規模な断層が密集していると指摘された。ところが1984年に着手された地域防災計画には、活断層への備えは盛り込まれなかった。震度5か6かをめぐる評価では、結局対策予算が膨大となる震度6想定は採用されなかったが、1995年の大震災では震度7となった。地域防災計画作りに係わった室崎神戸大学名誉教授は「日本では最悪のケースを想定できない。最大既往地震をもって想定対象とする経験主義に阻まれて、対策可能な地震以外は起りえないとして無視する行政判断が罷り通った」という。神戸の地域防災計画は阪神・淡路大震災には太刀打ちできなかった。阪神・淡路大震災の教訓を受けて1995年に地震防災対策特設措置法に基づき地震調査研究推進本部(地震本部)が旧総理府(現在は文部省)に創設された。1999年に地震本部に基本方針のなかで「海溝型地震の特性の解明と情報の体系化」を掲げた。このような予測は長期評価部会海溝型分科会で進められ、島崎邦彦東大名誉教授が2011年まで16年間長期評価部会長と海溝型分科会主査を務めた。地震本部は2000年に「宮城沖地震」、2001年に「南海トラフ地震」をまとめ、2002年に「日本海溝」について長期評価を行った。特に注目されたのは「三陸沖北部から房総沖にかけての海溝」でのM8.2程度の津波地震であった。過去400年に3回起きていることから今後30年以内に20%の確率で発生するとして、かなり高い確率となった。1896年の明治三陸地震では、最高38mを超える津波が遡上し、2万人以上が亡くなった。2008年に東電が趣味レーションした結果では福島第1原発で15.7mの津波をもたらすという結果であった。地震本部では震度9の地震は予測していなかったが、岩手沖から房総沖までのいくつかの領域の海溝が連鎖して発生したから今回の地震は巨大となったのである。「連鎖」(連動)という事態は2002年段階では読み切れていなかった。そして問題は中央防災会議が地震本部の「長期評価」結果の足を引っ張り(打消し)に出たことである。中央防災会議とは1961年に制定された「災害対策基本法」によって設置された。事務局は国土庁であったが後に内閣府に移され、総理大臣を長とする。地震本部の長期評価が出た後、2003年に中央防災会議は「日本海溝・千島海溝型地震に関する専門調査会」を設置した。ところが2004年2月の調査会で事務局は「海溝沿いの津波地震」は防災の対象としないという方針をだし、多くの委員が疑問を呈する中でこれを押し切った。まれに起きる巨大津波地震は考慮しないということであった。明治三陸地震が起きた岩手沖の領域だけで想定し、宮城沖以南は警戒しないということを決めた。中央防災会議の不可解な方針は、地震本部の結果の公表にも「発生確率や地震規模には誤差が大きいから取扱い注意」という但し書きを入れるよう執拗に迫ったという。当時確かに内閣府と文部省は仲が悪かったとはいえ、地震防災分野で新参者の地震本部が縄張りを侵すことに中央防災会議の官僚が反発したと思われる。こうした軋轢の中で地震本部の基本方針であった「地震本部と中央防災会議は地震による被害の軽減という共通の目標に向かって、より一層の連携を図る必要がある」は空文に終わった。まさに官僚機構の縄張り争いである。さらに東電や電事連がこれに介入したような形跡がみられるのである。東電は地震学者や原子力安全委員会の専門家に深く関係を持ち、サポートと称する抱き込み戦術、技術指導料と称する金銭授与などで、東電の都合のいい言い分を通すため、委員会報告書の事前入手と報告書の文章を削ったり訂正させることは日常的に行われていた。
3) 東電の不作為と抵抗東北大学理学部地学科の箕浦幸次教授は1986年、地層から過去の大津波を調べる方法を開発した人である。大津波が起ると海岸の砂を内陸まで運ぶ、それが「津波堆積物」である。仙台平野で過去3000年の間に少なくとも3回に大津波があったという。その最大で最新の津波が869年の貞観津波であると判明した。東電が福島第1原発を設計した時点で貞観津波を考慮した記録はない。東北電力は女川原発の第2号機建設のため、1980年代後半に貞観津波の調査を行った。箕浦幸次教授の協力を得て、津波堆積物の調査を行い、貞観津波よりは1611年三陸沖津波の方が大きいことを重視して1990年に対策を行った。1994年資源エネルギー庁は津波想定の見直しを指示し、東電は報告書の中で貞観津波に触れている。問題は仙台沖と福島第原発では、貞観津波の震源地も絞られていないので、貞観津波と1611年の津波のどちらが大きいか仙台と福島では異なる。東電は福島でも貞観津波の方が小さいとしてしまった。東電は1611年のチリ津波と1611年の津波を比較して、その高さは3.5mと計算した。申請時の3.1mの差の40cmだけの微修正を施した。主要施設は津波被害を受けないとしてなんら対策は取らなかった。1990年以降、貞観津波問題、1997年「7省庁手引き」、2002年「地震本部による海溝型津波地震」が新たなリスクとして浮かび上がった。「貞観津波」では水位が高い状態が長く続くのは、海底のずれは比較的小さいがずれる幅が広いためである。「津波地震」は水位は高いのは短時間であるが、破壊的なエネルギーは大きい。こうして1990年以降東電は何度も想定の見直し機会があったにもかかわらず、津波を無視し続けた。東北電力と経営者の体質が異なるようである。東電は2000年に津波想定は5mに、2002年には5.7mに引き上げたが、修正対策は講じていない。ここで東電がとるべき態度としては、地震確率が低いとか科学的根拠がないとか言って無視することではなく、自分自身で津波のレベルを調査することであり、津波の高さが不確実なら余裕をもって対処することであった。しかし東電は、土木学会は津波地震は起きないとしていると言って学界の権威を傘に不作為を決め込んだ。地震本部海溝型分科会の結果から、東電は2002年時点で8.6mを超えることは知っていたはずある。東電が津波地震の検討を再開したのは2007年11月からである。1998年プルトニウムとウランとの混合燃料MOXを使用するプルサーマル計画を福島県が受け入れを決定したが、1999年に茨城県東海村で臨界事故が発生し、原子力関係事故やトラブルが続き、プルサーマル計画は中断した。東電は2002年から激動の時代に入った。時系列に列記すると、3月に土木学会手法によるによる津波想定見直し報告書を提出した。7月には地震本部が津波地震を公表した。8月福島第1原発など東電の13基の原発でトラブル隠しが露見し、29件の事実隠蔽や虚偽報告が明らかになった。9月東電の会長、相談役、社長や4名が引責辞任した。9月さらに福島第1原発で格納容器の検査を虚偽報告。11月保安院が福島原発第1号機に1年間の運停止を命令。2003年4月再点検のため福島第1、第2、柏崎刈羽原発の全17基の原子炉が停止。この間原発の稼働率は2002年のトラブル隠しで80%から30%に低下し、2007年の新潟県中越地震による原発停止以降は稼働率は50%前後で低迷し、2011年の地震で稼働率はゼロとなった。2004年にインドネシアのスマトラ沖地震でM9.1の巨大地震で、インドのマドラス原発は海水ポンプを水没させる事故になった。これを受けて、原子力安全基盤機構JNESと保安院は2006年溢水勉強会などを開始した。津波高さが福島第1原発の敷地高さ10メートルを超えると、大物搬入口から海水が浸入して、電源設備が機能を失い、非常用ディーゼる発電機、交流電源、直流電源が使えなくなって全電源喪失に至る危険性が示された。10月保安院は津波への安全性に疑問を持ち始め電力会社に、津波に余裕がないか少ないプラントは具体的、物理的対応を取るように指示した。東電は対応を取らない言い訳に、2006年7月津波確率が数千年に一度といって反論した。しかしこれはシュミレーションした結果ではなく、土木学会津波評価部会の各委員へのアンケート調査から確率を求めたものであり、しかも委員31人中地震学者は一人しかいないで電力関係者が18人という委員構成では結論はそもそもやらせに近かった。2006年9月に耐震指針が改定され保安院は電力会社に既存原発のバックチェックを指示した。東電は福島第1では高台に設けた5号機を代表として選び、揺れへの対応だけを検討し、2008年3月に報告書を提出した。保安院で安全審査に係わっていた今村文彦東北大教授より「地震本部の津波地震も考慮すべきだ」と指摘された。東電が津波について本格的検討を開始したのはこの時からである。シュミレーションの結果津波地震が福島第1原発に高さ15.7mの津波をもたらすことが分かった。この結果は東電土木調査グループから、武藤栄原子力立地本部長と吉田昌郎設備管理部長(事故当時福島第1原発所長)に報告された。7月東電幹部の判断が示され、地震学会の津波地震を取り入れず、土木学会手法で評価すると言い渡した。このような高い津波は実際起きないだろうという見込みで、原子炉の寿命より頻度が少ないリスクには対応しないと判断していた。これが東電経営陣の考えであった。2008年度の東電の決算は柏崎刈羽原発の停止により28年ぶりに赤字に転落していた。2010年にプルサーマル計画が福島県知事佐藤雄平知事によって受け入れが表明された時の条件として、3号機の耐震安全性が確保されていることが出されていた。それに対して東電は土木学会の手法で安全性は確保されると言って、その時点で問題となっていた津波シュミレーションの結果を隠し、住民及び県に対して嘘をついていた。東日本大地震の4日前、3月7日保安院と東電は秘密の打合せを行った。その時の資料には3種類の想定津波高さが記されていた。①貞観地震津波 9.2m、②地震本部の11896年明治三陸沖タイプ 15.7m ③地震本部の1677年房総沖タイプ 13.6mでいずれの場合も、東電の2009年に修正した想定6.1mを上回っている。ということで東電が福島第1原発で実施した津波対策は、1971年以来40年間で海水冷却ポンプを数十センチかさ上げしたことだけであった。
4) 保安院の規制権限不行使前で見たように2002年までに、東電は地震本部の津波想定で福島第1原発はシビアアクシデントを引き起すことを把握していたようだが、資源エネルギー庁や原子力安全・保安院はこれにどう対応したのだろうか。規制当局は「最新の知見に照らして是正するところがあれば、遅滞なくこれを行う責任がある」(2006年 近藤俊介原子力委員会委員長)とされるのだが、規制当局は2000年から2002年にかけて、3度の機会にその責任を果たしていない。①エネルギー庁は1997年、想定を超える津波への対策を要請したが安全対策に結び付いていない。②2002年2月に策定された土木学会手法が妥当かどうか精査していない。③2002年7月地震本部の長期評価が日本海溝で大きな津波の発生を予想したが、保安院はこれに対応しなかった。筆者はこの時期の保安院の耐震安全課長本部氏、平野氏らのヒアリングを行ったが、知らぬ存ぜぬの繰り返しで責任のあいまいさを痛感したという。本部氏は福島第1原発事故における吉田氏の初期対応の失敗を強調するだけで、自分たちの不作為にはだんまりを決め込んでいた。保安院の統括安全審査官であった新潟工科大学特任教授の高島賢二氏は「統括安全審査官は7人いたが、津波に関心を持っていたのは私だけ」という。津波想定を本社で潰した一人であった吉田所長に対する高島氏の恨みつらみは大きい。2004年のインドマドラス原発の緊急停止事故により津波リスクは現実のものとなったが、保安院とJNESは東電に津波により施設が浸水した場合どいう事態(シビアアクシデント)になるか早急に検討したいと伝えたという。そして2006年1月「溢水勉強会」が開催された。6月に保安院は「溢水の検討方針案」をまとめた。そこでは土木学会手法の再検討と、津波高さを1.5倍の安全率で考える、対応計画策定の期間を2年以内とするなどを決めた。ところが2009年3月の安全情報検討会から2008年の提出期限は抹消されていた。優先順位と経済性から、計画期限を電力会社が守らないことが明白となったからだ。そして計画の実施を2010年とするとして方針も「耐震指針のバックチェックに委ねる」という先送りとなった。保安院の指示は電力会社の顔色を見ながら後退していった。2006年9月に原発の耐震指針は改定され「まれであっても発生する可能性がある津波によって、施設の安全機能が影響を受けることがないように」と定められた。原子力安全委員会は保安院に「原発の耐震安全性の評価結果を確認し報告すること」と指示した。東電は津波想定の見直しを含む福島第1原発のバックチェックを2009年6月までに実施することとしたが、2007年の新潟県中越沖地震の影響で津波のバックチェック計画は棚上げされた。柏崎刈羽原発では想定の4倍の地震揺れが観測され、東電と保安院は協議して、中間報告は原発の主要7設備のみの耐震チエックだけでよいことにし、津波チェックは先送りされた。東電では津波バックチェックを含む最終報告書の提出は2016年1月としていた。こうして問題山積の電力会社のご都合で、津波対策は後退し保安院はそれを放置した。保安院の業務運営基本方針には①安全規制の公開、透明性、中立・公正、最新の知見を反映などが謳われ、佐々木初代保安院院長は「産業界の利益により判断を左右させない。安全規制機関として常に中立・公正な判断を行います」と説明していた。ところが1994年から2011年にいたる東電と保安院の津波想定の意見交換はすべて秘密にされている。また保安院から東電への指示は多くが文書ではなく口頭で行われた。これは保安院の情報隠しの常とう手段であったという。
5) 不作為の脇役 学会・メディアここでは地震学者、土木学者、メディアの責任を問うものである。1997年福島県は地震・津波被害想定に関する調査を野村総合研究所に依頼し、3月報告書を受け取った。福島県沖の既往地震として1938年の2件、参考地震として1677年の延宝房総沖地震を取り上げて津波高さを想定したもので、既往地震2件は越流は阻止できるが、参考地震では5.8mの高さの津波となるとして課題に挙げたが、最も危険である原発に対し何の対処もしなかったのは残念である。原発に触れることは自治体としてタブーだったのあろうか。7省庁の手引きでは「既往最大だけでなく、常に安全側の発想から地震研究の成果を取り入れ最大規模も対象津波として設定する」と述べている。地震本部地震調査委員会の安倍委員長(東大名誉教授)が2011年12月の政府事故調のヒアリングに答えて「地震本部の長期評価の結果には、対策を講じるも一つ、無視するのも一つ、ただし想定津波が過去に発生していないことを証明する必要がある」といった。地震本部の長が結果を無視するならその証拠を示せと東電に入れ智恵しているようにも受け取れる発言である。やはり福島の人への配慮のない発言だった。2006年8月石橋克彦神戸大教授が「私は原子力員会の専門委員を辞任します」と言って席を立った。「この分科会の正体を見た。また日本の原子力行政がどういうものであるかを知った」とインタビューに答えている。耐震指針検討分科会とは、電力業者と資源エネルギー庁、原子力安全委員会が1990年代後半からすり合わせを行ってきた場である。既存原発への影響を最小限にするため、指針の内容を電力会社にとって有利な方向へ持ってゆくために、一部の員をサポート(抱き込み)してきた。安全審査の場で規制当局と関わってきた安部氏や首藤氏らのような人々と、石橋氏のように規制当局や電力会社から独立して視点で原発問題に取り組む人を除いて、多くの研究者は原発に係わるのを一種のタブーとして避けていた。専門家は一歩違う業界については無知である。従って地震学者が原子力行政に係わるにはすごいエネルギーが必要である。筆者は土木学会が取りまとめた津波想定手法「土木学会手法」は津波対策を遅らせた大きな要因であるという。土木関係技術者は津波想定の安全率を1とするか2とするかについては、まず電力事業者が受け入れられるものにする必要があったと述べている。津波評価部会主査だった首藤氏は安全率を上げることができなかった理由として「あと10年ぐらいで廃炉になる福島原発に1000年に一度の津波対策に大金をかけることは株主総会で認められない」といってとりあえず安全率を1とした。土木学会は1999年から2001年までの会合の資料や議事録は現在も公開されていない。朝日新聞の上丸氏は2012年に「戦争で日本のジャーナリズムは敗北した。原発の安全神話を突き崩せなかったことは第2回目の敗北であった」という。これを聞いて、おやジャーナリズムはそんなに強かったのかなと思った。私からすると、ジャーナリズムは権力の補強機関に過ぎず第4の権力と言ってもよい、第1の権力に対しては常に連戦連敗でしょうと言いたい。その敗因を分析すると、活断層が走る島根原発や福井県敦賀原発(日本原電)を追求することを怠った。原発推進元における隠蔽工作や情報遮断策を突き破って事実を発表する気力を欠いていた。これも不作為の一つである。2006年3月衆議院予算委員会で共産党の吉井氏がインド洋沖の津波被害をもとに原発の津波災害について質問した。想定を超えたアクシデントマネージメントAM対策を保安院は電力会社に要請していたが、こういった時においてもジャーナリズムはこの問題を取り上げなかった。新聞さえ取り上げないのなら事件事故はなかったのも同然であると思う社会にとって、新聞は吠える犬であることも忘れていた。面白ければ些細なことで人の社会的生命を断つこと(社会的制裁)は平気でやる新聞は裁判所・検察の手先でもある。