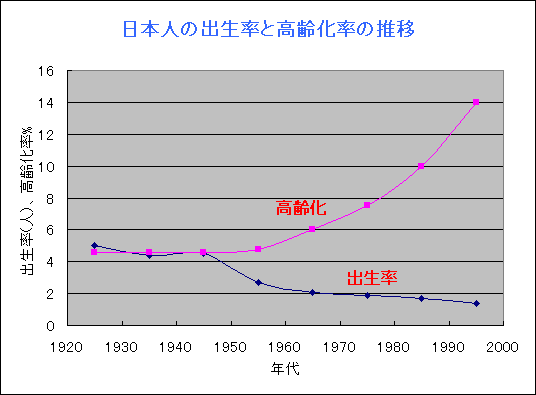
鬼頭 宏「人口から読む日本の歴史」の続編のかたちで少子高齢化社会を検討する。人口減少が世界的趨勢にあることは地球温暖化よりも明白で、また地球温暖化防止の特効薬でもある。地球環境問題の本質は人口増による資源とエネルギーの配分問題であることをこれまで何度も述べてきた(環境書評を見てください)。これこそが人類を滅亡から救う苦肉の知恵であるはずだ。ところが「人口が減っ国が栄えたためしはない」、「少子高齢化は高負担社会をもたらし、日本経済を破綻させる」といった経済面からの主張する人が政府筋に多い。地球では養えないほどの人口を抱え破滅の寸前にある人類が生物的に直感した対応が人口減少である。ナノにまだ銭勘定をしている懲りない輩がいるのである。そういう手合いは権益側の人間(支配層)であろう。また1990年以降の日本ではバブル後の経済対策を誤り、あがけばあがくほど蟻地獄のいわゆるデフレスパイラルに陥っている。夢よもう一度とインフレ願望の経済策を唱える経済バカがいるのである。むかしよっぽど甘い汁を吸っていたに違えねー!
さて松谷明彦・藤正巌共著「人口減少社会の設計」というタイムリーな本が出たのでこれをネタにして右肩上がりの経済からのソフトランディング策を考えてみようではないか。経済学者の松谷氏の論点のみを考察するので、人口減少時代の経済政策に焦点をあて、社会政治的問題や医療制度問題は省かせていただく。
少子高齢化現象はかならず人口減少につながる一歩手前の過渡現象である。すなわち老人は増えるのではなく死ぬ運命にあるからだ。これを政策でどうこうできる物ではない。これは日本だけの現象ではない。先進国全体の趨勢である。日本では2007年から、イタリアでは1997年、スペインでは1999年、ドイツでは2004年から減少し始める。我々が理想としてきた長寿社会は人口減少社会なのである。高齢化社会になると真っ先に起きるのが出生率の低下である。下のグラフを見ていただきたい。
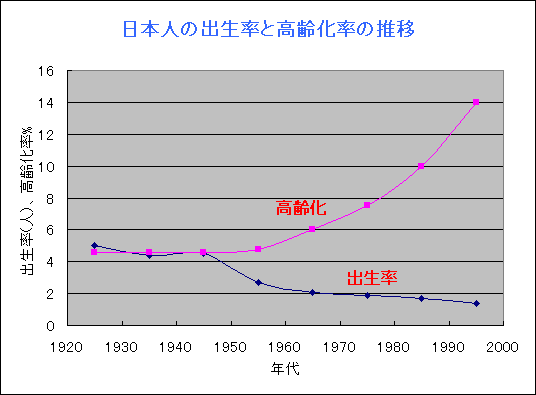
なぜ高齢化社会になると出生率が低下するかは生物学的には説明がつかない。WHOによると65歳以上の人口率が7%を超えた社会を高齢化社会、14%を超えると高齢社会と呼ぶ。高齢化率が7%を超えると例外なく出生率は2人を下回る。つまり人口減少になるのである。さらに先進国ではほとんどの国が14%以上の高齢社会になって出生率は1.5人以下になっている。日本の出生率は1999年には1.35人になった。高齢化社会を成熟社会と呼ぶが、成熟社会では出生率の低下をつぎの要因で説明できる。
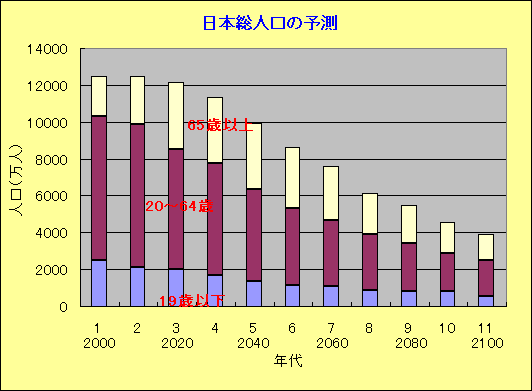
高齢社会の到来と出生率の低下が連動して人口減少にブレーキがかかり日本の人口は2007年より減少局面に入る予定である。1945年の戦後8000万人から再出発した日本は2007年に1億2500万人をピークとして、2040年には1億人を切り2050年には8000万人、2100年には江戸時代の人口に戻る。急速な人口減少は厳然たる未来である。また図には19歳以下、20〜64歳、65歳以上の2階層に色分けして示すが、働き盛りの20〜64歳の人口減少が一番著しい。
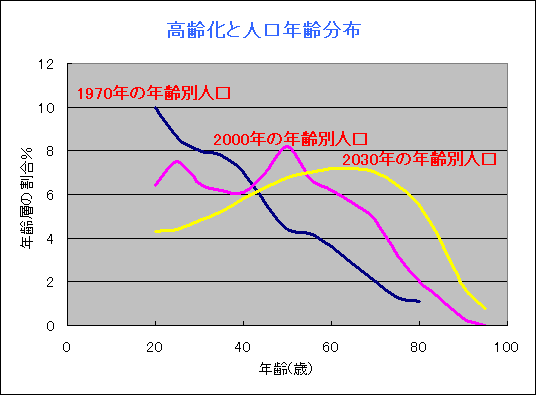
上図に年齢別人口分布の推移を示した。人口高齢化による中位年齢(社会の中心層となる年齢)がしだいに高齢化してゆく様子が分かる。1970年には中位年齢は39歳、2000年には50歳、2030年には中位年齢は58歳になろうと予測される。そこから経済活動の担い手、医療福祉政策、年金問題などの社会対策が問題となってくるが、今回は経済活動のみに焦点を絞りたい。
人口減少社会を暗いと見るか、そうではなく落ち着いた人間らしい生活が営める成熟社会と見るかは経済抜きには議論できないであろう。人口減少に伴い経済は縮小に向かう。日本文化を室町の中世と戦国の近世に出来上がった「縮みの文化」と定義した韓国人がいたが、これは平安時代の小さなことを善とする内へ向かう伝統を受け継いでいる。そうならば経済縮小は日本人にとってなんて事はないはずだが、経済縮小を嫌う人がいる。20世紀の技術革新と拡大の経済は日本では結局何をもたらしたかを検討しようではないか。そこで幸福の定義を経済的には単位労働時間あたりの労働所得が多いこととして、金額ではなく(物価が高くては買えない)購買力平価で日米欧を比較したのが下の表である。
| 年代 | 1980年代 | 1990年代 |
| 国 | 日本 | 米国 | 日本 | 米国 |
| GDP | 226.7 | 511.1 | 246.7 | 393.6 |
| 国民一人当たりGDP | 100.4 | 114.8 | 134.6 | 103.4 |
| 労働時間あたりGDP | 79.2 | 118.6 | 92.3 | 86.7 |
| 労働時間あたり労働所得(購買力平価) | 63.3 | 115.4 | 72.1 | 105.7 |
購買力平価による1990年代の労働時間あたりの所得はドイツ・フランスを100とすると日本は72.1に過ぎない。米国はやはり105.7で格差は歴然としている。その原因は経済効率の低さと、賃金の低さ及び物価の高さからきている。企業の儲けのうち賃金に回される割合を「労働分配率」という。つまり日本では働いた人の取り分が少なく、利益は企業の内部留保(投資及び償却費準備金:いわば企業の貯金である)に持ってゆかる分が多いということである。 下の表には労働生産性の上昇に対する賃金の追随率を日本・ドイツで比較した。高度経済成長期(1960−1970年代)とバブル期(1985−1995年)に賃金の追随率は良好だが、それでも日本の賃金上昇率は労働生産性上昇率に比べるとはるかに低い。ドイツは日本より追随率は常に40%ほど高い。これは経営者の労働者に対する後進性を示す。春闘などで経営者は労働者の努力に報いるといいながら、実は報いる率が欧米に比べて低いとを示している。
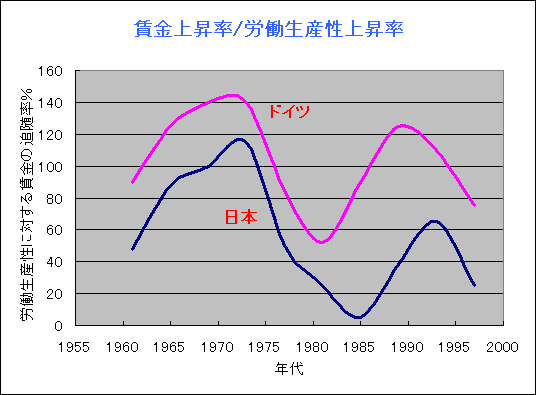
このような後進性はどこから来たのかといえば、良くも悪くも日本的経営からきている。日本的経営は戦後の人口増加と密接な関係を持っていた。日本的経営とは「売上高至上主義」・「終身雇用制・年功賃金制」を特徴とする。この制度はどこから出てきたかというと、なんと戦時中の1939年「賃金統制令」、1940年「従業員移動防止令」で労働者を確保し安く働かせることが国家の戦時経済体制の必要からきたのだ。戦後の急速な経済復興を行うにはこの制度を利用し伝統であるかのように装って若年層が多い時代の賃金を安く抑えて年をとれば増えるように期待させることにあった。それは戦争により働き手を失った若い人口構成であったからだ。人口構成は丁度理想的なピラミッド型で企業組織と一致していた。戦争に勝った欧米諸国の人口構成はむしろ釣鐘型で低賃金層の若年労働者は少なかった。つぎに日本型経営を項目別に検証してゆく。
終身雇用・年功賃金が可能となるにはパイが常に拡大し続けることが必要である。国から見ると企業が儲けることよりも多くの人間を食わしてゆくことのほうが重要視される。そのために売上高を極端に重要視し利益率の多少悪い分野でも投資することが多かった。多角経営は利益率を圧迫し収益性が犠牲になった。これが投資効率を相対的に低下せしめた。
2)日本型経営:金融システム(護送船団方式)欧米企業はなぜ利益率を重要視するかといえば、資金調達が株式によっているからである。利益から配当を出して株主に報いなければならない。ところが日本では外部kらの資金調達のうち8割が銀行借り入れで株式調達は9%に過ぎなかった。バブル期にはワラント債という偽手形で資金を集めるという不健全な時代もあった。だから日本では利益が出なくとも銀行は金を貸してくれる。それは政府の「傾斜金融方式」という規模順に資金を貸し付けるよう指導したがため、銀行自身も貸付額・預金量という規模を重視した。
3)日本型経営:賃金上昇不足賃金の上昇は労働生産性の上昇との相関で経済のバランスが良くもなり悪くもなる重要な要素である。高度経済成長期(1974年まで)以降は賃金の上昇率比は著しく低下していることが上の図から明らかである。日本ではこの比が1以上だったのはごく短期間でほとんどの時期が賃上げが不足していた。その一翼を担ったのは日本型労働組合である。企業内組合であるため最初から会社と運命共同体を標榜して企業への協力を惜しまず、石油ショック以降はストライキはほとんどやらなくなった。労働組合人事も会社の人事部で決定するのが実情である。欧米のような職能別組合が存在しなかったためであろう。そしてバブル以降では賃金支払いの抑制とリストラという企業トレンドが著しく景気停滞を長引かせている。経営者は同属経営を除いて任期は短命で自分の任期期間で経営指標を向上させるにはリストラが一番手っ取り早い。製品開発は時間がかかるしリスクも大きい。ボディブローのように企業活力をなくすリストラに血道を上げたことが日本企業の崩壊を招いた。このように日本の景気後退の最大要因は賃金が人為的に低く抑えられたためである。労働市場も生産物市場、金融市場、貿易と並んで経済活性化の重要な要因である。
人口の減少は経済を確実に変質させる。第1は規模の縮小すなわち経済成長の低下である。第2に生産資本ストックの減少である。第3は不況の長期化である。これらを纏めてデフレスパイラルと呼称する。
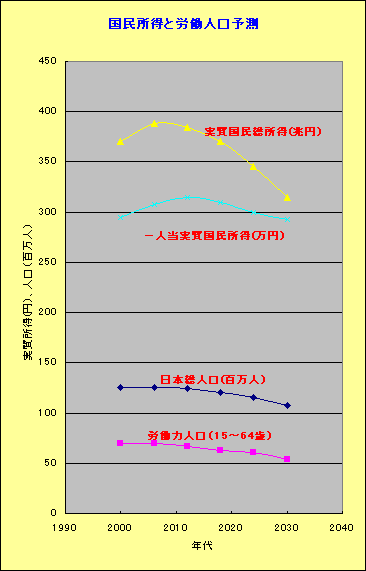
1)労働人口の減少
左の図「国民所得と労働人口予測」に示すように労働者の減少は経済成長に対してマイナスに働く(善か悪かという価値判断は別)。しかも労働人口の減少率は総人口の減少率よりも大きくなりダメージは加速される。日本の生産年齢人口(労働人口:15から65歳)の減少はすでに1996年に始まっており、経済成長率の大きな減少に連結するであろう。
2)国民総労働時間の減少
日本における労働時間の短縮は必ずしも自発的なものではなくても、ILOをはじめ世界的な労働条件の改善の流れの中で進行している。週労働時間は1990年代で日本が43時間、ドイツ38時間、米国41時間であるがこれが2030年には日本は2/31に29時間に縮小する。これも労働力減少をいっそう加速する。
3)経済成長率の低下予測
左図に示すと通り総人口減少と労働力人口減少に従って、国民所得も右肩上がりから2007年より確実に右肩下がりへ移行する。国民総所得は縮小するが国民一人当たりの所得はさほど低下しない。人口が減るからである。
日本的経営は働く人にとって労働配分は少なく、それがかえって購買力の減退と不況の長期化という悪循環になっていることが分かった。国も企業も個人も金は持っているはずなの貯蓄に回り一向に世の中に出てこない。つぎに企業の資本貯蓄の過剰さ(労働配分の低さと表裏の関係)を下の図「純投資額の推移と予測」に示す。
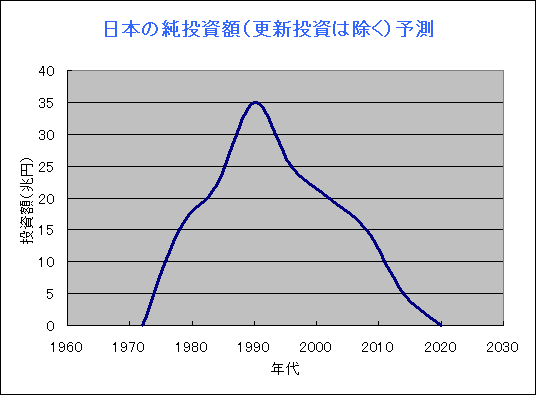
「設備投資」には老朽化を補う更新投資は生産資本ストックが増加するわけではない。生産資本ストックが増加する設備投資を純投資という。バブル以降純投資は漸減を続け2012年からは明確に縮小になる。設備投資が縮小すると困るのは設備関連産業で、日本はその設備投資関連産業が経済に占める比率が30%を超えている。これまでの「投資が投資を呼ぶ」という構図が成立しなくなり、公共投資圧縮で土木・機械関連産業が窮地に追い込まれているのと同じ構図になる。企業は設備投資に備えて減価償却費を別途積み立てている。これは利益ではなく費用だとして税法上優遇されている。この企業の内部留保が膨大な額に上っており、設備投資が縮小すれば賃上げの資金が出来るはずなのに回ってこない。これを「貯蓄超過」という。企業は自分の手でデフレスパイラルを生んでいる。
4)拡大メカニズムの消滅人口減少は日本経済に対して資源配分や所得配分に変更を迫るもので、その方向へ進めば「労働時間あたりの所得増大」につながる。ところがこういう改善をしないで無茶な規模拡大の景気刺激を行ったらどうなるのだろうか。経済活動の牽引力と抑制力は「人間万事塞翁が馬」のことわざのように「あざなえる縄の如く」裏表の関係にある。牽引力はすなわち抑制力に転化するのである。これがアダムスミスの古典経済学における「神の手」である。好況を予測して設備投資に走って、しばらくすると飽和を予測して生産調整・在庫調整になり設備投資を控えることの繰り返しがいわゆる経済学で言う「ストック調整」である。人口減少化の元では需要も縮小するので企業は生産能力を落として規模を縮小しなければならない。しかるに経営者は自分の任期中にやりたくないものだから決断をずるずる引き延ばす。したがって景気の底が見えてこない、不況の長期化になるのである。下の図に経済縮小のソフトランディング策の模式図を示した。
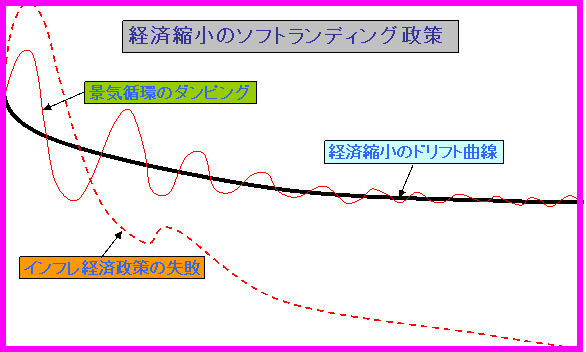
企業経営者が売上高や企業規模にこだわらず利益率を重視するようになれば需要動向に速やかな対応が可能になる。経済活動のトレンドが縮小へのドリフト曲線にあるならば、景気循環はその上に載った波動と考えられる。この波の振幅幅を小さく押さえ込むことが縮小経済への対応策である。この曲線は電気工学をかじったものならばすぐ分かるようにネガティブフィードバックNFB制御の問題である。経済振幅を早く押さえ込むにはダンピングファクターを小さくする必要がある。そして常に反対の制御力を働かせることが必要である。ここでへたなインフレ策を講じれば発振して機構は破壊される。