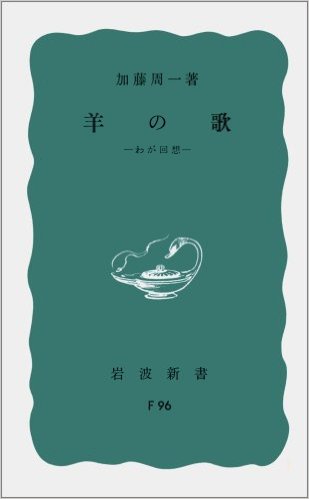

加藤周一箸 「羊の歌」 岩波新書 大江健三郎(左)と加藤周一(右) (憲法九条の会 2004年)
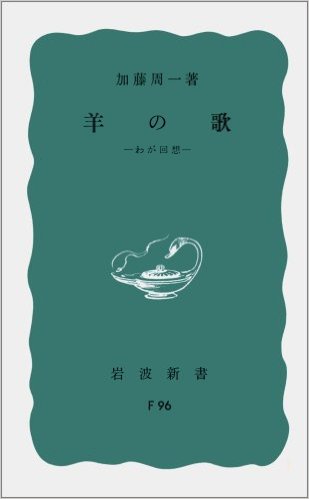

加藤周一氏については、その評論活動や伝記について、海老坂 武著 「加藤周一ー20世紀を問う」 (岩波新書 2013年4月) に詳しく記したので、ここでは繰り返さない。加藤周一氏の関係年譜についてもそちらを参照して下さい。ただちに、本書「羊の歌」に沿って加藤周一氏の言葉に入ろうと思う。小説仕立ての節も多く、すべてが事実ではない。潤色、取捨選択は当然なので、こころして読まなければならない。なお「羊の歌」という題名は加藤周一氏がひつじ年生まれ(1919年)だからだそうです。そういえば中原中也に「山羊の歌」や「羊の歌ー安原喜弘に」という詩があったが、それと関連付ける必要はないと思う。すると氏は私とは二回りの24歳上となり、私も羊年です。本書は上下二巻からなり、各巻20節で構成される。従って全40節で、各節はほぼ均一に12頁からなるのであとがきを含めると、上下巻合わせて500頁の本である。1966年から1967年に「朝日ジャーナル」に連載された。この本は他者が書いた評伝ではなく自伝であるので、第一人称で話を進める。
1) 祖父の家祖父(母方)は佐賀(薩長土肥藩閥政府という言葉があるが、佐賀は鍋島藩で肥後ノ国である)の資産家の一人息子が、19世紀末に明治政府の陸軍の騎兵将校になった。日清戦争(1894年)に従軍する前、家産を投じて馬を買い、新橋で名妓をあげて豪遊したという逸話の持ち主であった。イタリアに遊学してミラノのスカラ座で歌劇を聴いた。祖父はその時西洋風の交際術を見つけてきたようだ。日露戦争の頃には陸軍大佐になり、豪州へ軍馬の買い付けに行った。戦争後は陸軍を辞め、貿易業に転じ第1次世界大戦で儲けたが、その後の恐慌で資産の大半を失ったという。祖父は佐賀県令の妾腹の娘と結婚し、長男は帝国大学医学部を卒業して間もなく死んだ。長女は学院に通わせ佐賀の資産家で政友会の代議士に嫁がせた。次女(加藤周一氏の母)と末の娘は、雙葉高等女学校に通わせた。次女は埼玉県の大地主の息子で医者に嫁いだ。末の娘は会社員に嫁いだ。長女の夫は政友会が政権を取る県知事になりと急に羽振りがよくなったが、応援演説中卒中で亡くなった。次女の夫(加藤氏の父)は医者として成功もせずひっそりと渋谷で暮らした。末の娘の夫は肺結核で亡くなった。こうして祖父の家は次第に傾いていった。祖父の家は渋谷宮益坂の途中にあった。玄関の横の洋間は英国ビクトリア朝の様式をまねた作りであった。祖父は祖母と書生と3人の女中と共に住んでいた。偉ぶった主人にかしずく祖母と女中の姿は宗教的な儀式のようでもあった。庭の片隅にあった稲荷の祠のまえで手を打つのも儀式の一つであった。祖父には「女友達」が多かった。祖父はその頃西銀座にイタリア料理店を経営していた。祖父は家族でそのイタリアレストランに食事にでかけ、イタリア語かフランス語でやり取りしていた様子は、お稲荷さんに毎日手を打つのとは見違えったような祖父の姿を見た。そこの女主人も祖父の「友達」の一人だったようだ。父は外祖父を好きになれず、その「放蕩」を非難していた。それでも私は祖父の血を引いているのだろうか。イタリア料理店は子供にとって西洋そのものであった。祖父が口ずさむイタリア歌劇の一節、そこには感覚の別の秩序があった。20年後自分自身が西洋の地に立つと、幼少のころの世界を見出した。祖父の屋敷に登る坂道に長屋があって、その長屋がすべて祖父の持ち物で貸家であったが、私にとって何の関係もないので長屋に住む人々はなるべく見ないで過ごしていた。
2) 土の香り父の生家は埼玉県熊谷に近い村で、江戸時代名字帯刀を許された名主の家であった。大正時代、森林と耕地を持ち大勢の小作人に耕作させる豪農であった(当時は4部が自分取り、6部が地主納め)。二男一女の三人の子があった。長女は隣村の豪農に嫁していた。長男は東京に住み不労所得で生きていた。生家には寄り付かず、何にもせず、どんな職にも就かなかった。祖父母が年老いて、妻だけが子供ずれで老夫婦のお世話をしに熊谷に移住した。怠けていても楽に暮らして行ける人間が、一生怠けていただけの事であった。次男だった父は東京で医学を学んで町医者になって以来、生家を訪れることは稀であった。小学生の頃、熊谷の実家を訪れるには上野に出て信越本線に乗り、汽車が荒川の鉄橋を渡ると別の世界になった。航空機に乗って離陸した時と同じ感覚である。小さな駅で降りて自動車に揺られ停留場に着くと、そこから麦畑や田の中を歩いて、藪や竹林をくぐって農家の土塀沿いや桑畑の道を歩いた。田舎の匂いを胸いっぱいに吸い込み、田舎の少年少女の好奇心の目に曝され、村で一番大きな家にたどり着いた。電気はまだ来ていないので照明は石油ランプかろうそくで、風呂や便所は暗闇の庭にあった。暗闇や墓場、幽霊への恐怖はなかった。母屋と新座敷には渡り廊下があって、冠婚葬祭の宴にはこの新座敷が使われた。相手に見られながら相手を見るという相互的な関係は都会育ちの私には最初からなく、何時までもよそ者として生きざるを得なかった。それは自ら選んだ「観察者」の生き方であった。
3) 渋谷金王町父は埼玉県の地主の次男に生まれ、浦和の中学を卒業し、第一高等学校から東京帝国大学医学部に進み、大学病院の内科医局町になった。大学時代の同窓には斎藤茂吉や正木不如丘らがいたが、父は詩歌文筆の道には縁がなかった。内科教授選出について医局と当局の意見がことなり、父は医局を去って開業した。開業するといって、田舎の父親が渋谷の金王町の土地を買い、売りに出ていたさる豪邸を解体して運ばせたものである。訪れる人は一日に一人か二人、開業に成功しなかったというよりむしろ若い隠居風の男が、あえて偉業を心の赴くままに営んでいたというべきかも。「医者は薬屋ではない」とか「医者は太鼓持ちではない」というように、不愛想で「商売気」がなかった。それでも父をかかりつけの医師にしていたのは、東京駅の設計者で明治建築史上に名を遺す辰野金吾とその長男でフランス文学者辰野隆東大教授であった。父が往診する患者にはある財閥の本家もあった。米国製の車で父を迎えに来た。父に便乗して青山通りを走った覚えがある。家では私の下に妹が生まれたが、平等に取り扱い、手を上げることはなかった。二人の子供の教育には熱心で、間違ったことをすると罰を与えられるが納得がゆくまで子供に説明をした。家庭は子供にとって全く自己完結的な閉鎖的世界で、理解することができる小さな世界に生きていた。父親は頑固な無神論者で、子どもの教育とキリスト教が関わり合いを持つことは歓迎しなかった。幼稚園に入ったものの、なじめずに退園した。「両家の子弟」という言葉の範囲で完璧な子供時代であった。
4) 病身幼少より私は病弱で高熱と悪夢を恐れた。私の部屋は家の西の端にあり日当たりのよい部屋であった。母親の琴の音が音楽との触れ合いの始まりであった。物売りの声、ラッパの音、自動車の音、音の世界はすべてこの部屋で聴いた。外で遊ぶことの少ない少年は、すぐに文字を憶えた。そのころ金王町の家には父の姉の長男が同居しており、早稲田大学の学生であった。剣道部主将をしていて体の頑丈な青年であった。私はこの従兄によく遊んでもらった。この従兄は大学を卒業すると田舎へ帰り地主の旦那となって、農協の仕事を切りまわした。村で唯一学のある人だったからだ。戦争中は母と妹(妊娠中)の二人が父の実家(そのころ祖父母はすでに亡くなって、従兄が主であった)に疎開しお世話になった。いつも頼りがいのある味方であった。父には腕力も権力もなかったが、叔父(祖父の長女の夫)は県知事になって多いに権力を振い、県庁の課長らは叔父の前に平伏した。自分の家の中だけで権力をふるった祖父と較べて、叔父の権力は計り知れない人々を動かした。父のもとで自分は腕力も権力にもそれほど魅力は感じないで育った。少年時代、私は自然科学の本だけを読んでいた。他に本を知らなかっただけのことである。自然科学を学んだというより、世界を解釈することの喜びを学んだというべきかもしれない。世界の構造には秩序があるということを疑ったことはない。多くの本を読み、多くの言葉を憶え、それ以上に多くの疑問を持った。相談できる相手は父しかいなかった。そのため同学年の子どもと会話することは全くなかった。父には幻滅をごまかすほど忙しい仕事はなかった。人生に幻滅を感じることを理論化することに熱心であった。
5) 桜横町私の親戚の子どもたちで、町の小学校に通っている者は一人もいなかった。男の子は暁星や師範学校付属小学校、女の子は雙葉や聖心という名門私立に通った。つまり中産階級の子弟だけが通う学校である。良家の子弟は町の子と交わることは適してないと考えたからである。しかし私の父は町の子と交わることが大切と考え、普通の小学校に通わせた。なぜか起源のはっきりしない平等主義が父にあって、その考えは合理化されていた。学校で何の差別もなく遊んでいた級友の態度が、自分の家の前に来ると微妙に変化する。驚いて引き返すか、門の前で入るのをためらうのである。道玄坂の夜店の日に父母と散歩に出た。学校では動作の鈍いそれでいて皆から親しまれていた子が夜店のかき氷屋できびきびと働いていた。目が合うとその子は気まずそうに「今忙しいからまたね」といって引っ込んだ。忙しいことを一度も経験したことがない私は、その子の再発見であると同時に私自身の位置と役割を再発見した。成績が抜群に良い大工の息子の家に遊びに行ったとき、家の中は鉋屑で散乱しており、表の角材に腰かけて話をした。赤ん坊の御守りや家事で家では勉強ができないようで、最初から私とは出発点が違っていたことに後ろめたさを憶えた。近くには実践女子大があり、八幡神社が子供の遊び場であったが、学校のかえりその仲間に加わったことはない。要するに私は間違って紛れ込んだ局外者にすぎず、仲間として扱いようのない存在であったようだ。八幡神社から学校までの道には両側の桜が植えられ桜横町と呼ばれていた。住宅に交じっていくつかの商店があって、文房具屋で買い物をした。八幡様の境内を抜けると、金王町まで永井邸の金網が続いた。それは広大な立派なお屋敷で、その金網は世界を分けてコミュニケーションを不可能にするものであった。
6) 優等生小学校は、大きな知的努力を必要とはしなかった。体操・図画などは不得意でした。担任は全科目を教えるが、生物学が得意な先生だったので随分実験には興味を持った。校門の外にパン屋があり休み時間に昼食を買いに飛び出したが、あるとき始業ベルに間に合わなくなるという事件が起きた。先生に見つかって尋問を受けたが、自分だけが止めに入ったのだという先生の誘導に乗って、嘘をつき罰を遁れたことをずっと自分に対する憎悪となった。1920年代の末、渋谷は環状線と市電の他、玉電や東横線や地下鉄の駅が集中し、渋谷が東京の繁華街の一つになろうとする成長期の町であったので、人口が増えたため新設のコンクリート造りの小学校であった。4年生の終わりに中学校へ進学する組と進学しない組に分けられた。進学組に入った私の担任は師範学校出の若い教師で入学試験の厳しい訓練を受けた。毎年第1級の中学校へ多数の卒業生を送り込む学校は第1級の小学校と見なされた。本郷の誠之小学校や青山師範の付属小学校などが第1小学校と言われた。第1級の小学校になるため厳しい補習授業も行われた。私は試験勉強競争に、多くの子どもたちが遊びに感じる面白さを感じていたようであった。父は、5年が終わって資格試験を受けるとそのまま中学校へ進学できる(飛び級)ように考えて、小学校の先生を家庭教師にして試験勉強に邁進した。そして小学校を5年で終えて府立第1中学校へに入学することができた。
7) 空白5年1930年代の初め、東京府立第1中学校は日比谷から平河町に移った。各種学校を並立させたマンモス中学校だった。府立第1中学校はそのころ第1高等学校へ多くの卒業生を送る名門校であった。その受験予備校としての性格はプロの予備校教師によって担われた。満州事変が起きた年に府立第1中学校に入学し、中学校の5年間はほとんど一人の友達も見出すことはできなかった。そこでは基本的人権も議会民主制も自由民権運動の言葉は全く聞かなかった。授業は退屈であったにすぎない。教師たちはあだ名で呼ばれ「ネギ」、「ドブラ」、「テカ」などが記憶に残っている。
8) 美竹町の家中学校に入った頃、一家は宮益坂を上って右側の金王町から、左側の美竹町に引っ越した。土地は祖父の持ち物であった。祖父の屋敷より一段と高い崖の上にあり、反対側は氷川神社に接していた。住宅部分とはっきり区別された内科の診療室を備えていた。特に患者さんが増えたわけではなく、経済的には以前よりかえって苦しくなった。米と味噌は埼玉の田舎の実家から送られてきた。食べることを切り詰めたのではなく、買い物を節約したのである。妹は雙葉高等女学校に通っていた。祖父の家とは以前より近くなって、家の様子も聞こえてくることになった。大阪の会社員に嫁いだ叔母は、叔父が結核で亡くなると二人の子どもと共に祖父の家に戻った。祖父の貿易業の事業は1930年代の恐慌の痛手から立ち直らず、たくさんの借家を借金のために手放した。しかし祖父の女友達との交際はかえって盛んになって、祖母のヒステリーが絶えず聞こえてきた。父は祖父と祖母のいさかいに入ろうとはせず、母を祖父の家に仲裁にやらした。父は妻以外の女交際を不道徳とした。私は極度に禁欲的な家庭と軍国主義秀才教育の中学校を往復するだけの生活であったb。こうして祖父の家は傾いて借家は一つもなくなり、自分たちの住む家屋敷だけになった。古道具屋に家財を売ることもあった。祖父の家が傾いてゆくのに反して祖母の親戚は栄えていた。祖母の兄は大燃料店の副社長になって成功し、弟は海軍中将となって威勢が良くなった。海軍将校は若い時ロンドンに留学し、大使館附き武官をした。この叔父は揚子江艦隊司令官で艦政本部長となったが、「狂信的な国家主義者は必ず国を滅ぼす」という見識を持っていた。美竹町の家の診療室の2階の西南の部屋は父の書斎であったが、私は学校から帰ってから夕方はそこを使った。その部屋は夕陽をまともに受け富士山や箱根が見えた。この中学の5年間の記憶というと、道玄坂の西の空であったかもしれない。
9) 反抗の兆し私が活動写真(映画)を見るようになったのは祖父のおかげである。祖父は私たちを連れて活動写真を見て、その後有名な西洋料理店の店に行った。祖父は西洋の活動写真しか見なかった。若いころの西洋の事が思い出されてならなかったのであろう。渋谷の活動写真館には楽隊や「活弁」がいた。ただ活動写真館へゆくのはあまりに少なすぎため、活動写真の影響は受けなかった。むしろ文芸の世界に近づいたというものの「万葉集」しか知らなかった。意味から切り離された言葉(万葉仮名)を見た時、意味とは別の性質と可能性を意識した。万葉集が美竹町の2階の書斎の夕刻と重なっている。芥川龍之介の小説に感動し、同じ社会現象に新聞や世間が施してい入る解釈とは、まったく反対の意味さえ与えることができるという可能性に目を見張った。しかし高等学校の受験が近づいて来たので、小説を読みふけるという時間的余裕はなかった。中学でも4年の終わりに資格試験に通れば高等学校へ飛び級で行ける試験には失敗した。そのことで父との間に確執が生じたようであった。父は私が小説を読んでいたから受験に失敗したように思っていたようで、「文学青年」といった雑誌を軽蔑していた。受験勉強のため中学5年に最後の夏を信州の脇本陣の宿において過したとき、初めて文学青年を読んだ。そこで詩人立原道造などの文学少年にあった。
10) 2.26事件1936年2・26事件のなかに中学校を卒業した。中学生には全く何が起きているか想像もつかなかった。父の意見は、新聞と放送が検閲と自己検閲を通して、報道の自由のないところで選択し提供した情報に限られていた。南京陥落の事は知っていたが南京虐殺の事は父は知らなかった。「我々は何も知らされていなかった」という国民は、自ら最も自由だと信じていた時、最も不自由であったのだ。父は松岡国際連盟代表が脱退をした時喝采をしたが、陸軍の政治的影響力が大きくなってゆくことには反対で斎藤隆夫が議会で「粛軍演説」をした時は大喝采をあげた。これも情報の制限された状態での感情の動きで、父に合理性があるとも思えない対応であった。父の家庭内での発言は私にはほとんど影響しなかったようだ。交戦国の国民の大多数は、いつでも自国政府の立場に自分の立場を一致させるものである。(それは現在も領土問題でいえることである。北方四島問題、尖閣諸島問題、竹島問題では、国民はアプリオリに固有の領土という政府宣伝を信じている) 社会的には無力、医業開業に成功せず、父は仕事にどういう満足も喜びも見出すことはなかった。その人柄は責任感が強く、正直であったが、他人に不寛容であった。他人をこき下ろしては留飲を下げていたともいえる。そもそもこの世の中に低能で騙されやすい国民がいなければ、短時間で戦争宣伝が行き渡らず、国民総動員ができるわけがない。しかし父の徹底して実証主義的な懐疑主義は、すべて「神がかり」思想を許さなかった。支離滅裂な情報操作(隠蔽と宣伝)によって、国民大多数が支離滅裂な対応しか取れない時、私は多くの社会現象の連関を考え、一つの方向への社会の発展として理解しようと努めた。2.26の朝、ラジオ放送で陸軍将校のクーデターの事を聞いた。高橋是清蔵相、斎藤実内大臣、渡辺錠太郎陸軍教育総監、岡田啓介首相が殺されたことを知った。第一高等学校へ入学して、矢内原教授の「社会法制」という講義を聴いた。議会民主主義の終焉の日にその精神を語ろうとしたのである。軍部独裁への一本道がまっすぐ伸びている中での最期の講義であった。
11) 駒場第一高等学校が本郷から駒場に移って1年後に入学した。当時は全寮制で、駒場には一高以外には本屋、飲み屋、商店街も何もなく、渋谷に出なければ用は足せなかった。伝統や慣習の維持は第三者から見ると滑稽に映るのだが、「自治寮」制度はその最たるものである。寮委員会の形式上の民主主義は、また一種の個人主義と結びついていた。勝手気ままそのものであり、「弊衣破帽」は薄汚いだけであった。この自治の原則と個人尊重の風習が、学生の精神の「人間平等」に結び付いていたわけでなく、むしろエリート「選良」意識に裏打ちされ、大衆には許されない特権が自分たちには許されるという意識が強かった。一高―東大は天下国家に属すると自任していた。その小集団の内側での平等は、より大きなの不平等を前提として成り立っていた。一高時代の2年間はテニス部に属した。技術レベルは低かったと思うが、一高・三高戦に精神力を持ち込んで練習した。しかしその精神は必勝と結びつきやすく、合理性に反するものであった。「寮歌」や「酒宴」は微妙な意思伝達手段と解されやすいが、共同生活になくてはならぬもので、ごまかし、諦めや妥協、服従、ごますりを知ったのもこの駒場寮であった。ここで自己防衛の術を学んだ。集団への献身という精神は学ばなかった。
12) 戯画駒場の伝統的因習は寮だけでなく教場でもその「伝統」に忠実であった。教師は自ら教える価値があることを教えて、そのための予備知識は学生が何とか工夫するだろうとしていた。物理学の教師は学生の数学的素養は考慮しなかった。教場での質問は禁じられていた。質問されると授業がはかどらないからである。授業に出る出ないは学生の「自由」であって、「代返」も黙認していたが、試験では半分以上に及第点を与えなかった。詩人でドイツ語の教師片山教授は教科書にベルグソンの形而上学」ドイツ語訳を用いた。ここで片山教授の思い出、国文学の五味教授の思い出が語られるが省略する。駒場での3年間は寮や教檀の事だけでなく、歌舞伎座や築地小劇場に通ったことも懐かしく思い出される。歌舞伎では自分にはない権威に反抗する気配を潜めた遊人や侠客、盗人に惹かれた。築地では「新劇」のロシア文学「どん底」、「桜の園」など大正期を風靡した劇を見た。築地小劇場にも軍国主義の波が押し寄せていたが、反時代的な精神において客と舞台が一体化した空気が感じられた。私が西洋で発見したのは、絵画と彫刻、建築であった。その頃京都の庭園など日本の美術は何も見ていなかった。当時の日本人の油絵、建築物は見るべきものがなかったというべきだろう。思えば両大戦間の東京は不思議な空間であった。たくさんの西洋文化・文芸・美術が氾濫し、日本文化を忘れさせるには十分で、西洋を理解するには不十分であった。そういいう自分を、一時代の文化の戯画として、私自身がはっきり意識していたわけではない。
13) 高原牧歌中学校の最期の年の夏を信州追分村で過ごして以来、毎年7月にはこの村に秘書がてら勉強合宿に来ている。追分村は中山道から浅間に向かって少し入った林の中にある。展望は良かったが、ガス、水道はなかった。まるでキャンプ場だった。夏休みの大部分を妹と私で過ごした。妹はこの頃雙葉女学校を卒業し、家に入って母の手伝いをしていた。妹は東京の家の中では、父母の間を取り持ち明るくする存在となって、判断は決して愚かではなく人の気持ちに敏感であった。母は自分の気持ちにも敏感で信じることに従って争いも辞さなかったので、父との間に耐えず意見の食い違いがあったが、妹の存在で険悪にならなかった。良家の子女の慣習を破らず、妹には男友達がなく、私には女友達がなかった。8月の初めから東京から避暑客が集まり、「油屋」や「本陣」に住んだ。気の利いた寺では境内に長屋を作り学生宿泊場にした。東大英文科の中野好夫助教授も来られた。信濃追分駅の近くに、立憲政治家尾崎咢堂の長男尾崎行輝氏が八角堂の家を建て、東京に出ることもなく隠者のように家族連れで生活していた。飛行士をして発明に取り組みテニスにも凝っていた。追分で生活していた私は時折小諸や軽井沢に出かけたが、そこは東京の代用品であった。8月も末になると追分村は潮が引くように人がいなくなり、私の学校が始まる9月半ばころはもう秋だった。追分村の夏休みは10年以上も続いて戦後に及んだ。
14) 縮図30年代末に、第一高等学校の寮は、日本の社会の縮図であった。寮委員会の形式的な民主主義的制度と実際上の官僚支配。この小さな共同体はその内部において指導者とその成員の間に上下関係がはっきりしていた。個人の利益に優先するとされる共同体の目的は漠然として不明瞭であった。そこには文壇や報道機関に相当する「校友会雑誌」があった。同人雑誌でもあった。私は3年のときその編集者になった。駒場でものを書き、将来もの書きになる事に関心を持つ学生を知ることになった。そこには弾圧に生き延びたマルクス主義者もいた。戸坂潤を愛し、大森義太郎を愛読し、三木清に関心を持つ学生がいた。ドイツ観念論哲学、万葉集を原文で読む学生、詩人立原道造や中原中也や宮沢賢治、フランスの詩を読む学生、徳田秋声を祖とする自然主義私小説を試作する学生がいた。駒場と東京の文士と違う点は、それで生活の資を得ていないだけであった。政府は「国民精神総動員」と称して「ぜいたくは敵だ」という標語を作った。「大和魂・武士道・葉隠れ」は宣長の「大和こころ」とは違うし、そもそも武士道なんて言葉はなかった。江戸趣味に代表される永井荷風の「墨東奇譚」は軟弱な郭ものであった。こうした時代錯誤的な造語が氾濫しする裏でマルクス主義の弾圧と自由主義学者の追放が行われていた。京都大学の哲学者と雑誌「文学界」が西欧式近代を超克した、大東亜共栄圏イデオロギーを称賛した。止めどもなく進んでゆく軍国主義的風潮の中で、一高寮を取り巻くギャップは広がるばかりであった。日本の伝統文化を説く小説家横光利一氏が一高で講演会を開いた後の寮委員主催の座談会で「西洋の物質文明と東洋の精神文明」をめぐって矛盾が激突した。西欧の近代化を「禊ぎ」や「神国」で超克できるという横光氏の時代錯誤を鋭く突いた。当時日本社会は近代というにはほど遠い封建地主制度のもとにあった。
15) 古き良き日の思い出アメリカは朝鮮戦争で負けはしなかったが勝利は得られなかった軍部の無念を抱え、約10年後にはベトナム戦争でまた勝利無き撤退となった。その戦争の背後には常に共産中国があった。フランスにはアルジェリア民族解放戦争で挫折した経験は、その前のインドシナ戦争でイエンビエンフーでベトナムに負けた思いを引きずっていた。こうした経験は歴史を逆に読んでみると、戦前の日本の日中戦争に似ていたと言える。民族自立の独立戦争は軍部ではなく国民が決してあきらめない不屈の気持ちを背景にしている。日本では熱狂的な「愛国者」がその宣伝のすべてを「日本的なもの」に結び付けた。神がかり的に日本陸軍は無敵という程度の論理しかなく、愛国心は世界一という根拠のないデマを信じた。神武天皇が日本を統一したのは紀元前6世紀ごろに持ってこなくてはすまなかった、それで古事記に残る歴代天皇の在位を数百年と引き延ばした矛盾を狂信的に信じ込まされた。そういった非合理な「日本的なもの」に嫌気がさし、私は「西洋的なもの」を理想化するに至った。国民精神総動員は、都市向けの宣伝イデオログであって、農村ではパーマをかけた人も無く、ぜいたくは夢のまた夢という貧農の人には無縁のスローガンだった。私は戦争の性質を見極めることに関心を持った。中国との戦争は、道義上の罪悪であり、国際法上の侵略であり、戦略上のずさんさであった。私が南京虐殺の事を知ったのは、戦後の事であった。南ベトナムの子どもがどれほど殺されたかという数値も知らなかった。知ってもどうすることもできないという見解もあるが、無かったことにはならないし、「それでも知りたい」という人もいる。
16) ある晴れた日に1941年12月8日 ある晴れた日に太平洋戦争が起った。大学医学部病院へ向かう道で。ある学生が号外を読み上げていた事で知った。周りの風景が異様に鮮烈な印象を呼び覚ました。私の日常と世界がぷっつり糸が切れたようであった。それは終戦後母が亡くなった時もそうであった。その頃私は戦が近づきつつあることは知らなくはなかったが、英米を相手にして戦が本当に起こるとは信じていなかった。医学部の授業をいつも通りに受けて、家に帰ると、母はどうなるんだろうねと言ったが、私は「勝ち目はないね」と答えた。その日の夕方から燈火管制が敷かれたが、私は新橋演舞場の切符を持っていたので、文楽の興行を見に行った。やっているかどうかはわからなかったが、入り口は開いており、劇場には4,5人の客がいた。義太夫と三味線の世界が始まり、一部の隙も無い表現の世界が、女の嘆きを巡って展開された。真珠湾の大勝を聞いた東京市民は有頂天になり、、大学教授、雑誌、詩人、歌人は声を上げて勝利を歌い、大東亜共栄圏への道は開けたといった。日本軍は北へ向かう代わりに戦争継続に必要な石油資源を求めて南下政策をとることを予測したゾルゲに情報は正しかった。ドゴール・フランス大統領は「これで勝負は決まった」と喜んだ。渋るアメリカの背中を日本が押してくれたからである。これでファッシズム没落への展望がアメリカ参戦で開けたのである。世界中で喜んでいることを東京は知らなかった。島国日本は情報戦争で最初から負けたのである。アメリカ艦隊が極東南方の海に現れるにはまだまだ時間がかかったので、戦争が始まっても日常の生活には変化はなかった。家運の衰退した祖父は渋谷の土地屋敷を売り払い、目黒の小さな家に移った。祖父の美竹町の土地に家を建てた父と家族は、赤堤の借家へ引っ越した。祖父は陸軍の恩給と家財を売った金で生活していたが小説を書き始めたという。女友達との交友を思い出して書いているに過ぎなかったが、現在の中に生きる喜びを求め続けてきた人の、過去への執着心であった。於いた祖父は間もなく目黒の家で死んだ。父は赤堤の家で開業しなかった。伊豆の結核療養所で働き、東京に帰ってくることは稀であった。そうこうするうちに政府の言うことが微妙に変化した。「鬼畜米英征伐」や「必勝」という代わりに神がかり的な「絶対不敗の態勢」となり、守りに入った。この時点では私は疎開の準備も買占め行動もとらなかった。そもそも私は始めから戦争を生きてきたのではなく、眺めていたのだ。
17) 仏文研究室東京帝国大学では医学部の講義ばかりでなく、文学部の講義も聞いていた。まずフランス語の講座に出た。そこでは中島健三講師から仏文法を習った。辰野教授の「19世紀文芸思潮」、鈴木助教授の「マラルメ研究」、助教授の「モンテーニュ―」の購読などである。仏文科以外には芳光義彦講師の「倫理学」を聞いて、岩下壮一やカトリック神学にも及んだ。フランス文学にはカトリシズムの理解は必須であることに気が付いた。それは西洋の中世史の重要性に向かわせた。その頃の東大仏文科には個性のある俊才が集っていた。辰野隆、鈴木信一郎、中島健三、森有正、三宅徳嘉らが集ってだべる会にも参加した。仏文科の集まりには、ほかの世界とは遠く隔たったものがあった。それは権力を意識することなく何についてもかなり自由に話ができることであった。私が一番影響を受けたのは渡辺一夫助教授であった。渡辺氏は軍国主義的な周囲に反発して遠いフランスに精神的な逃避の場所を求めていたようだった。日本の社会の醜さの中に生きながら、そのことの意義をの中で見定めようとしていたのだろう。私は文科に出入りしてフランス現代文学端から読んでいた。渡辺助教授は16世紀の宗教戦争、異端裁判を周到綿密に研究されていた。そこの現在と同じ社会の狂気を見ていたのかもしれない。研究室の助手であった森有正・三宅徳嘉氏らとコーヒー店で談論した。そこにYMCAの劇作家木下順二氏も参加された。森有正・三宅徳嘉氏は戦争に騙されないという点でも渡辺助教授と同じように頑固であった。大学3年になった1943年、「学徒動員」によって卒業年限が1年早められ、4月卒業が前年9月卒業となった。私は医学部を卒業し、附属病院で働くことになったが、仏文科通いはやめなかった。神田教授のラテン語購読に参加した、キケロを読み、ウエルギウスを読んだ1944年英米軍はノルマンディ―上陸に成功し、ナチスは退勢を余儀なくされた。
18) 青春私は医学部に入って、間もなく肺炎から湿性肋膜炎になった。当時抗生物質は発見されていなかったので、生死の境をさまよい赤堤の家で療養した。そこで生きて居られることの喜びを感じ、死ぬことの不合理に恐怖した。人は死すべき存在というのは自分の内側の要因で死ぬことであって、外部の審判が介入することは創造主の神と言えども合理的な理由を見つけることはできない。長引く回復期を本を読んで過ごした。読書の興味の対象は自然や科学ではなく、文学、知的な領域に及んでいた。特に西洋の文学が、人間生活の感覚的・感情的・知的領域の全域にに関わっていることを知った。パスカルからダヴィンチ、そしてヴァレリーの「ダヴィンチの方法論序説」が私を虜にした。私は大学の仏文科にあるヴァレリーの著作を借り出すて読みふけった。それは文学の領域の事に限らず、人間存在全般にかかわった。赤堤の家の友人たちが集った。山崎剛太郎、中村真一郎、福永武彦、原田義人、窪田、中西らと読書会をやっていたのである。この朗読の集まりを戯れに「マティネ・ポエティック」と呼んだ。詩の脚韻の可能性を九鬼周造らと議論した。戦後日本語を素材として脚韻は成功しないという結論を出したが、それは19世紀のフランス語の脚韻に近づこうとしたからである。マラルメを踏み台にしていたからもともと不可能であった。詩は脚韻ではなく言葉であることを知った。そうこうしているうちにこの詩の朗読会の面々は戦争に取られていった。戦争が終わるまで誰一人帰ってこなかった。誰よりも生きることを望んでいた中西が死んだ。騙されて死を選んだのでもない。騙すことができなかった権力が物理的の彼に死地を強制したのである。水道橋の能楽堂に入った時、召集令状も、国民服もない世界に引き込まれた。シテは一人で足りる、舞台装置もいらない、芝居という言葉の究極の意味を発見した。
19) 内科教室東大附属病院の内科教室には無給副手として入局した。当時の名簿上医師の数は50名を超えていたが、軍医として招集された者を除くと実質は20名ばかりが医局に残っていた。食べることには問題がなかったので、市内の病院で働く必要もなく暮らしてゆけた。この医局で実験医学・実践医学を学んだ。中尾喜久、三好和夫氏から血液学一般の手ほどきを受け、血液や骨髄の細胞形態学を習った。誰のデータかで信用すること、自分で測り直さなければ信用するなという実験科学の基本を教わった。中尾喜久氏は血液学のみならず自律神経系なおどないか一般の広い知識を持ち、質問して知らないことはないというほどであった。敗戦直後の日米合同の原爆医学調査団に加わったのは、中尾氏の誘いによる。軍医の招集は大学病院の医局員の数をいよいよ少なくした。人手が亡くなっていけ餅患者の数が増えて仕事が多くなったので、ついに病院内の一部を借りて泊まり込みとなった。その頃太平洋の一つの島に米軍が上陸した。米軍は一度確保した島から撤退したことはなかったので、米軍が撤退し日本軍が挽回するかどうかで医局内で激論となった。「敗北主義」と言われて私は珍しく感情的になった。私は戦争を呪い、戦争宣伝とそれを受け入れた社会に怒っていたのだろう。私の周りでも、戦争の初期の勝利に酔い有頂天になっていた市民が、戦に疲れ、勝ち目のないことをそろそろ感じ始めていた。東京爆撃が現実となり、市街の1/3が焼き払われた後になって市民ははっきりそのことを自覚した。上野から深川にかけての下町は全滅した。やけどやけがをした患者が次々と病院に運ばれてきて、文字通り寝食を忘れて手当にあたった。我を忘れて働いたのは正直その時が初めてであった。
20) 8月15日1945年春、大学附属病院の内科は信州上田の結核療養所に疎開した。これは大学当局の指示によるものではなく、教授や医局のつてをたどって、東京から小数の患者と1/3の医局員が疎開したのである。父はすでに伊豆の療養所で医師として働いていたし、東京の家はなかった。妹は結婚して二人の子どもと母を連れて、信州追分村に疎開していた。浅間山の麓は疎開地として食糧生産には適さなかった。紙の紙幣はもはや信用を無くしており、物々交換しか信用されなかった。農村には若い男はいなくなっていたし、娘たちも軍需工場に取られていた。農民にも厭戦気分は広がっていたが、戦争が終わる気配はなかった。夏になると米軍は沖縄に上陸し占領した。そこから大阪、東京を空爆で焼き払い、艦載機で中小都市の爆撃が続いた。艦隊は日本の沿岸に現れ艦砲射撃を加えていた。日本には実質的抵抗能力は失われていた。「本土決戦」「竹槍戦術」などが勇ましく無意味に叫ばれたが、7月末のポツダム宣言無視は、軍隊の強がりに過ぎず何の策があるわけでもなく、本土決戦は権力者たちが、死出の道ずれに国民全体を巻き込もうとする陰惨な自殺行為に他ならなかった。8月10日新聞が「本土決戦、玉砕、焦土作戦」の代わりに「国体護持」を叫んだ時が、権力者の間に敗戦を受け入れる意見が支配的になったという表れであろう。8月15日「玉音放送」が行われ、終戦の詔が発せられた。片山教授は民主主義の勝利だと言って喜んだが、築地小劇場の俳優の鶴丸さんは冷静に「民主主義の勝利だって、そんなことはない。帝国主義の一方が勝ったに過ぎない。米国の占領軍はきっと、日本の支配階級を温存するだろうね、見ていてごらんなさい」と見通した意見を言う人もいた。私はポツダム宣言の民主化条項を信じて、民主化の徹底と経済的な復興がなされるであろうと考えていた。東京の焼け野原は、私にとって、単に東京の建物が焼き払われただけでなく、東京のすべての嘘とごまかし、時代錯誤が焼き払われたと思った。
21) 信条戦後父は宮前町で借家を診療所にして開業していたが、患者はほとんど来なかった。私の家族は戦争で誰もなくならなかった。家の前にはドブ川が流れ、隣では祖母と叔母と、その娘が三人で住み、祖母の年金と家財を売りながらつつましい生活を送っていた。宮前町から本郷の病院まで、電車を乗り継いで2時間、乗り合いバスで1時間足らずであった。焼け跡の男は」軍服で、女はもんぺや戦前の洋服を着ていた。やり手の男たちは闇市で儲けて輝いて見えた。配給では生活できない現状を実力でたくましく生き抜いていたのである。「戦後の虚脱状態」という文句もあったが、東京の市民たちは虚脱状態で途方に暮れているどころか、むしろ不屈の生活力にあふれていた。乗合自動車や電車の中には、傷病兵もいたり、戦争から帰ってきた男たちが元気でいい顔の市民に戻っていた。昨日まで大陸や南方で人を殺してきた人間とはとても思えなかった。性善説も性悪説も信じられなかった。米軍の占領が始まったときに、私は日本の後進性であるファッシズムが打倒され世界的な規模で民主主義の歴史になるだろうと予言した。それが私の信条であり、私の信条は正しかったと思った。封建的軍国主義から平等に基づく民主主義社会へ生まれ変わるのを米軍が誘導し、米国資本主義は潜在的な日本市場を育てるに違いないという「イデオロギー」の力を信じていた。私は身の回りの日本社会のおくれた状況を見てきたが、西洋の社会の進歩は本の上でしか知らなかった。国家権力の国内的対外的な行動様式についてはほとんど何も知らなかった。事実上の男女差別の実例を全く知らなかった。私にはどういう信条があったのだろうかを点検すると、①宗教的信条はなかった、②認識論的には私は懐疑主義であったが、具体的には疑い続けたわけではない、③道徳的信条は絶対的とは考えなかった、時代、社会で相対的にならざるを得ないと考えた、④私は臆病で青雲の志はなかった、つまり権力志向は全くなかった。⑤私は経験を持たず、いくらかの観念をもって戦後の社会に出発しようとしていたのである。
22) 広島広島には一本の木もなかった。見渡す限り瓦礫の野原が広がっていた。1945年8月6日の朝まで確かに広島市があったし、何万もの家庭と家があった。原爆爆撃直後確かに生きていた生命は、3,4週間後には髪の毛が抜け、血を流して死んでいった。その経験を潜り抜けてきた人はその話をしたがらなかった。「ピカドン」で生きた心地がしなかった後は口をつぐんだままである。私が広島に入ったとき、核兵器については何も考えなかった。広島の人を沈黙させた経験との距離をいつも繰り返し思い出していた。被爆者の苦しみ、痛みを取り去れるわけでもなく、治療の為ではなく原爆の効果を調査する科学調査団としての自分の立ち位置に掛ける言葉もなくしていた。被曝した時の位置と被爆者の症状を機械的に記録するだけの作業である。黙って東京へ帰るか、広島に留まるか、結局私は2か月広島にとどまった。爆心からの距離、遮蔽物の有無と材質、原爆病の症状である脱毛、血液標本の作製と所見に専心した。私は東京帝国大学医学部と米軍軍医団が共同で広島へ送った「原子爆弾影響合同調査団」に、日本側から参加した。日本側団長は外科の都築教授であった。都築教授は中尾博士に相談し、血液塗抹標本の分析を依頼した。ほとんどが「再生不良性貧血」の病変に似て骨髄に大きな影響が予想された。そこで中尾博士に同行して広島行きに同意した。占領軍医との接触はこれが初めてであった。米軍輸送機で人と機材・食料・車と共に広島に空輸された。
23) 1946年18)青春に書いた、赤堤の家で山崎剛太郎、中村真一郎、福永武彦、原田義人、窪田、中西らとやっていた朗読の集まりの連中が、戦死した中西を除いて戦後に再会して占領下の東京で同人雑誌「世代」を作った。私は福永武彦、中村真一郎と共に、共著「1946 文学的考察」を「世代」に連載した。小説という形式の将来を考察して、二人の小説家福永と中村は、東京の文壇で小説と考えられてきたものは、小説の一形式に過ぎず、「自然派流小説」は時代錯誤であるという論法を展開した。私は「新古今和歌集」の時代の歌人(定家、実朝)を研究し、「山家集」、「金槐和歌集」にはまっていた。京都大学哲学と日本浪漫派、高村光太郎と武者小路実篤が戦争で崩れ去った後、荷風と石川淳しか残っていなかった。そういうなかに病院に野間宏が雑誌「黄蜂」へ投稿を勧めに来た。私は「戦後文学」の時代が始まろうとしている予感を感じた。花田清輝は雑誌「総合文化」を主宰していた。詩人関根宏、物理学者渡辺慧、心理学者宮城音弥、心理学者南博氏らの活躍もあった。また「近代文学」の批評家たちとの交流もあった。「革命と文学」を論じていた。月刊雑誌「人間」の編集長木村徳三氏の依頼で私の原稿生活が始まった。小説「ある晴れた日に」を雑誌「人間」に連載した。そこで私は文筆を業として医を道楽とする生活を続けることになった。血液学の分野において日本ではほとんど進展がなかったが、米軍が徴用していた聖路加病院の図書館に出入りして、最近の欧米での進歩に目を見張った。血液凝固因子の研究から血漿タンパク質の電気透析法が生まれ、細胞形態学と血清学・免疫抗体反応・血液成分などが新しい領域として出現していたのである。日本のおくれを痛切に感じ取り、中尾喜久、三好和夫氏の臨床研究がはじまったのである。戦争中日本の文学者らはファッシズムに迎合して軍国主義を謳歌したが、同時期フランスでは反ファッシズムの抵抗主義文学が新しい潮流となっていた。日本の遅れと同時に私自身のフランス文学理解も遅れていることが明白であった。フランソワ・モリヤック、ルイ・アラゴン、ドリュ・ラ・ロシェルの著作を全く知らなかった。それだけでなく戦後俄かに一世を風靡し始めていたサルトルやカミュの文学が文学の範囲を拡大していることも知らなかった。遅れを取り戻す事ばかりに夢中になっていた私に、渡辺一夫先生は「本当に日本と日本人は変わったのだろか」という疑問を投げかけた。
24) 京都の庭この話は一見小説風に書かれている。京都の人とはだれかよくわからない。加藤氏は私的なこと特に妻については絶対秘密主義である。ウイキペディアでは妻は評論家・翻訳家の矢島翠と書かれている。加藤氏は「今まで三回結婚をしたけど」と言ったという。「羊の歌」でドイツ人女性と国際結婚をしていたらしいことも書かれている。「羊の歌」に京都の女というのが出てくる。加藤氏はそのとき結婚までいっていたんだけど、結局わかれてしまう。その経緯もよくわからない。京都の女という目でこの「京都の庭」の一説を読んでゆこう。その女のために私はしばしば京都へ行った。私は彼女を愛していると思っていた。東京で育った私には「京都弁」がたとえようもなく美しい言葉になった。若くして死んだ夫は仏教学者であった。子供が一人あって近所の小学校に通っていた。私は一人で京都の町を歩き、折節古寺を尋ねることをいつしか慣わしとした。龍安寺の石、西芳寺の苔、東山を借景とした南禅寺の枯山水に目をうたれた。私の外にあるものとうちにあるものとの一つの確かな関係に出会った。私は日本の庭に出会って以来15年も経って「詩仙堂志」(1964年)を書いた。その確かな関係がなければ庭に愛着ができない。古今集以来の歌にもつながり、一人の女の言葉の抑揚にもつながり、幼少のころ道玄坂に夕陽にもつながらなければならない。1949年、長く心臓をやみ、自律神経失調で健康にすぐれなかった母が、胃がんでこの世を去った。転移がなければ生きられたのに残念でならない。母が死んだとき私の内側が空虚になったように感じた。母の臨終にはカトリックの神父が立ち会った。母の信仰があったかどうかは確かではない。私が京都へゆくことを母は好んでいなかった。しかし私は結婚を考えていた。その時戦後第1回のフランス政府給費留学生の推薦に「半給費生」として選ばれた。京都の女が強く反対すれば出かけなかったかもしれないが、彼女は引き止めなかった。「1年後に帰ってきたら結婚しよう」という言い訳に、彼女は「そうね」と答えた。1951年フランスへ旅立ち、結局フランス滞在は4年に及び、京都の女の元へは戻らなかった。京都の女に関してはこれだけしか書かれていない。フィクション(小説)だと言われればそれだけの事であるが。
25) 第2の出発1945年戦後日本社会へ向かって出発した私は、1951年の秋西洋見物(医学留学生としてフランス留学)にでかけた。これが2回目の出発となった。私より1年前に来ていた森有正氏と三宅徳嘉氏がオルリー空港に迎えに来てくれた。パリ市街の灯も東京の灯もこの遠さを感じさせるものではなかった。飛行機で南回り航路二日間の旅は、香港からカラチ空港、ベイルート空港、アルプス越えでパリ・オルリー空港に着陸した。周囲の世界が英語を媒介として構成される世界に入ったのである。日常の事をすべて外国語で表現する他はないとすれば、私の考えに内容も影響を与えるだろうと感じ始めた。大学町の日本館という気宿舎に入居した。私はフランス・ブルターニュから来た学生と知り合った。彼と意見交換(論争)をしたことで、フランス語を話せるようになった。フランス語で話をすることは対して難しくはないが、ヴァレリーを読むのは容易ではないと考えるようになった。フランスの青年が母国語とその古典に結ばれているほど確かな絆で、私は日本語とその古典に結ばれてはいなかった。横に幅広い教養を「雑種」と呼び、縦に深い教養を「純粋種」と呼ぶなら、現代の日本人は雑種型に積極的な意味を見出すほかはない。大学町で米国の女性黒人画家と知り合った。その頃パリの在留邦人は少なかった。大使館はまだ開設されていなかった。外務省事務所の萩原大使た、彫刻家高田博厚氏、フランス文学者朝吹登水子さんらと知り合った。東京とパリの違いは、道の両側に並んだ石造りの建物が堅牢で、パリという街全体が一個の複雑な彫刻に見えることであった。私はそこに外在化されたすなわち感覚的対象と化した一個の文化の核心を見たのであろう。私は街を歩きながら、底知れぬ一つの世界へ自分が引き込まれて行くのを感じた。
26) 詩人の家第1次世界大戦の前後に、ロマン・ローランの影響のもとにあった青年たちが、旧僧院の建物を借りて芸術家の共同生活を営もうとしたことがあり、「僧院派」と呼ばれた。その中心人物は小説家デュアメル、劇作家ヴィルドラック、詩人レネ・アルコスであった。アルコス氏は妻と息子を病で亡くし、老いたアルコス氏は息子の嫁と二人でひっそりと住んでいた。私がパリに行ったのはその頃であった。学生街の日本館を去ってアルコス氏の家の2階に私が移り住んだ頃、アルコス氏は60歳を半ばを過ぎ、二人は絶えず議論をしながら生きていた。私は階下でアルコス氏と無駄話をしながら夕食を共にした。朝鮮戦争が長引いている頃だったので、アルコス氏は「アメリカ人は頭が悪い」といい、私は「アメリカ人の前提が共産主義者は悪魔だという間違った考えにあるからだ」と反論した。ロマンローランは明らかにこの人の上に影響を残している。ロランがその音楽や焼き絵ガラスや神秘主義にもかかわらず、人道主義者であり、国際協調主義者である、進歩主義者であった。アルコス氏は矛盾を感じないまま人道主義者であり、国際協調主義者であった。私はアルコス氏と冗談を言い合っているうちにこの人に親愛の情を感じた。アルコス氏は昼から酒を飲み夕方には呂律も怪しい会話に共感を感じた。息子の嫁ミシュールと朝吹女史と三人で芝居見物によく出かけた。フランス現代劇は理解しがたく、韻文の古典劇のセリフに私はついて行けなかったが、ミシュールは「なんという美しさだ」と興奮していた。サルトルが「悪魔と神」を書き、ブレヒトやベケットが現れる時代であった。私は現代劇より古典劇により強い興味を覚え、ジャン・ヴィラ―?の「ドン・ジュアン」を見たときは興奮した。モリエール、シェークスピアの良さを発見するまでにはまだ時間が必要であった。
27) 南仏老いた詩人アルコス氏を誘って「国際ペンクラブ会議」を見に、南仏ニースに出かけることになった。日本の作家藻会議に参加されており、田村泰次郎氏、平林たい子氏に会った。会議は午前中だけで、午後は物見遊山に出かけた。フランスの作家が弁舌をふるっていたが、学士院会員ジュール・ロマン氏は素晴らしいフランス語で無内容な演説をぶっていた。画家フラン・マズレール氏にも会った。20年前の友人の詩人片山俊彦はどうしているかと問われた。ロマンロランとマハトマ・ガンジーの出会いを賛美し東京で生き続けた詩人をもい出したのであろう。私は戦争中もマズレール氏の版画集を見ながら戦争を呪った。虚栄心だけのために「国際ペンクラブ会議」によくこれほどの文士が集ったものである。高尚で空虚な言葉だけで会議ができるのなら、文学はウソとごまかしでできている。
28) 中世1920-30年代に洋行した日本人は、その彼我の差に唖然としたことでしょう。誰の考えも二つの文化の相似な面よりも相違の面だけの心を奪われ、我国の悲惨さとフランスの偉大さという第1印章を拡大生産してきた。しかし1950年代前半にパリに行った男の目には少なくとも日常生活においては大きな差異は感じられなかった。私は両文化の差異よりも、相似を感じた。少なくとも自然化科学の研究面においては方法論的に同じであり、知的な面でも異国を感じることはなかった。根本的な違いがあるとするならば、その一つは言葉であり、もう一つは中世まで遡る歴史にあったと結論した。ようやくフランス語の不自由を感じなくなるとますます日本語との差異を鋭く意識するようになった。日本語の世界とは異なる別の精神的秩序の中に深入りすることに戦慄を覚えたという。ノートルダム寺院と中世の様式が、パリの景観の全体にとって決定的な要素であることに気が付いた。日本では鎌倉・室町時代の中世は平安貴族文化とは隔絶しているが、今も日本文化の基として連綿として続いている。それは文化の連続を意味する。15世紀西欧のルネッサンスは、ギリシャ・ローマ古代文明の掘り起こしに始まったが、欧州の中世の文化は今でも街の人々の中に生きている。それは連続しながら変わったので、断絶したのではなかった。半生をフランスで過ごした彫刻家高田博厚氏は、「文化とは形であり、形とは外在化された精神であって、精神は自己を外在化する」といった。私はフランスで中世美術を、美術の意味を発見した。京都の庭と和歌の世界、絵巻物から琳派の絵画まで思いを寄せなければならない。フランス人が「ランスの微笑」や「ピエタ・ダヴィ二ヨンの精神」を引用するように、彼らの文化と造形的世界との関係が、我々日本人とは異なるのである。もしイタリアがルネッサンスの国ならば、フランスはゴチック建築様式の教会なのである。
29) 故国の便故国の便とは手紙だけでなく、日本からの人の往来のことです。多くの日本人がフランスにやってきて、その人々との交友記録です。日本から総評の幹部がやってきて会議の通訳を引き受けた。フランスの労働運動にはかねてから興味を持っていたので、安い賃金であるが引き受けた。日本の労働運動の後進性ばかりが目立った。フランスに比べ使用者・資本家への要求が弱すぎるのである。勤務中の傷害保障、労働条件などすべてで及び腰で通訳不能となった。やはり企業組合主義の限界なのであろう。また国際代議士会議の日本語通訳もした。旧植民地国代表の帝国主義批判は激烈で、旧大国の受け答えは弁解的に聞こえた。またフランス上院議員が外交政策について日本の社会党代表に質問しても、なぜという質問に理論整然と答えられないのである。また志賀直哉氏と梅原龍三郎氏が自動車事故に遭った時、医者として診た。志賀直哉氏は、鋭い感受性、的確な言葉、徹底した自我中心主義、文学的唯我論に人であった。またNHKの放送員が病気になった時、宿舎で診た。ヘルシンキオリンピック実況中継で来られたのだが、尿毒症で今日明日の命であったので病院に入れたが、昏睡状態になって3日後に亡くなった。付き添ったデンマーク人の看護婦とシュヴァイツアー博士の事で討論となった。彼女は「聖人」だといい、私はそうは思わないと答えた。彼女はアフリカのシュヴァイツアー博士の病院で看護婦に応募したそうだ。アフリカに行ってから彼女から貰った手紙には、絶望したとは書いてなかったが、博士の立場の問題が綿々とつづられていた。植民地帝国の人間が、植民地において病院を経営する時、「聖者」になるまえに植民地帝国主義に対する見解をはっきりさせるべきだ。でなければ「偽善」である。加藤医師はどうもこの少女を好きだったようだ。
30) 二人の女24)京都の庭と30)二人の女と31)冬の旅 の節はどうも加藤氏の女友達の話である。フィクションのようにきれいに書いてあり、冷めた目で書いてあるので加藤氏が愛した女はだれかは判別できないが。この3節は「羊の歌」の恋情であろう。1950年代前半のパリでは日本人の話題は皆無に近く、ただ一つの例外はル・モンド紙の極東特派員として東京とパリを往復していたロベール・ギラン氏であった。加藤氏の友達の中で日本に興味を持っているのは、ギラン氏以外には左翼関係者であった。世界の反米運動を注視している証拠なのだが、彼らの日本の動向理解はまだ一面的であった。その中にルーマニア系のユダヤ人の女性と知り合いになった。熱心なスターリン主義者でピカソのスターリン肖像画を非難していた。欧米のソ連専門家からソ連を弁護する彼女の論法は旗幟鮮明であり、私の反論はむしろ懐疑的で何事も条件付きでないと賛成しない態度であった。彼女はパリにおける東洋人にたいする人種的偏見は根深いということを主張していた。私と彼女の関係は長くは続かなかった。再会することはなかった。パリの北部に「赤い帯」という共産党支持者の多い地区があり、そこで画廊を経営するある中産階級の婦人がいた。礼儀正しく、傲慢で、豊富な話題を持つ婦人と付き合っていてもすぐに退屈したが、彼女とは退屈することはなく、いつも生き生きとした会話を楽しんだ。彼女は夫と死別したが、静かで思いやりがあり、敏感であった。彼女の広い家に行くと、部屋の中には私と関係ない生活を記念する(別の男との生活)品物が多すぎ、少しも落ち着かなかった。私達は良い友達であったが、恋人以下であった。互いに盲目的ではなく、未来を夢見ることがなかったからだ。
31) 冬の旅オリエント・エクスプレスでパリから4ヶ国共同管理下のヴィーンに行く途中で、フィレンツェでその娘と同行した。近代ヨーロッパはイタリアの文芸復興にはじまる。それはフィレンツェとヴェネツィアを見なければわからない。ルーブル美術館だけでは不十分である。フィレンツェの丘の午後の後、彼女と二人でシエナに向かった。当時のオーストリアは4ヶ国分割管理(ヴィーンだけは共同管理)であったので、オリエント・エクスプレスが管理区域をまたぐ毎に車両に検閲官が入ってくる。ビザの手続きは大変面倒であった。ヴィーンに2週間滞在し、国立歌劇場場で、ヴァーグナーやアルバン・ベルグの音楽を聞いた。そこには音楽の質と聴衆の熱狂があった。劇的音楽は単なる音の楽しみではなく、感情生活の中心に係わる何者かになっていたようだ。美術館にいってブリューゲルを見て、コーヒーを飲み毎晩遅く彼女を家に送り届けた。私はパリ行きのオリエンタル・エクスプレスに乗って、彼女が振り返らず立ち去るのを見て彼女を愛していることに気が付いた。彼女との思い出は西ヴィーン停車場でで中断されたままになっている。ところが、私の世界の中心に彼女が入ってきた。私は京都の女を愛していたのではなく、そう思い込んでいただけの事だとはっきり理解するよぷになった。次にヴィーンに行く機会を求めたが、翌年春にある国際会議がヴィーンで行われる予定で日本代表が通訳を求めていたからだ。ベルリンから飛行機でヴィーンに入った。シェーンブルン宮殿の前でモーツアルトの管弦楽を楽しみ、私たちは幸福であった。このままで終わりたくないという決心をしたが、漠然とした気持ちで具体的に計画があったわけではなかった。
32) 音楽ヴィーン劇場でヴァーグナーに「トリスタンとイゾルデ」という悲恋の歌を聞いた時、私は恍惚として我れを忘れた。歌劇というものは退屈な通俗人情劇と美しい歌曲の二つの要素からなるものだが、その二つはさほど関連があるわkではない。ヴァーグナーを聞いて音と化した不合理性・破壊性・強迫性がヴァーグナーの本質であり、ドイツロマン主義の全体を定義すると思われた。ドイツの文化は体系的・組織的・合理的な完璧な体系を持つと同時に、他面において度外れて生々しく不合理な激情に満ちてという二面性を持っている。陶酔という言葉はナチスのヒットラーに通じており私は好まなかった。忘我という言葉も私は忌み嫌った。ところがヴァーグナーは暴力的に、不意打ち的に私に介入してきた。感傷的な旋律を吹き飛ばし、「わいせつ」という領域の恋の歌を歌うのである。?・シュトラウスの「薔薇の騎士」をおいて、女の声の美しさを語ることはできない。歌と旋律の関係は微妙である。シューベルトの「冬の旅」は歌詞が分からなくても楽しむことはできる。義太夫と三味線は関係がないと言ってもよい。それはフランスのシャンソンと同じである。言葉のおしゃれを楽しむものである。音楽は私の経験の体系のなかで、容易に置き換えることができない特殊な位置を占めるようになった。そのことは生涯の友人となった音楽評論家吉田和夫氏の導きがなければ、達し得なかっただろうと思う。
33) 海峡の彼方風の強い夕暮、波頭の白い海の彼方に、バラ色に染まるドーヴァーの白い崖を見た。白い崖を見ながら英国にやって来たという感慨にふけっていた。英国は不思議に東京に似ていた。欧州のどの都市も東京には似てはいなかったが、ロンドンのレンガ造りのビジネス街は丸の内に似ていたし、停車場付近は上野にそっくりの雑踏があった。学問、書物、医学はドイツ語で覚えていたが、日常的なものは私の育った環境の中に英国的なるものの断片が漂っていた。私が英文学の楽しみを知ったのは、中学校ではなく、カナダの外交官ハーバート・ノーマン氏の著作であった。日本生まれの外交官ノーマン氏を知ったのは、パリでユネスコ会議においてであった。英国の外交の仕事はカクテルパーティにあるようだった。私宅に招かれ彼が日本歴史の専門家であったことに驚いた。老子の本があり、バルトークの楽譜があり、日本語。中国語、フランス語に全く訛りがなかった。マレー語、アラビア語にも堪能であったという。英国文化に親近感があるとすれば、それは散文の「知的な侘び」(簡素性)にあったと思う。ノーマン氏はカイロで亡くなった。英国に上陸した私はアールス・コートの一軒家の安宿に住んだ。この下宿屋には多くの人種の人間が集まり、怪しげな男女が出入りしていた。私が英国に来た理由は、かのヴィーンの彼女がロンドンシティの投資会社の事務所で働いていたからである。彼女の叔母が料理人・家政婦をしている富豪の家にいって(主人が留守の時に)食事をしたり、一夜を過ごした。もう少しましな貸家を探して不動産屋の店頭に出かけたが、「有色人種お断り」とか「白人のみ」の但し書きが多かった。これは意外な英国社会の一面を見せつけられた。これは人種的偏見といえるが、日本社会を振り返ると、美人の基準は白人美女であったりするので、うかつに非難するわけにもゆかない。
34) 偽善オックスフォード大学美術館に勤める美術史家S氏、ロンドンの小説家などとの交流を書いているが、この節の本論とは直接関係はない。その中には田舎暮らしを好む人が多かった。江戸の昔「風流と俗事」という伝統的な二元論があった。ドイツ人は精神文化対物質文明の二元論を唱えていたが、政治は文明に属し文化の側にはない。それに対して英国人は「政治」と「精神」、「現実」と「理想」との関係は直接関係はなかったが、完全に切れてもいなかった。東京では左翼的政治的イデオロジーが濃厚な「政治と文学」論争が盛んである。パリでは東京の話題に似て、共産的人間、反抗的人間、組織と個人、革命と改良など、何が正しく、何を我々が欲するのかを議論していたようだ。しかし英国人は具体的状況で何を欲するのかというよりも、何ができるのかを考える習慣があるように思える。私が英国で覚えたことは、道義と政治を別物として扱うことではないということであった。太平洋戦争を民主主義対ファッシズムの戦ということは、今日の「冷戦」をみれば日本帝国主義とアメリカ帝国主義の程度の差に過ぎない。カミュは「反抗的人間」において、自由な人間は権力に反抗しなければならないが、反抗を組織するにためには個人を押しつぶすこともあると考えた。そこで道義的な価値と政治的な力関係がどう係り合うかという事であった。英国労働党のクロスマン氏は「反抗的人間」がこうも悲劇的に考えるわけが分からないといった。答えが得られない時は問題を変えなければならない。カミュの問題提起よりもクロスマンの問題提起が良い問題だと思える。相対的な価値を、力関係だけで決定されるのではない政治的現実のなかで、実現するにはどういう具体的な道があるのかと問う方を選びたい。条件付きでない答えを求めるのは不可能であり、意味のある答えは条件付きでしかあり得ない。そういう考え方はその後の私の政治的問題に対する態度を決定した。対象からの距離感と価値への自己拘束的思考との微妙なつり合いが私の政治にたいする態度となった。英国の外交政策が他国よりも偽善的であるのか、善(価値)を認めてなお偽善の必要性(アルタネイティヴ)も認めるやり方を議善と呼び棄てるのか。この節の大半はこの複雑な論議に費やされたが、最後にヴィーンの娘に対する私自身の「偽善」も告白しなければならない。英国での生活は苦しく、パリに帰ることを考えながら、一人で暮らすことはできても二人で暮らすことはできないだろう。そうすると別れしかないわけで、エジンバラの中世の教会を見る旅を最後にして愛する娘との別れを決意した。変わりゆく私とはいったい何者だろうか、「変わらぬ私」を想像することよりも大きな偽善はあるだろうか。
35) 別れ英国から帰って、フランスでの外国人労働の許可が下りた。これまでわたしはパリでの生活費を、日本の新聞への原稿料とか、通訳で賄っていたが、日本に組み込まれた生活では外国社会の文化を理解することは不可能であると判断した。フランスで暮らす限り、職をその土地に得ること、その職が表芸であることが望ましかった。私の表芸は内科学、血液学の臨床と研究であった。フランスの国立研究所に職を得るために外国人労働許可の申請をしていたのだが、審査が非常に長引き、忘れた頃に許可を得たのである。フランス留学は当初1年ぐらいで東京に戻るつもりだったが、フランス文化に一種の奥行きを感じて滞在は3年に及んだ。ところが私にとって第2の文化が、単に観察の対象であるばかりか。観察者そのものに影響を与え私を作り変えるようになると、その過程は非可逆的になる状況になるだろう。例えば小泉八雲のように帰化することになるかもしれない。二つの言葉を通じて考えることは、別の二つの事を考えるのと同じこと、おそらく精神にとって致命傷になるだろう。翻訳は本当の問題解決にならない。フランスで深入りすればするほど、日本語による考えから遠くなり、 また「去る者は日日に疎し」という様に日本で同じ経験を共有した友人たちから離れてゆくことになる。すべての具体的な経験はその特定の時間の中でしか起こりようがない。パリにいる限り、あたかも生涯をその地に暮らすであろう如くに、暮らし続けるほかはなかった。帰るべきか、帰らざるべきか、もし帰るならそれは近い将来でなければならない。私はロンドンで娘と別れてから関係を断つために手紙を書かなかった。彼女は突然パリの私の前に立った。すると英国での私の決心は忽ち変わった。京都の女との3人が不幸になるより、二人が幸福になればいいと計算したわけではない。私はすでに彼女と暮らすことを決めていた。私はフランスを離れる前に、彼女を連れて南フランスに出かけた。今度こそある意味で私たちの最初の旅になるだろうという予感がした。いつか彼女は日本にやって来るだろう。その旅の終わりに私たちは再び出会い、一緒に暮らすようになるだろうと確信していることを告げた。フランスから永久に去ろうとしているのではなく、滞在を中断しようとしていたのである。彼女は私の妻となり、その後の私は、しばしば欧州で暮らすようになった。(このくるくる変わる心境の変化と、あいまいな生活プランを結婚というのかどうか、難しいですね)
36) 外から見た日本三年間私は日本の地を踏まなかった。貨物船はマルセイユを出て、関門海峡を至るまでおよそ6週間を要した。それはヨーロッパ的なものが次第に遠ざかってゆく過程であり、アジアという自然的及び文化的多様性が次第に甦ってくる過程で会った。海路ではまだ英仏語が通じ、地中海気候は乾燥した空気と群青色の海を持っていた。船がインド洋を横切り、マラッカ海峡に入るとすべてが変わり始めた。空気は湿り海の色さえ変わった。熱帯の密林が波打ち際まで迫ってきた。シンガポールの埠頭と起重機、高楼、それは西洋とすこしも変わらなかったが、そこだけが密林で取り囲まれている。英語は商売の言葉であって生活の言葉ではなかった。無数の中国人が港で荷下ろしの仕事に従事していた。マニラでは当局が日本人の上陸許可を与えなかった。釜山でも日本人の上陸を許さなかった。もはやここまでくるとヨーロッパの影はない。冬の南シナ海は荒れ、玄海灘の波は高かった。北九州の岸壁が朝もやの中に現れ、工場の煙が立ち上って、瓦屋根の家や松が見えるとそれが三年間見なかった日本であった。日本の風土とは水墨画的な遠近法の世界の事ではなく、そこに住み着いた人間の歴史として私の前に現れた。北九州や神戸の港に似た風景はアジアのどこにもない。むしろマルセイユに似ているとさえ感じられた。アジアをひとくくりする漠然とした概念は再検討しなければならない。荷物を神戸港において私は京都の女のもとへ直行した。私は何のために帰って来たかを説明し、別れるほかはないことを繰り返した。彼女はそれを信じようとはしなかった。「また同じことを繰りかえそうとしている」という。ロンドンの女を深く愛したがゆえに、京都の関係がそれとは違うことに気が付いたという説明を信じないまま彼女と別れた。直ぐに東京へは行かず今日の寺や庭を見て歩いた。詩仙堂、大徳寺、八坂神社、仁和寺、六波羅蜜寺、神護寺、京都の冬は厳しい寒気と共に私の身体に染み通った。東京へ戻ると間もなく本郷の病院の仕事に就いた。私は妹の家に間借りをして。世田谷の上野毛片本郷に通った。本郷での勤務はあってないようなもので、ある鉱山会社の医務室に勤務した。医学的に興味があったわけではなく生活費を得るバイトのようなものだったが、独り身を養うには十分だった。週に一度は私立大学の文学部でフランス語の講義に出かけた。
37) 格物致知なぜ「格物致知」と題をしたのかは不明ですが、「物事の道理本質を追求し理解して、知識や学問を深めること」という意味です。日本に帰ってから雑誌や新聞に主として日本文化をどう見るかということについて書いてきた。そこで立てた仮説は二つある。①近代日本の文化は古来の良俗に西洋の学芸技術が混合した。純粋文化より劣っていないので純化する必要もないいわゆる「雑種文化」である。②日本の近代史は文化のあらゆる領域において、もはや明治以前と以後との関係を「断絶」と考える必要は無くなった。この2点を一般化し実例で豊富に裏付ける必要がある。売文業と医業の傍らの作業では-時間がなかったので、骨だけで肉付けがなかった。売文業のおかげで多くの同業者の知人を得た。作家高見順氏、フランス語学者の三宅徳嘉氏、音楽家吉田秀和氏、狂言評論家小山弘志氏、文芸評論家小林秀雄氏、作家石川淳氏、美術評論家寺田透氏やの蓄積に目を見った。これを文芸風流のめんいおいて徹底させるには画を見、書を読みに時間をかけるしかないと悟った。私が医業を廃する理由として、多忙だけが要因ではない。医学が高度に専門化して、私一人の人生と狭い研究の内容を橋渡しすることはできない。これは価値判断の問題で、目前の情勢の変化と将来の成り行きを一個の全体として考えるには、多かれ少なかれ価値判断と関係する仮説を樹てるしかない。私の生涯を左右した事柄のすべて(歴史)が、天災や運命でもなく、戦争という一連の政治的決定の結果であった。血液学という専門分野から文学の専門分野に移動したのではなく、専門化を廃したのである。そしてひそかに非専門化の専門家になろうとした。にもかかわらず容易には医業を捨てられなかった。しかし機会は中央アジアの作家協議会への出席を決心した時に訪れた。私は職を辞して出発し、再び医者の仕事には戻らなかった。
38) AA作家会議1958年10月中央アジアのタシュケントで第2回アジアアフリカ(AA)作家会議が行われた。ニューデリーでの第1回AA会議には日本から堀田善衛氏が参加され、第2回は伊藤整氏が日本代表であった。その国際準備委員会に語学力を買われ、1か月前から私が参加した。私はそれを機会に中央アジアとソ連邦を見たいと思い、一人で準備員会に参加した。インドのニューデリーで飛行機を乗り換えタシュケントに着陸した。機上からはパンジャブの緑野を過ぎ、パキスタンの山岳地帯からアフガニスタンの岩山が続くのを見た。中央アジアの無慈悲な自然、過酷な遊牧生活の歴史の果てに現在のタシュケントが目の前に現れた。当時定期便はソ連機しかなかった。第一印象は万事がヨーロッパと変わりなかった。私の計画は、ソ連の周辺に過ぎないタシケントからウズベキスタンを見学しインドの地方共産政権(ケララ州)を見て、そしてユーゴスラビアという「社会主義国の周辺」の比較見学であった。それは後に「ウズベック・クロアチア・ケララ紀行」という本になった。準備委員会の代表は、インドと中国から二人、モンゴル、タイ、ビルマ、カシミール、アルジェリアからも加わった。事務局はモスクワ作家同盟の書紀と3人の通訳であった。事務局の仕事は、宿舎、の割り当て、食事の手配、招待状の配布など事務的なものであった。途中でアルジェリア臨時政府の成立があってその政府を全面的に支持する声明の問題があった。私は大会決議に任せるべきだと主張した。また台湾沖の金門島砲撃での米中衝突問題の米軍即時撤退要求声明もアルジェリア臨時政府支持声明と同じ扱いとなった。作家会議が始まると、会議は魂の接触ではなく声明の連発となった。会議が終わると、私はタシケントの首都トゥビリッシを訪れ、モスクワからレニングラードを往復した。会議終了後直ちに東京へ戻らず、ヴィーンで過ごした。それからユーゴスラビアを見物し、ギリシャを通りインドに行った。インドの貧困は目を蓋わんばかりであった。
39) 死別一人の友人の死を悼んだ一節です。誰だとか書いてませんので特定できませんが、自分の分身との別れをもじっったフィクションとも取れますが、根拠はありませんので、その通りに志を同じくする東京に住む20年来の友人の死と理解します。恐らく末期がんで手の施しようもなく亡くなったようです。それが加藤氏には覚悟の上の病気の放置と見えたのでしょう。多くの物事の間に一種の関連が見えはじめ、そのことが自分自身の自覚とつながった矢先の死、そして仕事の準備をようやく終わった男がその仕事を始める前に死ぬのである。彼は欧州で彼女に会い恋に夢中になった。しかし東京に残した家族を捨てるつもりはなかった。強い責任感が恋愛を友情に変えたつもりでいた。激しく彼は傷つき、苦しんでいたに違いない。どういう犠牲を払ってまで生きていることは良い事だと思えるかと疑問に潰されたのではないか。「学徒出陣」でも「安保反対」でも権力に対して無力であったように、彼の死後私は再び東京を離れた。どこで働こうがやることは同じことだと思うようになり、新しい職があって海外に出ることになった。
40) 審議未了本節で「羊の歌」は終わる。1960年の安保改定騒動の中で、加藤氏は日本を離れたのである。1月日本政府は米国に出向いて新安保条約に調印した。新旧の条約の違いは次の3点である。政府の趣旨説明によると、①旧安保条約はサンフランシスコ講和条約調印とセットになっており、引き継いで米軍の駐留を可能ならしめる、日本にとって選択の自由がない占領期最後の条約であった。1960年安保は独立国日本が自ら進んで結ぶ日米軍事同盟である。②新条約は無限定から10年の期限として、米軍の日本駐留と日本国防衛の責務を明文化した。そして日本から米軍が動く際に「事前協議」を必要とする一項を付け加えた。③日本側は自国の防衛力強化を約束した。米軍基地に関する「地位協定」は米軍の軍事行動に制約を加えるものではないが、NATO並みの慣習に近いものである。政府は主に②と③を強調し日本側の地位の向上に努めたとしたが、反対側では①の軍事同盟は違憲である、軍備費の増大、アメリカの戦争に巻き込まれると言って反対闘争を組織した。加藤氏の見解は、安保条約は改定するより廃止すべきであると考えた。野党側は「国会を解散して民意を問え」といったが、政府自民党は5月19日衆議院に警察官を導入し、反対議員を排除して新安保条約を可決した。ここから参議院での審議未了による自然成立までの国会前の闘争が神原美智子さんの死を乗り越えて拡大した。この闘争で知識人をリードしたのは丸山真男氏であった。60年安保で多くの事を学んだのは権力側で、池田内閣の低姿勢と所得倍増論を柱とする高度経済成長路線が功を奏し闘争は鎮火した。1960年は私にとって、戦後の生活の結論の年であり、またその後の生活への出発点の年でもあった。