


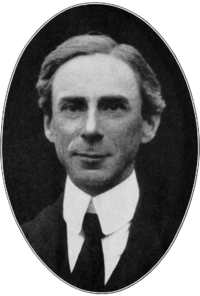
現代数学の創始者ヒルベルト 数理論理学の創始者ゲーデル 集合論の創始者カントール 論理学の創始者ラッセル



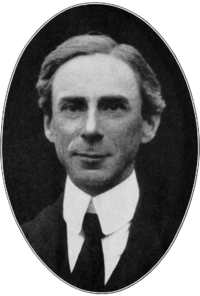
この本は数学(数学基礎論)と哲学(論理学)の中間を行く、いわば認識論と理解できる。むろんゲーデルという数学者が書いているのだから数学基礎論というべきかもしれないが、扱っている内容がラッセルの論理学の問題だからである。ゲーデル著「不完全性定理」という論文の内容は極めて難解で、数学の素人である私には皆目理解できなかったことをまず告白しておく。それでも訳者・解説者の方々の企画により、前後左右から何とかこの論文の数学上の意義を理解させてやろうとする励ましの声に煽られて、何とか本書を完読できた。断っておくが完読したことと理解できたかどうかは別ものである。しかし理解が不十分であろうとも読む価値はある。それはヒルベルトの数学上の業績を勉強しないでも、ヒルベルトのなしたことの意義を伝えようとする、C・リード著 弥永健一訳 「ヒルベルト」(岩波現代文庫 2010年)という本の役割と同じである。それでも本書はなお数学基礎論を基にした著作に偏っている。19世紀末から20世紀前半の数学の背景を理解することなしには理解はできない。そこで翻訳者・解説者の林晋氏と八杉満利子氏の略歴に触れないわけにはゆかない。林晋氏は1953年筑波大学数学科を卒業、龍谷大学工学部、神戸大学工学部情報工学を経て、現在は京都大学文学部現代文化学・情報史料学教授である。八杉満利子氏は東京大学数物系を卒業し、筑波大学、京都産業大学を経て、現在は京都大学文学部で数理哲学を研究している。本書のメインテーマである計算可能性関数(再帰関数)や数理論理学を専攻した。京大文学部の個人HPにおける自己紹介の弁は、「近年、数学における"計算可能性"が、数学研究のひとつの重要なテーマになっています。整数列や有理数列の計算可能性 は、何番目の要素の値は何かが自動的に計算できるもので"再帰関数"と呼ばれます。計算可能実数は計算可能な有理数列で近似され、近似の精度が再帰関数で 計算される実数です。計算可能連続関数は、計算可能な実数列を計算可能実数列に写し、再帰関数で連続の度合が測れるものです。積分は計算可能性を保存し、 微分は保存するとは限りません。不連続関数の計算可能性概念は、関数の定義域の位相を変えて連続関数の計算可能性に還元したり、関数値の有理数による近似 の精度として再帰関数の極限値をとる"極限再帰関数"を認めることにしたり、といろいろです。私の関心事は、再帰関数の極限という、無限遠点でしか値が決 まらない計算が、人間のどのような知的活動によって認められるか、ということです。それが不連続関数の計算可能性概念の基になっているからです。」と書いている。本書「不完全性定理」の数学領域の専門家といえる二人の訳者が解説してくれるのである。本書の第1部はゲーデルの「不完全定理」論文(1930年ウイーン科学アカデミィ―紀要)の翻訳である。論文であるので50頁に満たない短いものである。それに対して第2部が訳者による「解説」で230頁を占める。これは単なる解題ではなく、ひとつの時代の数学史(19世紀末から20世紀前半)となっている。そして面白いのはゲーデルが出てくるまでの数学の歴史の解説が大部分を占めており、現代数学の祖ヒルベルトを中心とする数学史と言ってもよいほどの分量の配分である。高木貞治著 「近世数学史談」 (岩波文庫 1995年8月)は18世紀末ー19世紀初めの近世数学興隆記となっており、ガウス、コーシー、アーベル、ヤーコビらの軌跡を記したものであった。そして高木貞治氏の描く数学界は本書のちょうど100年前の時代である。また高瀬正仁著 「人物で語る数学入門」 (岩波新書 2015年5月)はギリシャ時代から18世紀前半までの幾何学と曲線、関数、微分、数論の問題をテーマにしてガウスまでの近世数学史を描いたものである。本書「不完全性定理」の大部分を占める「解説」は20世紀前半の現代数学史を扱っている。形式主義、抽象主義、構造主義の現代数学は難しく、普通の人では理解不能である。本書の「まえがき」で、ほとんど予備知識のない人が不完全性定理の数学的内容を理解することは不可能であると宣言している。私などは本書の前で玄関払いされるのであるが、なぜなら数理論理学を理解しなければならず、本格的な教科書を予備知識としているのである。アインシュタインの相対性理論は特別な数学なしでも理解できるように書いてあるというものの、実は幅広い分野(物理、数学)の教育がなされているから理解可能なのである。ゲーデルの不完全性定理の理解に必要な数理論理学や集合論の教育は大学2年までに施されていない。かのフィールズ賞受賞者の小平邦彦氏も「自分には難しかった。なんとか分かったつもりだが自信はない」と述べているくらいである。ゲーデルの不完全性定理の分野は、関数論、代数学、微積分と言った普通の数学では理解できない、大学院生でも理解できる人は少ないだろうという。ゲーデルの定理はある意味では数学の定理ではないので、哲学的傾向の強い西洋文明の特徴であろうといえる。従って本書「不完全性定理」の解説はゲーデル研究やヒルベルト研究の成果を取り入れた独自の数学史となっている。ゲーデルの不完全性定理の解説の本というより、現代数学すなわちヒルベルトの数学基礎論研究論を中心とした数学史である。ゲーデルの第1不完全性定理が否定したのは、ヒルベルトの「数学の可解性」である。ヒルベルトの数学基礎論へのかかわりは「不変式論」に始まるということが訳者らの研究成果の一つだという。本書はゲーデルの不完全性定理をエポックとする基礎数学論争史となっている。だからゲーデルの不完全性定理が理解できなくても、その周りの背景をなす数学基礎論の論争史を学ぶことにしよう。第Ⅱ部の解説だけを紹介し、力が付いたなら第Ⅰ部のゲーデルの定理に入りたい。
C・リード著 弥永健一訳 「ヒルベルト」(岩波現代文庫 2010年)には、ゲーデルとの論争「数学は完全か」については、ヒルベルトがこの論文によってショックを受けた様子は書かれていない。数学基礎論については、若いオランダ人のブローウエルは短い論文で、これまでの論理学の法則が絶対的に正しいとする考えに異議を唱えた。彼は20世紀初めの集合論の矛盾の発見で引き起こされた「基礎論の危機」に決着をつけるプログラムを提出した。チューリッヒにいたヒルベルトの弟子ヘルマン・ワイルはこの問題に夢中になった。ワイルは1918年「連続体の論理学的基礎」を発表していた。心穏やかならないヒルベルトは、ブローウエルの考えはクロネッカーの亡霊の再来と思われた。ブローウエルは1911年にトポロジーの基礎を開き、点集合論は多くの数学者から評価された。ブローウエルにとって言語も論理学も数学の前提にはなりえず、直感のみが信じられるものであったという。ブローウエルは論理学の原理である排中律(アリストテレス以来、Aであるか非Aであるかのどちらかで第3の立場はありえない)を無限集合については認めることを拒否した。なぜなら無限であれば確認のしようがないからだ。1904年のハイデルブルグ会議以来、ヒルベルトはブローウエルの論文は一切読まないで、信念として「数学基礎論と数学的演繹法に関するいかなる疑念をも根拠のないもの」として退けた。1919年9月ヒルベルトはチュリッヒを訪れスイス数学会で「公理論的方法論を讃えて」という講演を行った。これはヒルベルトが1904年以来はじめての数学基礎論に関する発言であった。しかし彼自身はこの基礎論の危機には立ち入らないでいた。若い人の中に広がりつつあったブローウエルの直感主義的考えはまさしく数学への脅威と映った。ヒルベルトは存在論的発想を生涯の原理とした。「存在証明こそ科学の発展史上最も重要な里程標であった」と彼は主張した。1922年に行われたハンブルグの会議で、ヒルベルトは「ブローウエルとワイルは間違っている」と恫喝し、直感主義者(論理の約束事を無視する)のプログラムを受け入れると失われる数学の宝として、無理数の概念、関数、カントルの超限数、排中律、無限個の自然数が持つ最小値定理などを挙げた。彼は数学をあるシステムに形式化し、そのシステムにおける事象は論理学の言葉をもって記述され、そこにおいて構造のみが重視され命題の意味は問題とされないというかっての「幾何学基礎論」で展開された公理主義を繰り返した。 ベルナイスはヒルベルトと共著で「数学基礎論」を執筆した。ヒルベルトにとって終生の敵はクロネッカーであった。どうしても数学の健全さを信じて厳密性を守りたかったのであろう。ミュンスターでワイエルシュトラスを讃える祝典でヒルベルトは「無限について」という講演を行った。ワイエルシュトラスの解析学、カントルの無限の概念がクロネッカーの攻撃にさらされた時を振り返って、ヒルベルトは現実には存在しない無限の意味を、シンボルとして真の意味で存在するものであるという。ヒルベルトは数学における命題と証明をシンボリカルな論理学用語を用いて形式化し、研究対象とすることによって数学の本源的な客観性を回復することが可能であると論じた。ゲオルク・カントルによって創造された理論が集合論である。ヒルベルトは集合論の矛盾を暴くクロネッカーが許せなかった。「もしも数学的思惟が欠陥をもつものであるなら、一体我々はどこに真実を求めたらいいのだろう」とヒルベルトは叫ぶ。この集合論のパラドックスを回避する、完全に満足のゆく方法が存在する。自然数の演算は確実である。パラドックスは我々の不注意に過ぎない。我々はアリストテレス流の簡明な論理法則(排中律)をあきらめたくはない。そのためには有限的命題を補完するのに理念的命題をもってしなければならない。1930年11月25歳の数学論理学者クルト・ゲーデルの論文が数学誌に掲載された。この青年はヒルベルトが1928年のイタリア国際数学者会議で提起した数学基礎論の完全性に関する2つの命題を取り上げて、形式化された算術の不完全性を証明したと称した。また有限の立場に立つ形式的体系の無矛盾性は証明しえないといった。この論文の翻訳は、岩波文庫の「ゲーデル 不完全性定理」として刊行されている。論文本文は50頁足らずであるが、林晋と八杉満利子による解説は230頁を費やしてヒルベルトプログラムとの関係を論じている。ヒルベルトはこの論文を見て、クロネッカー、ブローウエルの挑戦に最終的解答を与えなかったことを理解した。クロネッカーの亡霊は今も生きていたのであった。形式主義の枠組みが、いまだ十分に強いものではなかったことを知らされたのである。ヒルベルトは人生の最後の段階で、この批判について前向きに修正を加えようとした。つまり形式化に関する要請を緩め、帰納法を「超限帰納法」によって置き換えようとした。
1) 不完全性定理とは何かゲーデルの「不完全性定理」は19世紀に始まった数学基礎論に、実質的な終止符を打った歴史的な定理である。数学基礎論とは狭い意味での理論論理学の意味ではなく、19世紀末から20世紀前半まで隆盛を極めた、「ヒルベルト計画」推進派とその実行不可能性を主張する反対派との数学運動論争史にことである。ヒルベルト計画は、数学における合理性を究極の形で実証する近代ヨーロッパ的な目的を担った数学運動である。合理性に対する素朴な信頼に無慈悲なノーを突きつける形になった。そのため数学の定理のみならず、哲学、心理学、現代思想、情報科学への影響は大きかった。本書は不完全性定理の成立の歴史的経過を説明することが目的となる。解説は①導入部 第1章、②歴史部 第2-5章、③検証部 第6-8章の3つの部分により構成される。本書解説では専門知識(数理論理学)がない読者にも、ゲーデルの定理の数学的意義を理解できるように書かれたという。歴史部 第2-5章にはゲーデルの定理が現れる歴史的背景を叙述したもので、定理は最後にしか現れない。登場人物はヒルベルト(1861-1943)らの数学者・哲学者が主人公である。中心はドイツゲッチンゲン大学にあって、クルト・ゲーデル(1906-1978)がいたウィーン大学は数学界の周辺に過ぎなかった。誰も注目していなかったのである。ゲーデルの前には1世紀以上の数学基礎論の歴史が存在していた。ゲーデルの不完全性論文とは、1931年ウィーンの数学専門誌に掲載された。むろんヒルベルトの注目するところとならなかったし、ヒルベルトは読んでもいなかったようだ。この論文には2つの定理があり、
①第1不完全性定理:定理6 数学の形式性 形式系と呼ばれる論理学の人工言語で記述された数学は、その表現力が十分豊ならば、完全かつ無矛盾であることはない。
②第2不完全性定理:定理11 数学の形式系の表現力が十分豊かならば、その形式系が無矛盾であるという事実は、その形式系自身の中では証明できない。
言葉を変えていうと、①より、数学は矛盾しているか不完全である。②より、数学の正しさを確実な方法で保証することはできない。この命題を数学基礎論の歴史的文脈に置くと、「数学の絶対的な基礎づけは不可能だ」ということになる。ゲーデルの定理が数学基礎論に一応の終止符を打つことになった。この命題を巡って様々な人の意見が現れた。「人類の知の限界」という意味のことを言う人もしたが、ゲーデル自身は終生その意見を貫いた。不可能性≒不可知論を主張するフォン・ノイマンらがいた。人文科学系の人々には「絶対的真理としての数学」という常識から自由な人が多かった。ゲーデルの定理の解釈の多様さ、不安定さは著しかった。上に述べたゲーデルの定理6,11は「数学的不完全性定理」と呼ぶ。命題1'と2'は数学の定理ではなく、言い換えに過ぎないので「数学論的不完全性定理」(数学についての議論、すなわち数学論)ともいえる。この数学的不完全性定理(定理6,11)と数学論的不完全性定理(命題1'、2')の二重構造が誤解のもとになっている。ヒルベルトのテーゼとは数学=数学の形式系という条件を仮定する。これはヒルベルトの数学観なのである。ゲーデルの定理はヒルベルトのその数学的実証性を保証することはできないということである。ゲーデルは知性の不可知論を言ってるのではなく、ヒルベルトのテーゼが単純な意味では成り立たないと言っているのである。だから数学的不完全性定理からヒルベルトのテーゼまで否定しているわけではない。数学や科学や合理性に対する自らの立場の表明がヒルベルトのテーゼである。ヒルベルトのテーゼは、現実の数学の理論が数理論理学の概念である形式系によって忠実に再現できるので、命題や証明に機械的定義が与えられ、意味論抜きにコンピュータ処理ができることである。これを「数学の基礎づけ運動」という。数学論としての不完全性定理は、人文・社会科学の理論と同様に、歴史的文脈から切り離すと、その意味が半減する。20世紀数学方法論の方向を決定づけたのが、ドイツの数学者ヒルベルトであった。ヒルベルト計画とは次の3段階を実施する研究プロジェクトであった。①第1段階:ヒルベルトのテーゼの基礎づけ、数学を形式系に写し取ること ②第2段階:形式系の無矛盾性の証明 ③第3段階:形式系の完全性の証明である。哲学者バートランド・ラッセルや数学者ノ-バート・ウィーナーのように醒めた目でヒルベルト計画を評価する人がいたし、数学者ブラウラーのようにこのプロジェクトに猛然と反対する人がいた。ヒルベルト計画推進派の人々は熱心にこのプロジェクトに取り組み、ゲーデルの定理発見までは、自然数論から実数論まで楽観的であったという。ゲーデルはこの第2段階と第3段階が実行不可能であることを発見し、近代ヨーロッパ的な数学運動に終止符を打った。セントラルドグマは道半ばにして葬られた。
数学の厳密化は19世紀には「算術化」と呼ばれ、有限算術化と無限算術化の二つがあった。算術化とは数学的知の代数計算化、すなわち意味不要の規則的演算に還元する意味で機械化でもあった。数学の厳密化は1821年パリのポリテクニークのコーシー(1789-1857)の「解析学教程」で始まった。微分積分学は無限小の概念を用いて「無限小解析学」と呼ばれた。ニュートンやライプニッツの時代の数学者にとって、解析学とは無限級数の代数計算によって幾何学的曲線論を解く方法であった。ライプニッツ(1646-1716年)は万能の接線法を開発した。1666年ライプニッツはドイツから出てフランスンのパリに移り、デカルト、ホイエンスの薫陶を受けて近代数学に輝かしい業績を残した。ライプニッツは1684年と1886年の二つの論文で微分計算法と積分計算法を確立しました。曲線状の無限に小さい距離を持つ2点を結ぶ直線が接線であり、代数方程式で表される曲線でも超越曲線でも接線を引くことができると主張しました。当時の解析学は計算が必ず正しい結果を出す保証はなく(級数が収束しなければ)、解析学は論理的にその正しさが保証されていたというより、物理や天文学、数学での応用で実用性が試されるという経験的事実に支えられていた。案外解析学の基礎は曖昧だったのです。物理と同様に経験科学だったいえる。コーシーは解析学の厳密化の標準を数学教育の方針とした。コーシーは無限小を変数と考え、極限がゼロとなる変量を無限小と呼んだ。コーシーは「自律的判断基準」を重んじたといえる。物理や幾何学、応用など他の判断を参考にせず自分で自分の判断の正しさをチェックしなければならない。しかしなおコーシーの解析学には、連続関数は微分可能だとか、無限小の極限の定理(変量と定数の差をいくらでも小さくできる)には曖昧さが残っていた。この無限小の厳密化にはワイエルシュトラウス(1815-1897)のεーδ論法が必要であった。ワイエルシュトラウスは連続であっても微分可能でない関数の存在を示して解析の厳密化を進めた。ワイエルシュトラウスの自立的判断基準とは、極限の論理的定義である。ワイエルシュトラウスはコーシーの極限の概念を次のように厳密に定義した。実数xに対して0<|x-a|<δ(aは正の実数)が成り立つなら、|f(x)-b|<εとなる。この定義は実は分かりにくい表現である。分かりやすい表現だと各自がかってに想像が働いて、異なった見解になることがある。そこで杓子定規に定義通りに解釈せざるを得ないような縛りを加えた定義である。分かりにくさが自律性と厳密性に結び付くのである。この厳密性をワイエルシュトラウスの厳密性と呼ぶ。ワイエルシュトラウスの極限の定義は、実数と「任意の」、「満たすなら」、「存在する」、「成り立つ」、「ならば」などの論理的言葉を基本としている。整数、実数、複素数などの数とその計算の体系を「算術」と呼び、ワイエルシュトラウスの厳密性を解析学の算術化という。このコーシー・ワイエルシュトラウスの解析学の算術化により、解析学の極限概念は算術に還元された。そのためにワイエルシュトラウスは実数の連続性を有理数の算術を基に厳密に定義し、その連続性を証明した。有理数の集合を実数と見なすことによって実数の定義を与えた。この定義方法を「実数の発生学」と呼ぶ。1850年代にドイツのデーデキント(1831-1916)も有理数の集合を使って実数を定義した。カントール(1845-1918)も有理数の列によって実数を定義した。カントールは1870年に「フーリエ展開の一意性定理」を解き、その中から集合論という無限についての数学が生まれたのである。集合の構成要素には個数という特性がある。無限の個数の考えを無限集合に拡張する時、新しい数学理論を建設した。素?がカントール集合論である。自然数という集合Aと実数という集合Bの無限集合の個数を比較して集合の大小関係を考察する時、カントールは「1対1対応が存在する」条件に置き換えた。1対1対応とはAからBへの写像〈関数)で、その関数によってBの要素にAの要素が一つだけ写像されたという。有限集合なら玉入れの玉の数を数えるのと同じことになる。1874年カントールは1対1対応の概念を使って、無限の個数を定義し、実数の集合と自然数の集合は同じ数ではないことを背理法で証明したのである。カントールは要素の数を濃度と呼んだ。実数の濃度は自然数の濃度より大きいと解釈できることで無限の数学が生まれた。無限という概念は実は1871年デーデキントがイデアル代数を無限集合を使って定義していたが、それ以上の進展はなかった。カントールは平面上の点と直線上の点の数が同濃度であることを発見し、無限集合論につながった。カントールの集合論は「超限数論」で、超限数とは、自然数の無限への延長である。超限崇には個数を数える基数という役割と、1番、2番という順序数の役割がある。
19世紀には新しい数や空間が発見され、カントールの超限数はその一例である。これら新しい「数学概念の存在」がすぐさま当然視されたわけではなかった。フランスの数学者集団「ブルバキ」が数学の近代化運動という厳密化運動を当然視したのは第2次世界大戦後のことである。19世紀の数学者にとってこれら新しい「数学概念の存在」は自明ではなかったのである。イギリスのド・モルガン(1806-1971)は数学の厳密化近代化に力のあった人で、数理論理学の先駆的研究で知られた。彼はマイナスの数の存在さえ疑わしいとした。生まれたばかりの集合論の批判者は多かったが、なかでもクロネカー(1810-1893)はカントオールの集合論を攻撃した。集合論の数学への本格的応用としては、デーデキントのイデアル論、その師クンマー(1810-1893)の理想数理論は代数的整数論のために開発されたが、1897年「数論報告」によってヒルベルトがこれを継承した。クロネカーはデーデキントのイデアル論に対抗すべく、有限の代数式とアルゴリズムを使う構成的「モズル理論」(一般算術の理論)を提案した。デーデキントのイデアル論は躊躇なく無限を使うので、クロネカーの批判を受けたのである。この有限主義的態度は19世紀の代数学者にとって当たり前で、カントールの無限数学は「哲学的」過ぎると言われた。19世紀には、超限数の他、非ユークリッド空間、n次空間、ブール代数など新しい空間や数が生み出された。カントールの集合論には、無限集合は分割しても個数は減らないという不思議な性質を持つ。自然数全体を奇数と偶数に分かっても元の集合と同じ個数を持つのである。ベルリン大学の教授であったクロネカーの影響力は、工業高校の教師であったカントールと較べようもなかった。しかしカントールの無限集合は、ヒルベルトら若いドイツの数学者から支持を受け、ドイツ数学者協会初代会長に選出された。ワイエルシュトラウスの解析学の無限算術化とクロネカーの伝統的有限算術化の二つの流れがあった。例えばラッセルの無限算術化で, √5を定義すると、X^2<5を満たす有理数の全体からなる集合となるが、クロネカーの有限算術化ではx^2=5と定義される。20世紀数学の主流派であったヒルベルト学派からは、クロネカーは旧習派と見なされるが、現在では「集合と論理の代わりに、代数式と計算を用いる数学の基礎づけの試み」と位置付けられている。無理数や連続の概念はクロネカーの受け入れるところにはならなかった。しかしこのカントールの流れこそ、コーシやワイヤーシュトラウスの無限集合を継承するものであった。はたして無限算術化の生産性・拡張性は有限算術化のそれを凌駕したことは歴史が証明した。こうして若干は胡散臭さを感じながらも数学者はカントール、デーデキント的数学を受容し選択したのである。実際、計算アルゴリズムの「巨大すぎる有限性」は「質のいい無限」よりはるかに始末が悪かった。ヒルベルトは数式操作の達人と言われたが、当時の代数学の計算複雑性は彼の能力をしても太刀打ちできなかった。余りに使い勝手のいい「哲学的・神学的方法」は一度根本的に破たんした。いわゆる集合のパラドックスの発生がそれである。カントールは1891年に「対角線論法」という巧みな論理を使って、「任意の集合Xについて、Xの濃度よりも大きな濃度を持つ集合Yは必ず存在する」の問題を解いた。集合Xの部分集合をすべて集めた集合を「べき集合」P(X)というが、「べき集合」P(X)の濃度は、集合Xの濃度よりも大きいという定理を導いた。これによっていつでも元の集合より大きな集合を作ることができるとカントールは考えた。これがカントールの命取りになった。一番大きな集合は存在しないことになる。この矛盾を「カントールのパラドックス」という。カントールからヒルベルトに宛てた1897年の書簡では、「すべての集合の集合」のような矛盾を導く無限集合(矛盾的多数)は本当の集合(無矛盾的多数)とは異なるとパラドックスを説明した。カントールのパラドックスは無限数論の矛盾であるが、初期集合論の崩壊をもたらしたのは「ラッセル・パラドックス」という論理主義的集合論の矛盾であった。
3) 論理主義、数学再創造とその原罪(1884-1903)自然数より単純な数は存在しないから、これを論理に還元しようとする動きを「論理主義」と呼ぶ。デーデキントは「数について」で自然数の発生学を興した。カントールやデーデキントは無限集合から自然数を作り、有理数から実数を作ったが、記号論理学を使った論理の厳密化・数学化をしていないので、これを論理主義に分類しない。ドイツの数学者フレーゲ(1848-1925)は自然数を有限基数として論理的に定義した。フレーゲは記号論理学・分析哲学の祖と言われている。1対1の対応という「ひとつ」から始めなければなりません。1という自然数を定義するのに1を用いては論理的ではないからです。そこで何も要素を持たない集合(空集合)を定義して、空集合を要素として持つ集合に対応する集合を1と定義する。ひとつづつ空集合を合わせて順次2,3,4を定義する。この定義はイタリアの数学者ペアノ(1858-1932)が提案した自然数の公理(ペアノの公理)です。「対応」、「集合」、「等しい」などの概念が使われたので、自然数は論理から発生したといわれる。カントールは無限集合から出発して数学を構築することであったが、論理学によっても個々の自然数や自然数の集合を導くことができた。論理学は論理だけを使って数学を再創造することができたのである。自然数の発生学を展開したのはフレーゲであるが、論理によって全数学の発生学が可能であることを示したのは、イギリスの哲学者バートランド・ラッセル(1872-1970)が1903年に発刊した「プリンシプルズ」が初めである。これが真の論理主義の始まりであった。フレーゲが「概念文字」と呼んだ記号論理学を用いて展開した理論である。ラッセルはペアノの論理学を改造し、今日の記号論理学あるいは数理論理学はこのペアノーラッセルの論理学の延長線上にある。「プリンシプルズ」は20個の記号論理学の原理(述語論理概念)だけから数学が発生することを示した。ラッセルは集合を類と呼んだ。1903年ラッセルは「ラッセルパラドックス」によって挫折を味わう。集合xの行と集合yの列の行列の交点に、「xはyの要素である」という条件が正しい時はyes、そうでないときはnoと入れると、もしxとyが同じ集合であるなら、対角線上には「xがxの要素である」が並ぶことになる。「べき集合は元の集合より大きい」ということがこの対角線論法で証明された。これは「カントールの定理」であることを?セルは知っていたが、このラッセルパラドックスは論理学の根本を直撃する矛盾となった。このパラドックスは「この文章は偽である」という「うそつきのパラドックス」と同じとなった。集合sがsの要素であるとすれば要素ではなく、sがsの要素でないとすれば要素であるという論理構造となる。このパラドックスはアリストテレスの論理学以来議論されてきたが解決策はなかった。多くの数学者はカントールの集合論に対して新たな困難を投げつけた。この集合論が新たな数学を切り開くための不可欠の言語であると認識する一人がヒルベルトであった。
4) ヒルベルト公理論 数学は完全である(1888-1904)1900年パリで行われた第1回国際哲学会議に参加したラッセルは、ペアノに強い衝撃を受け、記号論理学の研究を開始し、半年で「プリンシプルズ」の根幹部分を固めたといわれる。同年国際会議の一環として行われた第2回国際数学者会議でヒルベルトは「数学の問題」と題した講演を行い、ヒルベルトの数学思想である「形式主義」を初めて公表した。3年前カントールから集合論のパラドックスを聞かされていたヒルベルトは集合論のパラドックス克服の戦いを開始した。若いヒルベルトは、デ-デキント・カントールの方法を代数学、整数論、幾何学に展開して、新世紀の指導的数学者の候補になりつつあった。この講演でヒルベルトは23の問題(この会議では10、あとは後日論文で追加)を提起して、新しい数学像を指導した。「すべての数学問題の可解性の公理」(解けないという否定的解決も含めて、信念というべきか)は純粋思惟によって解決できると宣言した。数学に「イグノラビムス(不可知論)」はないということである。限りない数学的知への信頼と誇りの表現であった。ヒルベルトは「熱い人間」なのだ。その後可解性思想は進化し続け、1920年代の「ヒルベルト計画」にまで発展した。答えはイエスかノーしかない、中間はないとする排中律を否定する論であるブラウワーの直感主義はこの可解性への反発から生まれたのである。数学の形式系の完全性も、この可解性思想の一定式化であった。ヒルベルトの「数学の形式系の無矛盾性」は「実数の無矛盾性」から始まった。1900にヒルベルトが書いた「数の概念について」はクロネッカーへの反論であった。クロネッカーはデ-デキント・カントールらの無理数論が無限の概念を利用することを非難したが、ヒルベルトは「存在=無矛盾性」ていうテーゼで切り返した。ヒルベルトは無限集合を使って実数を発生させるのではなく、公理主義の考えから、「有限個の公理から有限回の推論の繰り返しで結論を得ると決して矛盾は生じない」定義した。クロネカー亡き後も、ヒルベルトはカントールのパラドックス(すべてのアレフ問題)、ツェルメロ(1871-1953)のパラドックス、ヒルベルトのパラドックスと戦い続けた。これを「クロネカーの亡霊」とよぶ。数学を公理からの演繹で構築することは、ギリシャのユークリッド幾何学以来の伝統である。ところがヒルベルト公理論では、論理的依存関係で結び付けられた定理・概念のネットワークとして数学を理解する現代数学の特徴的なやり方である。一つ一つの定理(命題)というレンガ積みから、それらの相互関係に興味が移った。縦の依存関係(主従)から横の関係性(独立、形式性)を重視する。ユークリッド幾何学では平行線の公理を他の公理から導くことはできないことを、他の公理からの独立性と呼ぶ。ヒルベルトは公理が無矛盾だけではなく、互いに独立であることを求めた。その方が数学者の生産性が飛躍的に高まる。ヒルベルト公理主義の本質は「数学をシステムとして捉えること」である。このことは、D.ヒルベルト著 中村幸四郎訳 「幾何学基礎論」(ちくま学芸文庫 2005)に詳しく述べられている。ヒルベルトは19世紀の数学の3つの問題を「否定的に解決」した。①平行線の公理、②円積問題、③5次代数方程式の代数的解法である。①非ユークリッド幾何学の存在は平行線公理の独立性からきており、もし平行線公理が他の公理から導けるなら、この論理はすべてのシステムで成り立つことである、平行線公理を満たさない非ユークリッド幾何学はそもそも存在しない。平行線公理の独立性が導かれる。非ユークリッド幾何学では直線はまっすぐではなく曲がっている幾何学である。それは曲面では直線に要求されるすべての公理を満たす直線としてのすべての機能を持つため、それを直線と呼ばざるを得ないからである。②円と同じ面積を持つ正方形を作図できないことは、代数的に考えると、y^2=πx^2という代数方程式を解くことであり、y=(√π)xという解が得られるが、有理数(整数)を係数とする代数方程式の解に円周率(しかも超越数の平方根)が入ることはできないというリンデマンの証明があるので、円積問題は比例を基にする作図法では解けないのである。③5次代数方程式の代数解はないということである。ヒルベルトの形式主義は1905年までを「前期形式主義」といい、モデルという非言語的かつ超越的なもの(伝統的近代数学)を基礎においている。ヒルベルトの形式主義は第1次世界大戦後1917年ごろから後期形式主義に入る。
20世紀現代数学の主流パラダイムとされるフランスのブルバキ構造主義はヒルベルト公理論(前期形式主義)を修正した。数学革命時代のヒルベルトの数学は実践と数学の基礎問題が分かちがたく結びついていた時代で、その時代からはるか離れた第2世界大戦後のブルバキの時代は数学から「哲学」(認識論)の除去であり、認識論的装置の要である「証明」を公理論(認識論)から取り除いたのであった。ブルバキは証明に認識論的意味合いを持たせなかった。ヒルベルトにとって証明は公理論の核であった。ヒルベルトはデーデキントたちとは異なり、実数を集合として定義しなかった。その代り実数の持つべき性質として有限個の公理系(①結合の公理、加法と乗法 ②計算の公理、交換可 ③大きさの順序の公理 ④連続性の公理)を設定し、この公理系から論理推論を有限回繰り返して結論を得ることを数学とみなした。ヒルベルトにとって実数は実存しているわけではなく、計算の実体も定義されとぃない。実数系システムは恣意的であってもいいが変更はできない。完成した証明ではなく建設段階のシステム開発に数学の醍醐味を見ているようである。ヒルベルトの公理論には無限はない。この考え方はクロネカーの有限算術化に非常に近い。クロネカーは無矛盾な等式によってのみ「新しい数」は導入されなければならないと考えた。例えば一辺の長さが1の正方形の対角線の長さを表す分数(有理数p/q)が存在したら矛盾が発生する。(p=√2qという矛盾 左辺は整数、右辺は無理数) クロネカーは「無矛盾性」以外に、拡大した体系の「計算可能性」を重視した。クロネカーの多項式→ヒルベルトの命題、代数計算→論理推論と置き換えると、ヒルベルトの公理論はクロネカーの有限算術化はそっくりである。ヒルベルトもクロネカーも全数学を代数学から見る視点は共通していた。クロネカ―とその師クンマーの数学を出発点としながら、ヒルベルトはカントール、デーデキントの数学観を採用したというべきである。ヒルベルトの数学基礎論は人間の計算能力を超える膨大な代数計算(今ではスーパーコンピューターが代行するが)との格闘という過程で生まれた。19世紀末からゲーデルの論文までの数学基礎論はその技術レベルは低かったが、世界の錚々たる数学者が参加した。上述の人々の他にも、ポアンカレ、ワイル、ノイマン、ウィーナーなどがかかわった。この動きは技術オンリーの日本の数学界では容易に理解できなかったようである。数学の問題の可解性は「ヒルベルトの青春の夢」であり、全生涯をかけた数学研究の目的であった。青春時代のヒルベルトの無二の親友であったミンコフスキー(1864-1909)との交流と「ヒルベルトの青春の夢」である可解性に関する「数学ノート」は、C・リード著 弥永健一訳 「ヒルベルト」(岩波現代文庫 2010年)に詳しく述べられている。次数が大きくなると代数方程式の解の不変式は急速に複雑になり, 順次不変式を求めていくのは大変困難になる. それでも, 19世紀に不変式の権威であったゴルダン(1837~1912)は, 5次以上の場合を含め,方程式の不変式(2次の場合は判別式と呼ばれる)は次数にかかわらず, つねに有限個の基本的な不変式の多項式として表すことができることを示した。イギリスのケーリー(1821-1895)は線形代数学の創始者と言われるが、ゴルダン問題の特殊なケースを解いたが、一般的なケースは解けなかった。ヒルベルトはこの未解決問題を、目弦的方法の優位性を印象付ける方法で解決した。ヒルベルトは1886年の数学ノートに、「ゴルダンの方法は複雑すぎてほとんどの場合に実行できない. 問題の核心はそういう計算方法でなく, 存在するという事実を示すことだけだ」と書いている.そして、1890年 他のすべての不変式を書き表すことができる 有限個の不変式系が「存在すること」を示した。これはヒルベルトの第14問題 と呼ばれる。不変式の存在とそれを構成する問題は別問題で、ヒルベルトは膨大な計算(数百ケース以上)に根を挙げて、不変式の存在定理だけに注目した。ゴルダン問題を「無限個あるかもしれない本質的特性が、実は有限個の基本特性の組み合わせで表現できる」という問題である。この戦略的発想転換により、ヒルベルトはデーデキント的な計算無視の一般有限性定理、すなわち冤罪のヒルベルト有限基底定理を考え出した。ヒルベルトは計算が命の代数においても、存在定理のような非構成的証明を使ってもよいとした。しかし有限完全不変式を計算するアルゴリズムを全く考えていないとゴルダンは評したが、ヒルベルトの師クリスチャン・クライン(1849-1925)はゴルダンの見解を無視した。
一般有限性定理の非構成的証明は、多くの拒否反応を生んだだが、ヒルベルトは無限列の最小値の原理を理解して、計算可能ではないが、最小値があることは確かである(帰納推論可能)と考えた。これをC・リード著 弥永健一訳 「ヒルベルト」では、「ゴルディオスの結び目」と表現されている。コロンブスの卵といってもいい。ヒルベルトの方法は代数学一般に利用され、代数学のほぼ全体がデーデキントーヒルベルト的に書き替えられた。20世紀以降代数学は計算的側面を無視した非構成的数学が一世を風靡した。クロネカーらが間違っていたわけではなく、具体的に計算できるという圧倒的な強みがあったが、当時の論文生産力に劣っていただけのことであった。今日コンピュータ代数学の登場によって、ゴルダンのアルゴリズムは実行可能となり、再び計算と論理についての価値感が逆転しつつある。計算と論理、有限と無限は数学の両輪の関係にある。ヒルベルトの可解性思想の成立には不変式研究が深く関与していた。可解性理論に関する、1890年無限版論文」、1893年の「有限版論文」、6以上の偶数は素数の和で表せるかという「ゴールドバッハ予想」問題など、ヒルベルトの数学基礎論思想の源流は可解性思想であり、不変式研究であった。ヒルベルトの可解性思想は、単純な人間中心主義というよりは、人間の現実的有限性を逆手に取った、可能性としての無限界性への信念なのである。1893年の「有限版論文」で不変式論は片が付いたと思ったヒルベルトは、1897年「数論報告」をドイツ数学者協会に報告した。これは後の「幾何学基礎論」と並んで彼の数学的業績として双璧をなす論文である。内容はデーデキントのイデアル論で書き換えた数論であった。数式と計算を避けて、概念と思考により数学を進める方法であり、リーマン(1826-1866)を受け継ぐものであることを宣言した。集合論と論理によって数学を進める方法はデーデキントとカントールの方法である。リーマンはデーデキントの友人であり一般相対性理論の為の数学、リーマン幾何学の創始者であった。ヒルベルトは無限版から有限版への不変式論の転換を振り返って、数学における存在の証明には三つの段階があるとした。①一般有限定理のように、存在性だけを証明すること ②解はどこに現れるか ③それを計算して見せることであった。第2段階と第3段階しかなかったこれまでの代数学に第1段階の解の存在性を示すことは斬新なアイデアであった。1897年カントールから集合論のパラドックスを聞かされたヒルベルトは、これは数学の問題ではないと不問に付すこともできたが、彼自身がパラドックスを発見した。これは「ヒルベルトのパラドックス」と呼ばれた。このパラドックスの解決策が前期形式主義の柱であった「存在=無矛盾性」である。ウィーナー(1857-1939)は「数学の証明は考察対象の内容に依存せず、その有限の証明の形式だけが問題である」と主張したが、ヒルベルトは、数学の本質は対象とする内容にあるのではなく形式的・構造的な関係にあることを看破した。「存在とはその概念を定義する公理が自己矛盾しないことである」という考えを1893年のノートに書き留めている。ヒルベルトの「存在=無矛盾性」というテーゼは、カントールの「無矛盾集合は存在する」からきているといわれるが、論理回路の創始者イギリスのブール(1815-1864)らも同じことを唱えていたので、矛盾なく機能するものは存在するという考えは19世紀後半の時代精神だったのかもしれない。
5) 数学基礎論論争(1904-1931)20世紀次第の数学の熱い論争「数学基礎論論争」は、登場人物の多彩さを超えて、世界史的な転換期を象徴する出来事になった。簡単に言うとヒルベルトの形式主義、ラッセルの論理主義、ブラウワーの直感主義、ボレーの経験主義という数学観の論争である。この論争をヒルベルトの立場を中心に描くと、非計算的数学という革命で勝利したはずのヒルベルトが、集合論のパラドックスという危機を迎え、20世紀の洗練された公理論、すなわち証明論で乗り越えたと見えたが、論争の場外からゲーデルの不完全性定理で打ちのめされた。そして第2次世界大戦で「数学基礎論」自体が無意味になってしまった。この論争には真の勝者はいない。1960年以降の数学基礎論研究によって、真の敗者もいなかったことが実証さつつある。ヒルベルトも70-80%は正しかった。ヒルベルトは1900年のパリ公演で、実数論の無矛盾性証明を彼の23の問題の第2番の問題とした。ユークリッド幾何学や非ユークリッド幾何学のモデル作りにより無矛盾性証明を行った。もし実数の世界が無矛盾であるなら、これら幾何学の公理系の無矛盾性は、実数論の無矛盾性に還元されたことになる。これがヒルベルトの無矛盾性の根拠であった。モデルの作成には集合論や無限算術が必要であった。ヒルベルト著 中村幸四郎訳 「幾何学基礎論」(ちくま学芸文庫 2005年)に5つの公理群が述べられている。Ⅰ1-8(結合の公理)、Ⅱ1-4(順序の公理)、Ⅲ1-5(合同の公理)、Ⅳ(平行の公理)、Ⅴ1-2(連続の公理)の最期の「連続性の公理」は、装いを変えた無限算術の「実数の連続性」つまりクロネカーの原理そのものであった。モデルは無限集合が本質的に必要となる。パラドックスが生じた無限集合論および無限的実数算術をクロネカーの批判からどう救い出すかという認識論的(哲学的)問題であった。ヒルベルトは哲学的アプローチを避け公理からの有限回の論理推論を重ねて表現する伝統的数学の証明を直接的に分析した。1904年の第3回国際数学者会議の講演で発表した方法は、自然数と超限数の公理系を使った後の形式系のひな形になる手法であった。この手法は数理論理学のイロハが分からないと理解不能であるので棚上げにしておく。欧州の数学史では二人の巨人が睥睨している構図がよく描かれる。ニュートンとライプニッツ、ガウスとコーシー、そしてヒルベルトとポアンカレ(1854-1912)である。ヒルベルトとポアンカレは何につけても好対照である。弟子を多く持ってシステマチックな総合科学の学閥の頂点にいたヒルベルト、弟子を全く持たず科学エッセイが得意なポアンカレ、形式主義者のヒルベルト、直感主義者のポアンカレという塩梅である。このフランスの数学者ポアンカレからフルベルト批判が出た。ポアンカレ著 吉田洋一訳 「科学と方法」(岩波文庫)において、ポアンカレは数学的論理学の最近の進歩を批判して次のように言っている。ラッセル、ヒルベルトらの数学的論理学派は、最近修正を加えながら発展してきたが、その法則は果たして確実性があるのか、また数学的帰納法が何ら直感に訴えることなく証明できるのかという点を考察した。ポアンカレーはいわゆる「直感派」であるので、ヒルベルトはいつも彼のライバルであった。ポアンカレーは数学論理派の主なリーダーたちの批判を展開している。クーテゥラの「存在することが矛盾のないことの証明である」という「矛盾の自由」を批判し、ヒルベルト批判は、一定の公準が矛盾を含むか否かを論じて、先天的綜合判断を想定しているとみなしている。ラッセル批判として、ブラリ・フォルティの二律背反、ツェルメロ・ケーニヒの二律背反、リシャルの二律背反、カントルの二律背反を引用して、ラッセルの部類語禁止の無限循環論で非確定的であるという。数学的帰納法について、ホワイトヘッドを循環論だと批判した。分析論理学の原理に基礎をおく証明は命題の系列からなる。言葉の置き換えは重複語法(トートロジ- 同義反復)に陥る。循環論法は非確定的定義を含組むと不毛の二律背反を生むのである。実無限は存在しないことを忘れて、カントル派は矛盾に陥った。実無限はラッセルの数学的論理学に欠くべからざるものである。ラッセルは内包的見解をとり、ヒルベルトは外延的見解を取るという違いはある。有限と無限の順序では、無限を有限の前に置くと無限は実在と見なさなければならない。 なおポアンカレは「数学的帰納法」の絶対的信奉者であった。ヒルベルトは数学が形式的に表現可能と考えたが、それは数学の可解性を信じ、その数学の分野の構造がよく見えてきた、数学は形式化できるという意味であった。理論の公理化である。ポアンカレのヒルベルト批判の最大のポイントは「数学的帰納法」であった。自然数の公理化には数学的帰納法が必要であるし、数学的帰納法を公理として追加して無矛盾性が証明できるとしたが、ポアンカレは循環論法となって証明できるわけがないと主張した。ポアンカレは自然数個の無限は認めるとしても、カントールのような制限のない無限集合は数学的でないとした。ポアンカレの批判は1920年代のヒルベルト計画のよき批判者であったが、ヒルベルト自身は第1次世界大戦末期の1917年まで数学基礎論から遠ざかって、もっぱら積分方程式論と量子力学物理学(ヒルベルト空間)の建設に関与していた。ヒルベルトの「解析学と物理学の時代」は、一般相対性理論の構築の時代と重なっている。重力場方程式の発見でアインシュタインと競争した。それは23の問題のうち第6番の「物理学の公理化」であった。
ラッセルはパラドックスを契機に、論理学による数学の基礎づけに邁進した。「クラス無し理論」などいくつかのパラドックス回避法を考えていたが、数学の基礎は必然的な歩みというより、試行錯誤的な経験がものをいう世界であった。1908年に最終的に「型理論」を発表した。その思考実験の結果が1913年の「プリンキピア」全3冊の刊行であった。そしてこの本がゲーデルの不完全性定理のターゲットになった。自然数の集合Nから始めて、べき集合を次々に作り、この範囲内だけで数学を構成するという。P(N)、PP(N)、PPP(N)に属する。a∈bという集合の帰属関係は、aが第n型でbが第n+1型の時しか認めない。これでパラドックは存続しえないと考え、言語に関するパラドックスも排除したとされた。ポアンカレとの論争を受けてラッセルは「循環論法の排除」をパラドックス対策の根本原理とした。この出来上がった論理は今日では「分岐的型理論」「可術的型理論」と呼ばれる。しかしラッセルの共同研究者のホワイトヘッドは、可述性が障害となり無限算術化理論にラッセルは新しい公理「還元公理」を導入した。この公理には非可述型が再導入されていた。ラッセルはデーデキントやフレーゲの「無限の公理」、「選択公理」を採用した。無限集合は論理だけからは作れないので公理として仮定したのである。選択公理はカントールの順序数ですべての集合を測ることができるという「ツェルメロの整列定理」の証明に必要だった。ラッセルはプリンシプルズで数学を論理のみに還元したかったのだが、実際は無限定理、還元公理、選択公理のような数学的公理や集合論的公理を導入せざるを得なかった。ゲーデルはこのことを「型理論は変装した集合論」だといった。つまり論理学ではなく制限付き集合論だったのである。1908年ツェルメロは集合論の公理系を発表した。現在の形式系数学では、ツェルメローフレンケル集合論や、ベルナイス-ゲーデル集合論が使われる。プリンキピアも現代の目から見ると形式系とは言い難いレベルである。数学基礎論におけるヒルベルト不在の期間に、ラッセルやツェルメロが行っていたのは、無限数学の安全装置に開発である。安全に使用できる範囲を検討する無限集合論の修正論である。パラドックスを契機にして数学における無限を根本的に問い直す動きである。反ヒルベルト計画の中心は、ブラウワー(1881-1966)でポアンカレ―の後継者を自任しこの流れを「直感主義」と呼び、ラッセルやヒルベルトらを「形式主義」と呼んだ。ブラウワーはカント哲学、ベルグソン哲学との関連性が指摘されるが、「排中律の否定」に最大の特徴がある。つまり「論理的原理の不確実性」と言った主観主義的思想(二一性)は、ゴルダンの有限回数の代数計算しか確実性はないとする主張に近い。数学のすべてがクロネカ―的な有限性に限定されることになり、非可述的集合を根底から作り上げることは不可能であり数学からは排除される。カントール集合論を「哲学的」と言って非難した現実主義者クロネカーにとって、神秘的なブラウワー直感主義は許容できなかったであろう。だがヒルベルトにとってブラウワーはクロネカーの亡霊に見えたのである。ブラウワーは点集合論的位相数学の研究で世界的に知られていて、カントール的・ヒルベルト的な位相幾何学で成果を上げた時点まではヒルベルトと太い紐帯で結ばれていたが、1918年より直感主義的集合論の論文を出版してヒルベルトに反旗を翻した。ブラウワーの数学の最大の欠点は定理の証明が複雑すぎて、展開が困難で生産性がなかったことである。ゴルダンやクロネカー、クンマーの数学にも共通する欠点であった。ヒルベルトのように最初は解の存在、次に計算方法と進めると簡単になるが、ブラウワーやゴルダンのアプローチではこれを一挙にやる必要がありより複雑なものにする。今日の計算可能性数学という分野では、定理がアルゴリズムで処理できるかを計算可能構造という数学のシステムとは別の性質として研究する。つまりヒルベルトの第2段を専門とする分野である。ヒルベルトの「一般有限性定理」は本質的に計算不能な問題も多くある。数学者は新手法が多産(多くの実りある結果を生む)であるときには、それを受け入れる。ブラウワーの数学の書き換えは非ユークリッド幾何学の多様な存在を示した点で評価はされるが、西洋合理主義の根本原理である排中律の否定や主観主義的二一性原理は数学を沈没させる以外のものを生まなかった。プリンピキアが出版された1914年にはヒルベルトのいるゲッチンゲン大学で新たな動きが始まった。ヒルベルトの学生ベーマン(1891-1970)がプリンピキアの研究を開始し、還元性公理の妥当性について1918年論文を書いた。ベーマンの決定問題とは、「任意に与えられた対象が、ある性質を満たすか否かを判定するアルゴリズムをつくること」である。
ヒルベルト自身が数学の基礎問題に復帰すると表明したのは1917年のことである。この年スイス数学会でヒルベルトは数学基礎論について語った。講演のタイトルは「公理的思惟」であった。無矛盾性証明の方法として、プリンキピアの論理体系への還元という論理主義アプローチを選択したのである。論理的無矛盾性の解決が最大問題ならば、論理主義的アプローチで十分だったはずだが、ヒルベルトのラッセル理解には問題があって、論理主義とハイデルベルグの証明分析手法の間を揺れ動いた。ヒルベルトの数学基礎論が無矛盾性でなく完全性を主眼としていたことが伺える。ヒルベルトの公理論が解決すべき数学的内容を持つ認識論的問題として、次の5つを挙げた。①原理的可解性、②結果の事後検査可能性、③っ数学証明の単純性判断基準、④数学と論理における内容と形式の関係、⑤有限回の操作による数学の問題の決定可能性とし、これらの問題がすべて解決するまでは論理学の公理化が完成したとは言えないといった。ここに「完全性」という定義さえ不明確であった。完全性を「イグノラビズム」(不可知論)に対する問題とする捉え方は古い。完全性に多義性があり、それが整理されるのは1929年ゲーデルの論文を待たなけばならない。ヒルベルトの優秀な学生で偉大な数学者と見なされていたワイル(1885-1955)は1921年「数学の新危機」という檄文を書いて、ヒルベルト陣営からブラウワー直感主義へ転向したことが、ヒルベルトにこの問題への強い関心を呼び起こし、1922年「数学への新基礎」という反論文を書かせた。前半でブラウワーの主張は古いクロネカーの亡霊であると言って攻撃し、後半数学の形式化前の生の内容についてクロネカーやブラウワーの数学に近い有限的・構成的な数学であるべきことを実質的に認めたうえで、彼の公理論を進化させて、プリンキピアの記述法は式と呼ばれる記号の組み合わせで有限かつ機械的に定義する規則であるとした。ゲーデルの論文において「形式的な観点からすると、証明は論理式の有限列に過ぎない」という見解に相当する。ヒルベルトは「証明図」と呼んだが、この考えは証明から内容を完全に抜き取ってしまった、形式系の誕生である。この数学を公理的集合論やプリンピキアと同一視した「ヒルベルトのテーゼ」の成立であった。こうして無意味な記号列の羅列としての形式系数学と、それについての内容的思考としての数学という、数学の二重構造が確立された。ヒルベルトは形式系数学を超数学または証明論と呼んだ。無矛盾性証明を実行する際に使用される「有限の立場」は不明瞭に残された。この点についてゲーデルは第2不完全性定理で、「不確かなもので確かなものの確かさを証明する」と排斥されたのである。こうした形式系の数学がヒルベルト計画の中枢として確立したのは実はずっと後の1934-39年に出版されたヒルベルトとベルナイス(1888-1977)の「数学の基礎」刊行以後のこととされる。1931年のゲーデルの不完全性定理の後である。有限な立場がヒルベルト計画の中核に在って不安定さを増していた。式としては等式のみを持ち、すべての原始再帰的関数の定義と数学的帰納法を持つ理論で、それを形式系にしたものが、現在PRA(原始再帰的算術)と呼ばれるものである。「形式系の無矛盾性証明による数学の基礎づけ」というヒルベルト形式主義は「数学と何か」という哲学問題になる。不安定な非形式的問題を超数学に取り込んだことである。ヒルベルト計画の哲学的側面はもっぱらベルナイスが担当した。ヒルベルト計画の中心を担ったのは、ベルナイスとアッカーマン(1896-1962)である。アッカーマンは数理論理学者である。1924年アッカーマンは有限の立場としてPRA(原始再帰的算術)をイメージした論文を発表した。第1階算術と呼ばれる形式系、実数論の部分体系となる第2階算術の無矛盾性を証明した。(この論文の間違いを指摘したのはゲーデルの定理の後であった。) 1926年ヒルベルトは「無限について」という論文で、彼の23の問題の内第1番の「連続体仮説」の証明のあらすじを発表した。しかし難解すぎてだれも理解できず、その結果は後年間違っていることが分かった。1926年若き数学者ノイマン(1903-1957)がゲッチンゲンに到着し、公理論的量子力学の研究に参加した。そして彼もヒルベルト計画に参画した。直感主義者ブラウワーは1927年ベルリン大学で、翌年にはスイスで連続講演を行った。この時の聴衆に哲学者のヴィトゲンシュタインや、ゲーデルがいた。1928年ヒルベルトとブラウワーの関係が極度に悪化し、政治的な解決が図られた。しかし無条件降伏勧告に近いブラウワーの4条件をヒルベルトが呑むわけではなかった。
第1次世界大戦後ドイツ数学会は国際数学者会議から締め出されていたが、1928年イタリアのボローニアの会議からドイツ人数学者が招聘されることになった。これにボイコットを呼びかけるブラウワーの動きもあったが、ヒルベルトは「数学の基礎づけの問題」を講演した。ここでヒルベルト計画の目標である4つの問題をリストした。①第2階算術の無矛盾性、②さらに高階理論の無矛盾性、③第1階算術の完全性、④数理論理学の第1階述語論理の完全性定理であった。ヒルベルトはブラウワーへの攻撃を企てた。ゲッチンゲンをベースとする数学専門誌「アナレン」の編集会議からブラウワーを追放する企てである。新編集員にブラウワーの名前はなかった。これにショックを受けたブラウワーはこれ以降数学会から遠ざかってしまった。アナレン事件により、数学基礎論論争の時代は終わった。ボローニアの4問題のうち、最初に解かれたのは第4問題であった。ラッセルの数学基礎論の影響を受けた哲学者の群れ(ヴィトゲンシュタインら)はウイーン学団と呼ばれていたが、そのなかからウイーン大学のクルト・ゲーデルによって解決された。ゲーデルはヒルベルト―アッカーマンの未解決問題つまりボローニアの第4問題を博士論文に選び、1929年には解決した。ヒルベルトが生み出したε記号の消去法の反復操作を使ってその不可能性に気が付き、そこから第1不完全性定理を得たという。1930年ヒルベルトは68歳の定年を迎えた。ケーニヒブルグの名誉市民号受賞記念講演で、ノイマンは形式主義を代表し、ハイティンクは直観主義を代表した講演をこなった。この研究発表会に参加したゲーデルは「無矛盾性だけではその理論の正しさは保証できない。すべての正しい論理式が証明できる数学の形式的理論があるとは言えないからだ」と発言した。「内容的には正しいのにその体系では証明できない命題の例がある。このような命題の否定を公理として付け加える、数学的には偽であるのに、拡大された体系自体は無矛盾であることになる」という第1不完全性定理が初めて公言された。ヒルベルトは予定通り「自然認識と論理」と題した受賞講演を行った。第2不完全性定理に発見は、ゲーデルとは独立にノイマンも発見した。ノイマンは発見のプライオリティはゲーデルに譲った。ゲーデルの結果はベルナイスがヒルベルトに伝えた。ボローニアの第3問題「数学の可解性」も否定され、実数論の無矛盾性も第2不完全性定理によって否定された。1931年にゲーデルの論文は出版され、その内容は早くからノイマンらによって学者の間には伝わっていたので、この驚異的な結果はほとんど抵抗なく瞬く間に受容されたという。ヒルベルトは1934年のベルナイスとの著作「数学の基礎」のまえがきで、「なお有限の立場の拡張が必要なだけ」と言い張った。しかしそれ以降ゲーデルの定理に関する発言はなく、ナチスが政権を取ってユダヤ人を追放したためゲッチンゲン大学の数学研究は崩壊し、1943年ヒルベルトはなくなった。
6) 不完全性定理のその後ゲーデルの不完全性定理によって終止符を打ったのは、ヒルベルト計画すなわち数学の基礎づけについての認識論的問題への挑戦である。数学としての数学基礎論はむしろゲーデルの定理をパラダイムとしてゲーデル以降に始まったのである。ヒルベルト計画とゲーデルの定理が後世に与えた影響、歴史的意義を考察して最後の章とする。ゲーデルは1933年アメリカ数学会での講演「現在の数学基礎論の状況」で、有限の立場による無矛盾性の可能性を、第2不完全性定理から否定した。超数学を形式系の中で実行するというゲーデルのプランは斬新であったが、ブラウワーの直感主義数学を使う超数学はそのままでは形式化できなかった。ノイマンやエルブランはその経験から有限の立場から無矛盾性の不可能性を実感したであろうが、まだ若いゲーゲルには彼らの無矛盾性は不可能という結論には俄かに同意できなかった。1933年の講演で、厳密な意味での有限の立場による無矛盾性の可能性を否定した後、直感主義に置き換えた場合の無矛盾性証明の可能性を検討した。直感主義的に思考することが、数学の安全性保証という問題にはほとんど意味がないことに気が付いた。こうしてゲーデルは直感主義をも捨て去った。ゲーデルは1938年ウィーン学団での不完全性定理の講義で、ヒルベルトの無矛盾性証明の目的は、A:数学の全体を、極小さい部分に縮小すること、B:数学理論を確固たる基礎に還元することにあったとしたうえで、Aは第2不完全性定理で否定されたが、Bの可能性は損なわれたわけではないとした。Bの高階関数による無矛盾性の証明は20年後ゲーデルによってなされたのである。ゲーデルは講演でBに希望を託したのであるが、多くの数学者が「構成の理論」として研究されたが、現在に至るまで万人が納得するような還元先は見つかっていない。ゲンツェンやゲーデルの無矛盾性証明は、第2次世界大戦後、主にドイツ、アメリカ、日本を中心に発達を遂げ、1960-70年代にかけ重要な成果が得られた。ヒルベルト計画が残した形式性の概念は、情報科学に与えた直接・間接の影響は量り知れない。ヒルベルト計画前の公理的集合論は決して明確な体系とは言えなかったが、計画後ンは数学者の中で解釈の差はなくなっていった。「通常の数学」の議論のほとんどが、公理的集合論に還元されることも経験的に確かめられた。ゲーデルが言う「確固たる基礎」に集合論を選ぶという選択は、哲学に興味を持たない数学者にとって抵抗感はない。共通言語としての集合論に、認識論的な安全性などは求めていないし、集合論が数学の本質であるとも考えていない。集合論は数学を記述しやすいツールである。このことは第2次世界大戦後に公理的集合論を数学の基礎の実質標準とすることに貢献したフランスの数学者集団ブルバキの見解がそれである。ブルバキは「未来においてそれが破たんしても、数学はまた新しい基礎を見つけるだろう」という。ゲーデルはヒルベルト計画の失敗は、本来超越的な信念でしかない無限の世界を、正反対の有限的・懐疑的な方法によって正当化しようとしたところにあると考えた。数学の不可侵性を実証しようとするヒルベルトの夢想は終焉したが、ゲーデルの定理は手法的にはヒルベルトの延長線にあり、形式系としての公理的集合論はヒルベルト計画の一部であった。数学が形式化され、数学の対象となったのちには、数学の基礎は数学として研究できるのだ。ゲーデルのBの研究も数学なのである。我国で「数学基礎論」と言われる学問は、海外では「数理論理学」と呼ばれ、数学の基礎というよりは、論理の構造、数学の論理構造などを研究する数学の一分野である。不完全性定理の兄弟ともいわれるチューリングの決定不能性定理を通して、ゲーデルの定理は人工知能などの情報科学にも大きな影響を与えた。現在では数理論理学は、証明論、再帰性関数論(計算可能性)、構成的数学、モデル理論、公理的数号論など多くの分野に別れて高度な発展を遂げた。また計算機科学への応用も行われた。ヒルベルト計画の推進者・反対者の勝敗はともかく、数学的成果の生産性の問題で直感主義は問題とならなかったのである。1967年ビショップ(1928-1983)は排中律、非可述的集合論、ブラウワーの原理のいずれも使わないで解析学の非常に大きな部分を再構成した。これをほかの分野にも広げていった。これをビショップの構成的数学という。20世紀初頭までの数学では排中律、非可述的集合論はめったに使わないで済んだ。だから無限算術化を行おうとするとつまずくのである。ブルバキによると排中律、非可述的集合論が必要な部分の多くは、集合論という数学記述言語に依存する部分で発生するが比較的少ないという。逆にいうと排中律、非可述的集合論が必要なのは、主として無限算術化における概念、例えば実数の基本的性質を証明する時なのである。そこでビショップは必要な時は実数をご都合主義的に定義してしまえばいいとまでいう。無理数や超越数など実用例ではビショップの「定義強化路線」でやって矛盾はないのである。こうした数学を「逆数学」とよび、数学のかなりの部分が厳密な意味での有限の立場と同等の体系で実行可能なのである。逆数学はヒルベルト計画の部分的達成ともいえる。論理と数学は、人間尾知的活動の内で、最も形式化を行いやすい分野である。形式化の恣意性や不確実性をまぬがれることはできない。また工学や応用科学などの分野では、形式化の不完全性こそが独創の源になっている。数式を扱う天才物理学者ファインマンも前提条件の吟味よりもまず適用してみよという。今不完全性定理を真剣に受け止めようとする数学者は極めて少ない。一般の数学者の多数派は数学の不完全性に悩まされることはないことが普遍的な事実である。