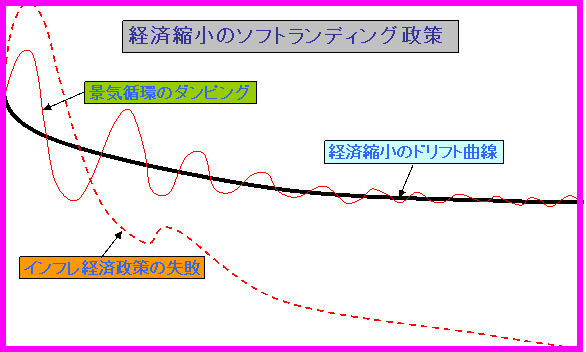
2013年にフランスで公刊された、フランスの経済学者トマ・ピケティの著書「21世紀の資本」がいま日本で大流行の兆しである。誰もが現在の社会や資本主義のあり方に疑問を持っているが、その謎解きをした経済学の本であるからだ。この書はまだ私は読んでいないが、内容についてはいくつかの紹介があるので、その一つを取り上げると、「議論の出発点となるのは、資本収益率(r)と経済成長率(g)の関係式である。rとは、利潤、配当金、利息、貸出料などのように、資本から入ってくる収入のことである。そして、gは、給与所得などによって求められる。過去200年以上のデータを分析すると、資本収益率(r)は平均で年に5%程度であるが、経済成長率(g)は1%から2%の範囲で収まっていることが明らかになった。このことから、経済的不平等が増してゆく基本的な力は、r>gという不等式にまとめることができる。すなわち、資産によって得られる富の方が、労働によって得られる富よりも速く蓄積されやすいため、資産金額で見たときに上位10%、1%といった位置にいる人のほうがより裕福になりやすく、結果として格差は拡大しやすい。また、この式から、次のように相続についても分析できる。すなわち、蓄積された資産は、子に相続され、労働者には分配されない。たとえば、19世紀後半から20世紀初頭にかけてのベル・エポックの時代は、華やかな時代といわれているが、この時代は資産の9割が相続によるものだった。また、格差は非常に大きく、フランスでは上位1%が6割の資産を所有していた。一方で、1930年から1975年のあいだは、いくつかのかなり特殊な環境によって、格差拡大へと向かう流れが引き戻された。特殊な環境とは、つまり2度の世界大戦や世界恐慌のことである。そして、こうした出来事によって、特に上流階級が持っていた富が、失われたのである。また、戦費を調達するために、相続税や累進の所得税が導入され、富裕層への課税が強化された。さらに、第二次世界大戦後に起こった高度成長の時代も、高い経済成長率(g)によって、相続などによる財産の重要性を減らすことになった。しかし、1970年代後半からは、富裕層や大企業に対する減税などの政策によって、格差が再び拡大に向かうようになった。そしてデータから、現代の欧米は第二のベル・エポックに突入し、中産階級は消滅へと向かっていると判断できる。つまり、今日の世界は、経済の大部分を相続による富が握っている世襲制資本主義に回帰しており、これらの力は増大して、寡頭制を生みだす。また、今後は経済成長率が低い世界が予測されるので、資本収益率(r)は引き続き経済成長率(g)を上回る。そのため、何も対策を打たなければ、富の不均衡は維持されることになる。科学技術が急速に発達することによって、経済成長率が20世紀のレベルに戻るという考えは受け入れがたい。我々は「技術の気まぐれ」に身をゆだねるべきではない。不均衡を和らげるには、最高税率年2%の累進的な財産税を導入し、最高80%の累進所得税と組み合わせればよい。その際、富裕層が資産をタックス・ヘイヴンのような場所に移動することを防ぐため、この税に関しての国際的な協定を結ぶ必要がある。しかし、このようなグローバルな課税は、夢想的なアイディアであり、実現は難しい。」というものである。この解説は社会政策的な表現であるが、その裏付けとなる経済学側の説明がほしいところである。それはこの書を読まなければ分からない。そういう意味で本書の水野和夫著 「資本主義の終焉と歴史の危機」は現在の状況を、金融資本側からまさに「目からうろこ」のような説明をしてくれる。久しぶりに知的興奮を覚えた書である。
本書は「資本主義の終焉(死)」という題がついていることからして、ユニークでショッキングである。入口で度肝を抜かれる。地球上にはどこを探してもフロンティア(外部)が残されていない。フロンティアとは資源(人もふくめて)をほとんどタダ同然に奪うことができるところで、非対称的世界のことである。資本主義(市場)は中心(内部)と周辺(外部)から構成され、周辺つまりフロンティアを拡大することによって、中心が利潤率を高め、資本の自己増殖を推進してゆくシステムです。アフリカのグローバリーゼーションが叫ばれ、地理的な市場拡大は最終局面に入っていると思われます。金融・資本市場を見ても、各国の証券取引所は株式の高速取引を進め、100万分の1秒から1億分の1秒で「電子・金融空間」で投資しなければ利潤を上げることができない仕組みになりました。日本を筆頭にアメリカやユーロ圏でも政策金利はおおむねゼロ金利、10年国債利回りも超低金利となり、資本の自己増殖は並の投資では不可能となっています。つまり、「地理的・物的空間」(実物投資空間)からも、「電子・金融空間」からも利潤を上げることはできません。資本主義を事項増殖を宿命とするプロセスであるとするならば、そのプロセスである資本主義は終わりに近づいたと言えます。さらに中間層が貧困化されると、中間層は資本主義を支持しなくなり国家は崩壊します。一握りの寡占家族が国家を乗っ取っているようでは、資本主義を維持しようとするインセンティブは働きません。日本の10年国債利回りが1997年に2%を下回ってから、北海道拓殖銀行や山一証券が破綻し、そして20年近く経ったいまでも2%どころか2015年では1%を切っています。なぜ超低金利がいつまでも続くのか、その理由を著者は「長い16世紀」のイタリア・ジェノヴァの「利子率革命」に求めました。長い16世紀は中世封建制の終焉と近代資本主義の幕あけ期せありました。著者は、では今の超低金利は近代資本主義の終焉のサインではないかという大胆な問題提起を著者は行います。著者は利子率の推移に着目して世界の経済史を見つめると、資本主義の始まりはローマ教会が利子率の上限を33%と許容した1215年あたりではないかと推測します。不確実なものに貸し付けるをするときは利子をつけてもいいという「リスク性資本」が誕生しました。それから長い時間が経過し資本が蓄積され資本主義は発展してきました。マックスウエーバーは資本の蓄積をプロテスタントの禁欲主義に求めましたが、資本の再投資によって新たな資本が生み出されることは言及していません。ですから禁欲と強欲は紙一重なのです。資本が利潤を上げられなくなった、すなわち利子率がゼロに近づいた時、資本は死にます。市場内部が成熟し飽和になれば新たな需要はなくなり、投資先を失った貸付利子率は低迷し、フロンティア(外部)を求めて資本は国外に出ます。そこから帝国主義・植民地主義が生まれました。世界に低開発国がある限り資本は利潤率の高い市場で稼ぐことができますが、その外部もなくなった時本当に資本は行き場を失います。この「歴史の危機」に直面して、なんらかの資本主義からのソフト・ランディングを求めるか、強欲資本主義をさらに強化して破壊ビジネスを繰り返しバブルと崩壊によって破綻するというハード・ランディングとなるか選択肢は2つしかありません。ソフトランディングとは人口減少社会の定常化社会と同じ考えです。松谷明彦・藤正 巌著 「人口減少社会の設計」(中公新書 2002年6月)が参考になります。今こそ日本は新しい社会、定常化社会への準備を始めなければならないというのが著者の結論ですが、その道の姿は見えないと嘆いています。私にとって本書が腑に落ちるように見えるのは、著者が実物経済学者であればデフレ論で終始していたであろうが、著者は証券会社のエコノミストであったことによって、日本経済を金融面から見ることで現状の明快な解釈ができていることに感銘を覚えたからです。著者のプロフィールを紹介する。1953年生まれで、現在は日本大学国際関係教授である。埼玉大学経済科学を卒業後、三菱UFJモルガン・スタンレー証券チーフアナリストを経て、内閣府大臣官房審議官、内閣官房内閣審議官を歴任した。本書の特徴は、金融から見た経済(当たり前のこと)という意味で、実経済(モノを中心とする)や労働にはあまり言及しない。その方が経済がよく見えることもある。利子がゼロになれば誰も見返りがないので投資しないということです。すなわち成長なき経済ということです。それを資本主義の終焉と著者は呼んでいる。松谷明彦・藤正 巌著 「人口減少社会の設計」が説く成長なき社会へのソフトランディングとは、下の図の模式図のようである。アベノミクスがいうような、無理なインフレ政策をとると急速に失速するのである。
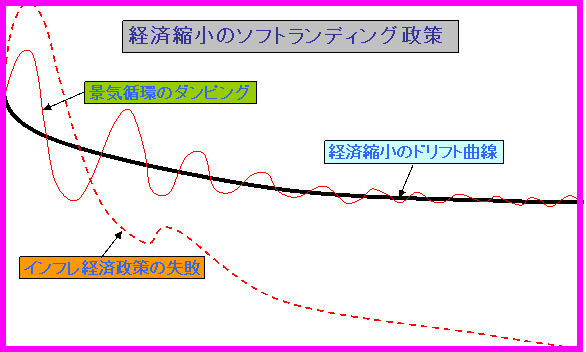
近代とは経済的にみれば、成長と同意語です。資本主義は成長を効率的に行うシステムですが、その環境や基盤を近代国家が整えてきました。資本主義の終焉ということは、もはや成長がない、投資先がないということです。確かに新興国と言われる国々はこの後20,30年は成長を続けるでしょう。労働力を非常に安く買いたたくことで利潤を上げる企業もいるでしょう。この成長が止まるという歴史的プロセスは、近代資本主義システム(経済システム)を根本的に転換してゆくことになるでしょう。同じような転換期が15世紀半ばから16世紀半ばの「長い16世紀」と言われる時期に、中世封建システムから近代資本主義システムに転換した。500年後の今日に近代資本主義システムの転換期が来たこととアナロジー的に一致するというのが著者の視点です。ねずみ講のように右上がりの成長路線にしがみついていると、国の基盤を危うくさせることになると本書は警鐘を鳴らしています。先進国の国債利回りの利子率の低下が顕著なのは、日本です。2014年1月段階で10年国際の利回りは0.62%です。短期金利の世界では事実上ゼロ金利が実現しています。17世紀初めイタリアのジェノヴァで利子率が1.12%でした。金利とは資本の利潤率のことですから、異様な状態(イギリス・アメリカ・ドイツで利回りは1-2%という)が先進国で長い間続いていることになる。これを「利子率革命」と著者は呼んでいます。利子率=利潤率が2%を切ると、資本側が得るものはほぼゼロです。「長い16世紀」のジェノヴァがそうでした。今を「21世紀の利子率革命」と呼びましょう。利潤を得られる投資機会がなくなったことです。「使用総資本利益率ROA」は結局国債利回りに連動します。この利子率低下がいつごろ始まったかというと、日本とイギリスで1974年頃から、アメリカで1981年ごろからといえます。利子率の低落傾向は40年以上続いていることになります。これを「市場の飽和」とか、「フロンティアの消失」という言葉で表現されます。日本では「交易条件=輸出物価指数/輸入物価指数」は、1975年までは1を超えていましたが、2000年までは1前後であった交易条件が2000年以降下降し2010年には0.6となっています。例えて言うなら輸出の花形である自動車1台と輸入必需品である石油1単位がパラであったのに、最近では車1台では石油は半分しか買えないということです。つまり資源を安く買い、効率よく生産した製品を高い値段で売っていたら、高い利潤が得られていました。石油は第1次、第2次石油ショックで交易条件は悪化するばかりです。新興国の近代化が資源高騰の背景にあるので、交易条件の悪化がトレンドとなっています。交易条件が悪化するということは、モノ作りが割に合わない商売になったということです。ヴェトナム戦争後、軍事力を背景としたアメリカの市場拡大策は頓挫し、戦争も割に合わない馬鹿馬鹿しい行為になっています。ポール・ポースト著 山形浩生訳 「戦争の経済学」(バジリコ 2007年)は、「アメリカのGDPあたりの戦費%は第二次世界大戦時132%を最大として、朝鮮戦争31%(11%)、ベトナム戦争8%(10%)、湾岸戦争1%(-1%)、イラク戦争<1%(2%)であった。GDP成長率は第二次世界大戦時は69%、朝鮮戦争11%、ベトナム戦争10%、湾岸戦争-1%、イラク戦争2%であった。戦費を減らす効率的戦争よりも凄まじいGDPの拡大ができたのである。しかしベトナム戦争以降戦争はもうGDPを押し上げない」と言っています。そこでアメリカのとった策は、新たな実物経済空間を生み出すことではなく、別の「電子・金融空間」に利潤のチャンスを見つけ「金融帝国」を目指すことでした。アメリカの「電子・金融空間」はニクソンショックの後に始まり、1980年頃からテイクオフしたようです。アメリカの金融業の全産業利益に占めるシェアーは10%から1990年には20%を超えました。この金融業のシェアー拡大は、金融のグローバリゼーションとシンクロしています。高い資源を使用しない空間を作ることで利潤を拡大したのです。アメリカの金融帝国化は格差を拡大する政策を推し進めました。この時のイデオロギーとなったのが「新自由主義=市場原理主義」でした。レーガノミックスに始まって、資本配分を市場に任せると、当然労働分配率を下げ資本側の取り分を上げます。だから儲けるのは企業ばかりで、中間層は貧困層へ組み込まれていった。当時アメリカは双子の赤字に苦しんでいましたが、ソビエト政権が軍拡競争に敗れて崩壊すると市場が一気に拡大しました。そして1995年からルービン財務長官が強いドルに政策転換すると、財政赤字のままでも世界中からカネが流れ込むフローができ、世界中に再投資してゆくことで「アメリカ投資銀行株式会社」となり、金融帝国となったのです。商業銀行の投資銀行化が進みました。労働者の貯蓄を扱う商業銀行は、レバレッジを大きくかける投資銀行に変容したのです。「電子・金融空間」で集めた金を運用して、アメリカ金融帝国はITバブル、住宅バブルを起しました。ここで資本主義は構造変化をしました。先進国を核として周辺に途上国という外部を持つ空間は、それとはまったく別の金融空間を生み出したのです。
1995年以降、日本やアジアで余っているお金は、アメリカの金融市場で簡単に投資できるようになっていきました。1995年から2008年の8年間で世界の電子・金融空間には100兆ドルmのマネーが創出されました。実物経済をはるかに上回るお金が地球上を動き回っています。2008年のリーマンショックでバブルが破裂して、実経済は一気に収縮しました。リーマンショック後のアメリカは、積極財政と超低金利政策を繰り返した日本と同じ経済構造に直面しています。アメリカの長期金利が2%を下回ったプロセスも1990年台の日本の不況期と同じです。企業のリストラが加速し、賃金が低下し、国内の多くの製造企業は海外の途上国に移転しました。実物経済の利潤低下がもたらす低成長の尻拭いを電子・金融空間に求めても、結局バブルの生成と崩壊という破壊ビジネスになります。「長い16世紀」時代に、スペインの無益艦隊を破ったイギリスが海上交易を支配し、イギリス・オランダの金融資本家の時代を迎えました。中世封建システムは近代資本主義と中央集権国家へと一変しました。そして「長い21世紀」では電子・金融空間に利益の活路を資本家たちが利益の一人占めをしています。そこで犠牲となっているのが労働者です。まさに若者は奴隷労働を強いられています。21世紀のグローバリゼーションとは労働側への配分率を極度に下げ、中間層を没落させる成長に他なりません。グローバリゼーションとは中心が周辺を再編成することです。資本でいえば実物投資先を途上国に変え成長軌道に乗せました。その途上国が成長すると、内部での周辺化を狙っています。EUにおけるギリシャやキプロスがそれであり、アメリカではサブプライム層(貧困層)、日本では非正規社員の増大です。製造業ではなく資本が牛耳る資本主義は膨大な中間層からなる民主主義の基盤を崩しています。貨幣数量説に基づく量的緩和策は、貨幣量を増やすと取引量が増えるという仮定で動いていますが、アメリカ国内では開閉流通速度が落ち、実物の取引は増えないで金融市場の取引が増えて株価の上昇があっただけです。物価水準は全く変化はなかった。金融規模はマネーのストックが140兆ドルあり、実物経済の規模は2013年で74兆ドルでした。グローバリゼーション時代にはお金は国内に止まらないで世界中にめぐります。量的緩和政策の景気浮揚策は一国内の国民国家経済の時代にしか通用しないのです。国内に有望な投資先が見えない飽和時代では、必然的に国外の途上国に流れます。だから金融緩和政策では国内景気は回復しません。先進国が輸出主導で成長するという状況は現代では考えられないのです。オバマ大統領の輸出倍増計画は旧時代の補強策であって、絵に描いた餅に過ぎません。アメリカのシェール石油に希望があるでしょうか。2020年頃までにアメリカは世界最大の石油産出国になるとしても、アメリカ資本主義は数十年間の延命策にはなるでしょう。しかアメリカはWTI市場で石油も先物取引で金融証券化されています。OPECに対抗して石油価格を決める機構を作りましたが、石油がバブル化し崩壊することの危険性があります。最近(2015年度初頭)石油価格が低落傾向にありますが、これはおそらくOPEC絞め殺し政策であって、主導権争いが終わると、石油価格は高騰してゆくでしょう。バブルの後始末は金融危機を伴うので、公的資金が投入されそのツケは国民に回されます。ウィルリッヒ・ベックは「富者と銀行には国家社会主義で臨むが、中間層と貧者には新自由主義で切り捨てる」というダブルスタンダードになっていると言います。バブル崩壊による信用収縮には過剰な金融緩和と財政出動をおこない、無傷で残った金融機関のお金は再び投機マネーとなって次のバブルを狙っているのです。サマーズ財務長官は「こうして3年おきにバブルが繰り返される」といいます。
2) 新興国の近代化というパラドックス1974年以来、先進国では実物経済において固い利潤を得ることができるフロンティアはほとんど消滅しました。資本利潤率とほぼ一致する長期利子率(国債)の低下がその証拠になります。その利潤率の低下に対して資本主義の延命策としてアメリカが企んだのは「電子・金融空間」の創出でした。それは資本が国境を越えて「新興国市場」に投資し、新興国の近代化を促すことで新たな投資機会を生み出そうとするものです。BRICSは2000年代に入って急成長を遂げました。しかし現在、その経済成長率に陰りが見えています。中国は2013年にGDPは7.6%に、ブラジルは2.5%、インドは3・8%に下がりました。その理由は簡単に言えば経済発展が輸出主導型で、売り込み先の先進国の消費ブームはリーマンショック後冷え切ったままです。欧州危機も大きな足かせになっています。新興国の過剰な設備投資は先進国の消費がなければ持続性はありません。アメリカ、日本の量的緩和政策は無限の金融空間の拡張ですが、それをいつ辞めるかが実は恐ろしい問題です。アメリカは2014年暮れに量的緩和を引き締めると公言しましたが、日本はまだ続ける予定です。バブル崩壊が恐ろしいからです。「価格革命」とは異なる価格体系を持つ空間と空間が統合し均質化する過程で起こる現象だそうだ。21世紀の価格革命では、原油などの資源価格が高騰している。イギリスの消費者物価の推移をみると、「長い16世紀」に物価は一桁上昇し「長い21世紀」では、20世紀の第2次世界大戦後に消費者物価はさらに一桁上昇し、21世紀難るとさらに一桁上昇しました。特に値上がりが激しかったのは穀物、石油でした。これは単なるインフレではなく、政治経済システムを揺るがす「価格革命」です。中世の「長い16世紀」では物価水準は下がり「労働者の黄金時代」で、政治権力システムは絶対王政と資本が合体し、国家が利潤の独占に向かって活発に活動しました(重商主義)。「長い21世紀」では1995年の国際資本の完全自由化(金融ビックバン)が「価格革命」に相当します。さらに2008年以降先進国の量的緩和策が投機マネーを増加させました。原油価格高騰の推移をみると2000年までは30-40ドル/バレルであったが、その後2008年に一時的に140ドル/バレルを突破し、以降110ドル/バレルの高値が続いている。先進国がBRICS30億人市場を統合した結果、新興国の経済圏が先進国を飲み込んでしまいます。生活水準を高めるため新興国の人口が食糧や資源価格の高騰インフレを招来するからです。1945年から1974年までは世界的な経済成長の下で「福祉国家」が実現し、「労働者の黄金時代」でした。ところが1974年以降「価格革命」が起きます。それを名目GDPと雇用者報酬の弾性率(GDPが1% 増えると、賃金が1%上がるとすれば弾性率は1です)は20世紀を通して1.00であったが、1974年から弾性率が下降し始め2010年には0.00となりました。つまりGDPが増えても賃金は上がらないということです。労働分配率がゼロという資本天国となったのです。1074年以降企業の利益と雇用者報酬とが分離し、一時的には企業の利益が増えているのに雇用者報酬が減少する事態(弾性率がマイナス)となりました。日本の実質賃金の推移をみると、2010年を100とすると1997年の111.3を最高として、2013年には97まで低下しました。グローバリゼーションを進めた資本側(一番安いコストで生産できる国に移動する)の完勝です。自国民を養う必要は資本側にはないという論理です。「長い21世紀」においては、資源価格の高騰と賃金の低下が閉校して起きています。
中国の一人当たりGDPが日米に追いついた時点で、世界は均一になるだろうと予想できます。現在日米と中国のGDPには4倍に開きがあり、中国の成長率と日本の成長率の差が8%-1%=7%として、(1.07)^n=4を解くと、n=20年となります。その時点で新しい政治経済システムが立ち上がるだろうと考えられます。「21世紀の価格革命」とは、それまでの国家と資本の利害が一致していた資本主義が維持できなくなり、資本が国家を飲み込む、つまり資本に国家が従属する資本主義へ変容しているということです。これが現状です。過剰なマネーが新興国で実経済の過剰設備を生み出し、デフレ圧力をかける一方、供給力に限りがある資源価格の将来の需給逼迫を見込んで先物市場で押し上げているからです。1995年までは国境の中に住む国民と資本の利害は一致していたので、資本主義と民主主義は衝突することはなかった。しかし資本がグローバル化すると、「近代が反近代をつくる」というように、現在の資本は国民を消費者・投資家としか見ていません。資本は国家を支配し、市民としての権利をはく奪する行為(貧困化)に及んでいます。先進国12億人が達成した生活水準を、途上国の56億人があと20-30年で達成しようとすれば、これまで先進国が独占していた資源が逼迫することが予想されます。例えば生活水準を電力消費量で見ますと、一人当たりGNIと一人当たり電気消費量は指数関数(飽和曲線)の関係にあります。いま日本の一人当たり電力消費量は8000KWHであり、中国は3000KWHです。中国とインドの電力使用量を日本並みに増加するとすると、この2か国だけで現在の世界の電力消費量の2/3を上乗せしなければなりません。鉄の生産量も現在の3倍強が必要です。全世界の近代化は不可能なシナリオになります。先進国と途上国(南北問題)の格差は言うに及ばず、先進国内、途上国内の格差が進行中です。アメリカでは1%の富裕層の所得が国民総所得に占める割合が、1976年に最低の8.9%になりその後上昇に転じ2007年には23.5%になっています。バブル崩壊の度に雇用条件が劣化し、先進国の中間層が最大の被害者になっています。中間層の所得がごっそり富裕層へ持っていかれた格好です。新興国では経済成長と国内での格差が同時に進行することです。新興国では国内の階層の2極化のため、民主主義が機能する前提を欠いています。投機マネーは140兆円を超えていますが、新興国が経済成長のために必要な固定資本形成は経済規模の30%と言われていますので、新興国の経済規模は28兆ドルでその30%は9.3兆ドルに過ぎません。余剰のマネーの10分の1以下です。すると中国は「生産能力過剰時代」を迎えます。その時中国もデフレに陥り、ゼロ金利、ゼロ成長時代に入るでしょう。資本主義とは内在的に「過剰、飽和、過多」を有するシステムなのです。このような中国のバブル崩壊まで見据えると、中国が新たな世界経済の覇権国家になる可能性は低いし、元が世界基軸通貨になる可能性はもっと低いと言わざるを得ません。世界経済の覇権をとった国は、いずれも実物経済がうまく機能しなくなり、金融帝国に走ることになるでしょう。基軸通貨の国では最も低い金利になるということです。近代の延長線上で成長を続けている以上、新興国もいずれ現在の先進国と同じ課題に直面します。
3) 日本の未来をつくる脱成長モデル中国が次の覇権国にはなりえない理由は、覇権国とは近代の酒宴国家体制の中の概念で、近代がグローバルの中で終焉するとすれば、次の覇権国家はあり得ないからです。先進国の中でいち早く金利ゼロ時代に入った日本は資本主義の限界に直面しています。日本の交易条件が大きく改善したのは、戦後の中では1955-1972年までです。粗鋼生産量は1973年でピークを迎え、それが横ばいを続けているのは需要が飽和点に達しているからです。大量生産方式と大量消費社会は1970年半ばでピークになりました。日本の中小企業・非製造業に資本利潤率が9.3%でピークを迎えたのが1973年であったのと同時期です。そして日本の合計特殊出生率が人口を維持できる2.1を下回ったのは1974年のことです。日本は、それから40年経ってついに人口減少社会時代に入りました。実物経済の「地理的・物的空間」の縮小傾向が明らかになって、1980年代日本は「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と浮かれていましたが、1990年日本が先進国では真っ先に資産価値バブルを経験しました。近代資本主義の優等生だった日本が資本主義の限界に達するのも早かった。金融バブルの発生には、①貯蓄が豊かであること、②実経済の膨張が止まったという2つの条件が必要でした。人口の増加も止まりました。人口増加で成長路線を期待する自民党政府の愚かさは、まさににシーラカンスです。成長が止まった日本でだぶついたマネーが土地資産バブルを引き起したのですが、それに続いて金融王国アメリカでも、ITバブル、住宅バブルサブプライムローン問題と立て続けに起こりました。自由貿易や金融の自由化はよく言われる「ウイン・ウイン」の関係にあるわ家ではありません。その時点で経済効率の勝っている国のための保護貿易主義なのです。自由主義はもともと最弱なものを犠牲にして成り立っています。自由主義というイデオロギーは最強の者が最弱なものを搾取するための自由であり言い訳に過ぎません。バブルが崩壊すれば2年間ほどのGDPを奪うくらいの信用収縮が起きます。バブルの後には賃金の低下や失業が待っています。それに対処するという名目で国債の増発とゼロ金利政策が行われ、超低金利時代と国家債務の膨張という破滅の道を歩みます。資本の絶対優位を目指すグローバリズムは、「雇用なき経済成長」という成長と賃金の分離を可能としました。1990年後半以来の日本の労働政策は、派遣業法の改悪という資本の要求通りに労働市場の規制緩和を行いました。人件費を経費化する(比例費とみる)ことで、縮小した規模に応じて労働者をいつでも首にできます。資本の利益のために、労働分配率を限りなく下げてゆき、それで経済成長を図るという政策は、危機の能度を高め、時期を早めます。アベノミクスの第3の矢である成長路線は名目の物価上昇という数値さえ達成できず、賃金が下がったままで、円安効果で資源価格は上がっていますので実質賃金はマイナスに転じています。そしてアベノミクスの第1の矢である金融緩和によるデフレ脱却はできません。グローバル化で金融緩和で生まれたマネーは国内を素通りした国境を越えて投資されています。いくらマネーを増やしても物価上昇にはつながりません。貨幣が増加してもそれは金融市場・資本市場で吸収され、資産バブルの発生の危険性を倍増しています。ではアベノミクスの第2の矢である積極的な財政出動(公共事業)は無意味です。1992年の宮沢内閣以来歴代内閣が総需要対策で、これまで200兆円以上の真水(外生)需要を追加してきましたが、日本経済を持続的成長軌道に乗せることはできなかった。財政出動は「雇用なき経済成長」の元凶です。公共投資を増やす積極的財政政策は、過剰設備を維持するための投資を膨張させ、それが賃金を圧迫しています。2000年以降の製造業の名目GDPの内訳は、固定資本減耗と営業利益の増加となり、反対に雇用者報酬は減少しています。固定資本減耗の増加と雇用者報酬の減少額が同じです。これは分配率が移動したことです。労働者に渡すべき賃金をカットして、過剰設備の減価償却に向けたということです。量的緩和策は実物経済に反映されず、資産価格を上昇させてバブルをもたらすだけです。公共投資政策は過剰設備を維持するための固定資本減耗を膨張させています。日本株式会社の失敗で、先進国が製造業を復活させる事は不可能であることを明白にしました。アベノミクスの積極財政政策は過剰な資本ストックを一層過剰にするだけなのです。既存システムが機能不全(不況)に陥っているとき、既存システムを維持強化する政策が失敗することは明白です。デフレよりも雇用改善尾ない景気回復の方が致命的なダメージを社会に与えます。民主的な配分ができなければ中間層が無くなって民主主義は崩壊します。奴隷的な貧困者しかいなくなれば民主主義は不要で、専制君主主義に逆戻りする危険があります。今資本の奴隷となっている国家をも資本は見棄てるときが来ます。その結果国民経済は崩壊して、グローバルエリートと言われる特権階級のみが富を独占するでしょう。破滅を回避するため、資本主義の「強欲」と「過剰」にブレーキをかける必要があります。日本は1000兆円の国家債務と個人資産を相殺するような国になれば、国家と社会は崩壊します。軍事力で国民を抑えるだけの奴隷国家となります。
4) 西欧の終焉ギリシャの財政崩壊に端を発する欧州危機は、PIIGS(ポルトガル、アイルランド、イタリア、ギリシャ、スペイン)に波及し、国債金利を高騰させ、金融機関の破綻、若者の失業の増加など深刻な課題を抱えています。ドイツを中心とするユーロ加盟国が欧州市場の救済措置をと取りました。ユーロの中核であるドイツがギリシャを見捨てなかったのは経済問題よりは政治問題を優先したからです。ユーロは事実上ドイツを中心とする政治同盟なのです。この欧州危機が単なる経済危機ではなく、西洋文明の根幹にかかわる問題なのです。「海の国」であるイギリスと米国に対抗する、「陸の国」である欧州大陸国の抗争問題です。アメリカは電子・金融空間を創設し、金融のグローバリゼーション(規制緩和)を通じて、世界の金融市場でお金を吸収する金融帝国を作りました。ロンドン市場、ニューヨーク市場が金融センターとなっています。アメリカは国民国家から、資本が主人公となった帝国システムに変貌しました。市場を支配することがアメリカの政治そのものなのです。これに対して欧州大陸の国であるドイツとフランスは資本帝国の道は選ばないで、ヨーロッパ統合という「領土」帝国化に進みました。この構図は「長い16世紀」では、「海の国」イギリスにたいする「陸の国」スペインの戦争に相似します。今日では「海の国」アメリカの覇権体制が緩み、EU、中国、ロシアという「陸の国」の台頭という構図です。欧州では主権国家システムを超える形態の一つである「ユーロ帝国」(神聖ローマ帝国の再現)を選択しました。これを国際政治学者のへどりー・ブルは「新中世主義」と呼びました。これは別に世界政府に展開する様子はありません。共通の価値観を持つ主権国家の融合に過ぎないからです。主権国家システムは国民に富を分配する機能を持つから支持されてきた。かっての市民革命を経て資本主義と民主主義が一体化したからこそ、主権国家システムが維持されたといえます。巨大資本が利益を総取りするグローバル資本主義に対抗するためにユーロ圏が形成されました。しかしながらEUですら資本の論理に巻き込まれました。恐ろしいほど欧州でも社会格差が拡大しました。失業率は慢性的に高い。特に若者は行き場を失っています。リーマンショックが資本の終焉だとしても、欧州のユーロ圏が行き詰っていることは、欧州の死を意味することです。ユーロは資本の力や軍事力で主権国家をかき集めたのではなく、「理念(価値感)」によって国民主権国家を習合したものである。ドイツ・フランスが目指す領土空間とはすなわち欧州の政治的統合です。「経済連合」の意味合いが強かったECを、マーストリヒト条約により「政治的統合体」EUに変えたのです。1990年西ドイツが東ドイツと統合した際に、1対1のレートでマルクを統合しました。経済的損失は念頭に置きませんでした。現代の世界で起きている「帝国化」とは、主権国家の終着点なのです。ドイツ・フランスの「領土帝国」も、英米の「グローバル資本帝国」と同様に限界に近付いてきています。これ以上に帝国化を推し進めれば、社会の崩壊という深刻な事態も考えられます。資本主義には「過剰」の宿命を持っています。絶対的優位に立つための手段で自らの首を絞めることになります。そもそも資本主義が生まれたの、12、3世紀の「利子」が容認されたときです。教会は33%までの利子率を貨幣の正当な時間リスクとして容認しました。12世紀から長い16世紀までが資本主義の孵卵期と考えられます。その間「知の革命」からルネッサンスそして近代へ移行しました。市民革命から産業革命をへて資本主義は開花しました。そして今や資本主義は国民の福祉を投げ捨て、人間を離れて資本だけの論理で市民から乖離しました。ここで資本主義の限界が近づいたと言えるでしょう。
5) 資本主義はいかにして終わるのか狭い意味で金をかき集めることを「募集」という。資本主義はヨーロッパの本質的な理念である「募集」に最も適したシステムです。資本主義は時代によって、重商主義でったり、自由貿易主義、帝国主義、植民地主義であったりと変化しますが、21世紀のグローバリゼーションこそ、その最たるものと言わざるをえません。資本主義の本質は、富やマネーを「周辺」から「募集」し、「中心」に集中させることに変わりありません。新興国への投資拡大によって先進国と新興国の所得格差は縮小しつつあります。グローバル資本種gとは、国家の内側の社会の均質性を消滅させ、国家の内側に「中心/周辺」を生み出してゆくシステムだと言えます。そもそも資本主義とは少数の人間が利益を独占するシステムでした。そして地球の全人口の約15%の先進国の人が豊かな生活を享受しています。15%という数値は18870年から2000年まで少しも拡大しませんでした。この15%というのが上限なのかもしれません。これまでの資本主義は資源がタダ同然で手に入ることを前提として、「安く仕入れて、高く売る」という近代資本主義はもともと格差を前提としています。全世界が均質化したら非対称性がなくなり利益が出ない構造になります。差があるから利潤が出る仕組みです。そのため資本主義は国内でも無理やり「周辺」を作り出し、利潤を確保するのです。その典型がアメリカのサブプライム・ローンと言った貧困ビジネスであったり、日本の非正規雇用問題なのです。むき出しの強欲資本主義では少数の資本家が利益を独占しています。それを「勝ち組」という詭弁で、「負け組」を諦めさせます。アダムスミスは「道徳感情論」で一定のブレーキをかけ、マルクスは資本家の搾取を見抜きます。ケインズは市場以外の政府の総需要政策を説きました。1990年までの社会主義国の存在は、資本家や起業家に常に雇用者福祉を念頭に置かせました。しかしあらゆるレーキをはずしむき出しの資本論理を貫こうとしたフリードマンやハイエクらが新自由主義をとなえ、グローバル資本主義の旗振り役を果たしました。金融緩和を行い、インフレ期待を持たせたら経済は好転するというリフレ派が主流となっています。しかしサマーズ長官が2013年のIMF会議で、先進国が貯蓄過剰の下、需要不足の長期停滞に陥っていることを認めました。ではケインズ派のような積極財政政策で需要は喚起できるのでしょうか。ケインズ主義が成立するのは、一国経済のなかでマネーを制御できる時代のものです。21世紀ではケインズ流の「大きな政府」は失敗を宿命づけられています。我々は「長期停滞論」に憂えることも考え直す必要があります。資本主義の定義は「資本は自己増殖するプロセスである」とするなら、もともと「無限」の空間を想定しています。無限であると考えると「過剰」は存在せず、スピードや効率だけが課題となります。近代社会は経済的には資本主義社会であり、政治的には民衆主義社会である。近代は無限の物資を使うということがそもそも可能だとは思えません。青天井の空間、それが「電子・金融空間」であったのです。先進国は途上国に対して見えない壁を作り資源を収奪し、先進国内に見えない壁を作り、下層の人から上層の人へ富の移転を図ることです。ケインズ流財政出動も、公共事業に乗数効果が見込めない現在に在っては、将来の需要を過剰に先取りしている点では、次世代からの収奪です。1990年代末に世界的な流れになった時価会計は、株式などの資産価値は期待値に過ぎず、将来の価値を先取りしそれが膨張すると、将来の人々が享受する利益を先取りすることになります。地球上から「周辺」が消失し、未来からも収奪しているという事態の意味は深刻です。デフレと言った次元ではなく、資本主義の終焉、つまり近代の終わりが近づいています。すでに資本主義は永続型資本主義(株式会社型)からバブル清算型資本主義(金融支配型)へ変質しています。バブルを作っては壊れるという破壊ビジネスの繰り返しです。
中国はリーマンショック後。政府の主導で大型景気対策として4兆元の設備投資を行ったことによって、中国の生産過剰が顕著になった。世界の工場と言われる中国ですが、輸出先の欧米の消費は縮小しています。いずれこの過剰設備は回収不能となりバブルは放火しますが、中国がもしドルを手放すなら、ドルの終焉を招くことになるでしょう。新興国で起きるバブルは欧米で起きた資産型バブルではなく、日本型の過剰設備バブルです。国際資本の完全移動性が実現した21世紀では、先進国の量的緩和で生じた過剰マネーが、新興国の近代化を日米欧よりももっと早く進行することを可能にしました。中国バブルの崩壊が世界に与える影響は甚大です。財政破綻に追い込まれる国が出るでしょう。日本がその筆頭候補です。国家債務に苦しむ日本は、普通なら戦争になってもおかしくない状況にあります。過去は戦争とインフレで帳消しにしてきました。しかし簡単には戦争はできないことも確かです。資本と労働の対立が深まり、社会不安が暴動や革命を生むかもしれません。いまや資本が主で、国家は使用人に過ぎません。バブル崩壊や戦争と言ったハード・ランディングではなく、資本主義の暴走にブレーキをかけるソフト。ランディングの道はあるのでしょうか。上の図で模式的に示した「経済縮小によるソフト・ランディング」の道を「定常状態社会」(ポスト近代)と言います。資本にブレーキをかけながら、国家の破滅を防ぎ延命を図ることです。「定常状態」とはゼロ成長社会と同義です。つまり純投資がなく、減価償却の範囲内d家の投資しかない状態です。買い替えだけで基本的には経済の循環を作ることです。日本の人口は少子化対策をしても、間もなく9000万人で横ばいということが予想されます。国家債務は減らすことができなくとも、少なくとも基礎的財政収支(プライマリーバランス)を均衡させる必要があります。いま日本のGDP(500兆円)に対する債務残高(1000兆円)が2倍を越えるほどの赤字国家であるのみなぜ破たんしないのかというからくりは以下のようです。金融機関のマネーストックは年金が主ですが、毎年24兆円づつ増えていきます。さらに毎年の企業内資金剰余額は23兆円あります。この家計部門と企業部門を合わせた資金剰余は48兆円で、対GDPの10%と高水準にあります。これが国債の購入費(毎年40兆円の国債発行)に充てられることが可能になる根拠です。また累積債務の1000兆円は、民間の実物資産や個人金融資産が大きくそれを上回っているので信用不安にならないのです。ですから外国に国債を買ってもらう必要がないのですが、将来金融機関のマネーストック(預金・年金など)が減少したり、国債の無原則的な発行が毎年50兆円を超える場合には事態は一気に悪化します。現実には個人預金は間接的に国債を買っているのと同じ意味ですので、1000兆円の債務は、いわば日本株式会社の「会員権」への出資と考えられます。財政を均衡させるために増税は仕方ありません。問題は消費税に頼るのではなく、法人税や金融資産税を増税することです。持てる者からより多くの負担をしてもらうことです。政府がそこを逃げていたのでは逆累進性の強い税制となります。ゼロ成長ですら困難な時代ですので、ゼロ成長を維持するには、成長の誘惑を断ち国の借金を均衡させ、人口問題、エネルギー問題、格差問題などに対処しなければなりません。金融緩和と積極財政に頼っていては傷口を広げるばかりです。マイナス成長社会は貧困社会です。1990年代から金融資産を持たない世帯の比率(1990年で5%)が上昇しており2010年では31%になりました。グローバル資本主義は社会の基盤である民主主義も破壊しようとしています。民主主義の経済的意味とは、適切な労働分配率を維持することです。労働者全体が貧困化しては、政治的民主主義は無いのも同然です。国家が資本の使用人になっている状況では、国家の存在意義に疑問が生じます。近代資本主義と主権国家システムはいずれ別のシステムに転換するでしょうが、その姿は予想できません。当面必要なことは資本主義にブレーキをかけることです。