 丂丂丂丂
丂丂丂丂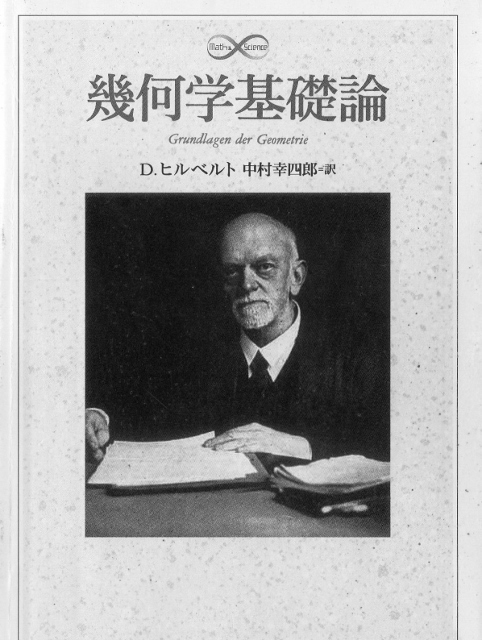
 丂丂丂丂
丂丂丂丂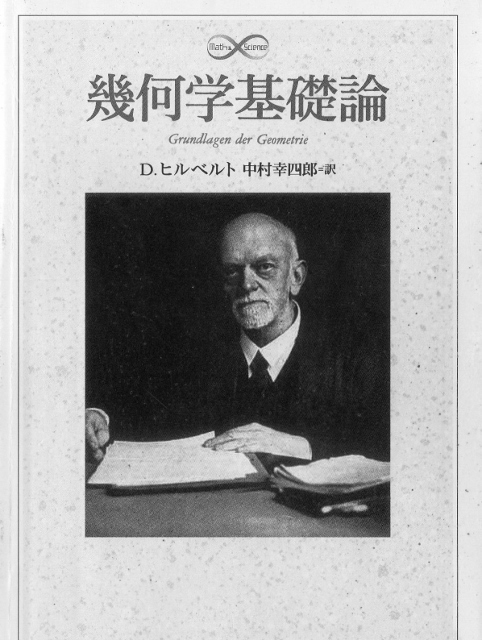
屄恖揑側偙偲偱嫲弅偱偁傞偑丄巹偼杮彂傪2010擭10寧偐傜撉傒巒傔丄戞1復乮58暸乯偱僊僽傾僢僾偟偨丅慡暥200暸傎偳偺悢妛榑暥乮杮彂偼堦斒恖岦偗偺孾栔彂偱偼側偄乯偱偁傞偑丄婔壗妛偲偄偆偙偲偱捈姶揑偵傢偐傞恾宍偲偄偆姶妎偱娒偔尒偨偺偑娫堘偄偩偭偨丅弶摍婔壗妛傪偳偆偟偰偙傫側偵夞傝偔偳偔揥奐偡傞偺偩傠偆偲偄偆媈栤偐傜巒傑傝丄搑拞偱杮彂偺堄恾偑尒偊側偔側偭偨偙偲偑僊僽傾僢僾偺尨場偱偁偭偨偲斀徣偟偰偄傞丅偦偙偱嵟嬤偵側偭偰巚偄弌偟偨傛偆偵丄C丒儕乕僪挊丂淺塱寬堦栿丂乽僸儖儀儖僩乕尰戙悢妛偺嫄曯乿乮娾攇尰戙暥屔乯傗丄彫暯朚旻挊丂乽婔壗傊偺桿偄乿乮娾攇尰戙暥屔乯偲尵偭偨丄堦斒孾栔彂傪撉傫偱僸儖儀儖僩偺乽婔壗妛婎慴榑乿偺廃傝偐傜峌傔傞偙偲偵偟偨丅杮彂慡暥傪偟偭偐傝撉傓偲丄傛偆傗偔杮彂偺堄恾偼暘偐傝杮彂偺恾宍偵娭偡傞揥奐偼僼僅儘乕偱偒傞傛偆偵側偭偨偑丄傗偼傝悢妛偼摼堄偱側偐偭偨偲偄偆晧偗惿偟傒偐傜偐丄懠偺悢妛暘栰偲偺娭楢傗悢妛巎忋偺堄媊偵偮偄偰偼傛偔傢偐傜側偄丅婔壗妛傪恾宍側偟偱昞尰偡傞偙偲偑尰戙悢妛偺傗傝曽偩偲暦偄偰丄傑偨傃偭偔傝偟偨丅傑偝偵拪徾悢妛偺擖傝岥偵棫偭偨姶偑偡傞丅曗彆慄堦偮偱妝偟傔傞乮嬯偟傔傞乯恾宍偺壢妛偱偼側偔側偭偰偄偨丅偦偺曈傪彫暯朚旻巵偼扱偄偰丄乽婔壗妛婎慴榑乿偺暯柺婔壗偺岞棟揑峔惉偼偁傑傝偵傕尩偟偔偐偮擄偟偄偺偱丄傕偆彮偟堈偟偔偰堦墳尩枾側暯柺婔壗偺岞棟揑峔惉傪帋傒偰丄1985擭娾攇彂揦傛傝乽婔壗偺偍傕偟傠偝乿偲偄偆杮傪弌斉偟偨丅乽婔壗偺偍傕偟傠偝乿偺岞棟揑峔惉偼丄婎慴揑側晹暘偺傒側傜偢墌榑偐傜斾椺傗柺愊偵偄偨傞傑偱暯柺婔壗慡斒偵媦傫偱偄傞丅岞棟偼棟桼傪弎傋側偄傑偱傕恀偲擣傔傞柦戣偱偁傞偲偡傞丅宍幃庡媊偲偼斀懳偺棫応偱偁傞丅C丒儕乕僪挊丂淺塱寬堦栿丂乽僸儖儀儖僩乕尰戙悢妛偺嫄曯乿偵傛傞偲丄1898擭僴儖儗偱峴傢傟偨H丒償傿乕僫乕偺婔壗妛偺婎慴偲峔憿偲偄偆島媊傪暦偄偰丄乽揰丄捈慄丄暯柺偲偄偆尵梩偺戙傢傝偵丄僥乕僽儖丄堉巕丄偦偟偰價乕儖丒僕儑僢僉偲尵偄姺偊傞偙偲偑偱偒側偔偰偼偹乿偲偄偆堄枴偁傝偘側尵梩傪揻偄偨偲偄偆丅偦偟偰1898擭乣1899擭偵偐偗偰僸儖儀儖僩偼乽婔壗妛偺婎慴乿偲戣偡傞島媊傪峴偭偨丅僸儖儀儖僩偑婔壗妛傊偺傾僾儘乕僠傪巒傔傞偲偒丄婔壗妛偼堦尒偟偰帺柧側柦戣偲丄榑棟妛揑側曽朄偱摼傜傟偨柦戣偑崿嵼偟偰偄傞桳條偱偁偭偨丅婭尦慜3悽婭偵儐乕僋儕僢僪偑傎傏1僟乕僗偺岞棟偲掕媊偺傒傪梡偄偰500埲忋偵忋傞悢偺婔壗妛揑柦戣傑偨偼掕棟傪摫偄偨丅帺柧偲偼尵偊側偄岞棟傕偁傞偑儐乕僋儕僢僪偺乽尨榑乿偲偄偆懱宯偼2000擭埲忋恖乆偐傜媈傢傟傞偙偲傕側偔懚嵼偟偨偲偄偆偙偲偑嬃堎揑偱偁傞丅偁偄傑偄側揰偲偄偆偺偼丄偁傞摿掕偺嶌恾偵偍偄偰2偮偺捈慄偑岎傢傞偲偄偆偨偖偄偺帇妎揑擣幆偵婎偯偔壖掕偱偁傞丅暯峴慄偺岞棟傕帺柧偐偳偆偐妋偐傔傛偆偑側偄偑丄僸儖儀儖僩偼攚棟朄偵傛偭偰柍柕弬惈偲偄偆奣擮傪摫擖偟偨丅僈僂僗偼1800擭偛傠儐乕僋儕僢僪偺暯峴慄偺岞棟偺斲掕偼昁偢偟傕柕弬傪摫偔傕偺偱偼側偄偲偐傫偑偊丄儐乕僋儕僢僪婔壗妛埲奜偺婔壗妛傕壜擻偱偁傞偲姶偠偰偄偨丅1830擭戙偵捈慄奜偺1揰傪捠偭偰暯峴慄偼柍悢偵堷偔偙偲偑偱偒傞偲偄偆丄儘僔傾偺儘僶僠僃僼僗僉乕偲僴儞僈儕傾偺J丒儃儎僀偺2恖偺悢妛幰偑尰傟偨丅偦偟偰3捈慄偑側偡3妏宍偺撪妏偺榓偼2捈妏偵偼側傜側偐偭偨偵傕偐偐傢傜偢怴偟偄婔壗妛偼榑棟揑側柕弬傪娷傑側偐偭偨丅旕儐乕僋儕僢僪婔壗妛偺巒傑傝偱偁傞丅媴懱婔壗妛偼偦偺抂揑側椺偱偁傞丅1870擭僼儕僢僋僗丒僋儔僀儞偼儐乕僋儕僢僪婔壗妛偲旕儐乕僋儕僢僪婔壗妛偺娭學偲懳徾偼摨堦偱偁傞偲帵偟偨丅崅搙偵拪徾揑側榑棟懱宯偼暲棫偡傞偺偱偁傞丅儌儕僢僣丒僷僢僔儏偼婔壗妛傪弮悎側榑棟揑峔暥偺憖嶌偺栤戣偵婣拝偝偣偨丅儁傾僲偼婰崋榑棟妛偺婰朄偵傛傞東栿傪帋傒偨丅姰慡偵拪徾揑側僔儞儃儖壔偵岦偐偆婔壗妛偺挭棳偑婲偭偨丅儐乕僋儕僢僪偵傛傞揰丄慄丄柺偺掕媊偼悢妛揑偵偼堄枴偺側偄偙偲偱丄偦傟傜偲慖偽傟偨岞棟偲偺娭學偵傛偭偰婯掕偝傟傞偲偄偆丅僸儖儀儖僩偼島媊偺拞偱丄娙寜偱姰慡偱屳偄偵撈棫偟偨岞棟宯傪抸偙偆偲偟丄拪徾揑帇揰偲嬶徾揑側媽棃偺岅朄偺撈憂揑側寢崌偼惉岟偟偨丅偦偟偰岞棟宯偑師偺榑棟妛揑梫惪傪廩偨偡傕偺偱側偗傟偽側傜側偄偲偟丄姰慡惈丄撈棫惈丄柍柕弬惈傪偁偘偨丅僸儖儀儖僩偵偍偄偰偼丄嵟屻偺柍柕弬惈偺徹柧偺傒偑丄棟榑偺捈姶揑恀幚惈偵偲偭偰戙傝摼傞傕偺偱偁偭偨丅僸儖傋儖僩偺乽婔壗妛婎慴榑乿偼19悽婭偵偍偗傞僈僂僗埲棃偺旕儐乕僋儕僢僪婔壗妛偺宍惉偲敪揥傪庴偗偰丄幩塭婔壗妛乮摟帇恾朄偵傒傞暯峴慄偼柍尷偵1揰偱岎傢傞乯偺揥奐傕幩掱偵擺傔偰丄儐乕僋儕僢僪婔壗妛偺埵抲偯偗傪棟榑揑偵柧妋偵偟偨傕偺偲峫偊傜傟偰偄傞丅偙偆偟偰婔壗妛棟榑偺柍柕弬惈偼嶼弍乮僸儖儀儖僩偼慄暘嶼偲偄偆乯偺柍柕弬惈偵婣拝偝傟偨丅僸儖儀儖僩偺悢妛婎慴榑偼屆戙僊儕僔儍偱抋惗偟偨岞棟庡媊傪庴偗宲偄偱傞丅偙偺岞棟庡媊偑尰戙暔棟妛偵揔梡偱偒傞偐偳偆偐偵僸儖儀儖僩偼怱寣傪拲偄偩偲偄傢傟傞偑丄敪揥宆宱尡庡媊偺暔棟妛偵姰慡柍寚偺岞棟榑傪帩偪崬傓偙偲偺惀旕偼崱側偍寢榑偑偱偰偄側偄丅杮彂偼偦偆尵偆堄枴偱丄岞棟榑揑傾僾儘乕僠偑嵟傕岠傪憈偟偨帠椺偱偁傞丅嬤戙悢妛偺夋婜傪側偡婰擮旇揑挊彂偲偐丄恖椶巎忋嵟崅寙嶌偺傂偲偮偲偐偲偄偆巀帿偑杮彂偵梌偊傜傟偰偄傞丅僷僗僇儖偑1657擭偵挊偟偨乽婔壗妛揑惛恄乿偵旵揋偡傞愨巀偱偁傞丅
杮彂乽婔壗妛婎慴榑乿偼1930擭敪姧偺戞7斉傪掙杮偲偟偰偄傞丅杮榑偲晅榐10曆傛傝峔惉偝傟偰偄傞偑丄拞懞岾巐榊巵偼晅榐偺東栿偼廳梫側乽悢偺奣擮偵偮偄偰乿丄乽岞棟榑揑巚堃乿偩偗偵偟偨偲夝愢偵彂偄偰偄傞丅偙偺婔壗妛婎慴榑偺杮榑偼1898擭乕1899擭偺僎僢僠儞僎儞戝妛偵偍偗傞乽儐乕僋儕僢僪婔壗妛尨榑乿偲偄偆島媊偵婎偯偄偰偄傞丅1899擭偵敪昞偝傟偨偑丄偦偺屻晅榐傪偮偗偰1903擭偵戞2斉偲側偭偨丅1930擭偵杮暥偺2攞検偺晅榐傪偮偗丄偐偮戝暆側夵掕偑峴傢傟偰戞7斉偲側偭偨丅拞懞岾巐榊巵偵傛傞擔杮岅傊偺東栿杮偼1943擭乮僸儖儀儖僩偺巰偺擭乯峅暥摪傛傝弌斉偝傟丄愴屻戞3斉偱愨斉偲側偭偰偄偨杮彂偑1969擭惔悈峅暥摪傛傝敪姧偝傟偨丅栿幰拞懞岾巐榊巵乮1901亅1986擭乯偵偮偄偰偼丄巵偺斢擭偺悢妛巎尋媶偺掜巕偱偁偭偨嵅乆栘椡巵偑徯夘偟偰偄傞丅拞懞岾巐榊巵偼1926擭搶戝棟妛晹悢妛壢傪懖嬈偟丄搶嫗崅摍巘斖妛峑島巘偵側傝丄1929擭傛傝僗僀僗偺僠儏乕儕僢僸戝妛偵棷妛偟丄僩億儘僕乕乮埵憡婔壗妛乯偺擔杮傊偺摫擖幰偲偟偰抦傜傟偰偄傞丅愴屻偼戝嶃戝妛丄娭惣妛堾戝妛丄暫屔堛壢戝妛偱悢妛偺嫵曏傪偲偭偨丅偐偨傢傜拞懞巵偼壓懞撔懢榊偺塭嬁偱悢妛巎尋媶偵栚妎傔丄愴屻偼尨椇媑巵偲偲傕偵悢妛巎尋媶傪棫偪忋偘偨丅変乆偺悽戙偱偼夰偐偟偄庴尡悢妛嶲峫彂乽僠儍乕僩幃悢妛僔儕乕僘乿偺挊幰偲偟偰妶桇偟偨丅埲壓杮彂姫枛偺拞懞巵偺夝愢偵廬偭偰丄僸儖儀儖僩偺乽婔壗妛婎慴榑乿偺悢妛巎忋偺堄媊偵偮偄偰妛傫偱備偙偆丅1891擭僂傿乕僫乕偑僴儖儗偱峴偭偨島墘偑僸儖儀儖僩偺婔壗妛婎慴榑偺廳梫側摦婡偲側偭偨丅揰偲慄偺寢傃偲岎嵆傪桳尷夞孞傝曉偟偰摼傜傟傞乽岎揰掕棟乿偼偄傢備傞僨僓儖僌偺掕棟偲僷僗僇儖偺掕棟傪壖掕偡傟偽偙偲偛偲偔徹柧偱偒傞偲弎傋偰丄幩塭婔壗妛偺婎杮掕棟偵摫偄偨丅偙偆偟偰乽婔壗妛偺岞棟偵撈棫偵丄偟偐傕婔壗妛偵暯峴偟偰堦偮偺拪徾揑妛栤偺揥奐偑壜擻偱偁傞偐偳偆偐傪栤戣偲偟偨丅偙傟傪暦偄偨僸儖儀儖僩偑婣傝偺婦幵撪偱摨椈偺悢妛幰偵乽揰丄捈慄丄暯柺偲偄偆尵梩偺戙傢傝偵丄僥乕僽儖丄堉巕丄偦偟偰價乕儖丒僕儑僢僉偲尵偄姺偊傞偙偲偑偱偒側偔偰偼偹乿偲偄偆桳柤側寈嬪傪揻偄偨偲偄偆丅偙偺尵梩偺杮幙偼乽悢妛揑偵偼婔壗妛揑奣擮偺捈姶揑撪梕偑栤戣側偺偱偼側偔丄婔壗妛揑奣擮偺岞棟偵傛傞寢傃偮偒偑栤戣側偺偱偁傞乿偲偄偆尒夝偱偁偭偨丅1894擭僸儖儀儖僩偼旕儐乕僋儕僢僪婔壗妛偺島媊傪峴偄丄1898擭儐乕僋儕僢僪婔壗妛偺島媊傪峴偭偨丅僸儖儀儖僩偑婔壗妛偺妚柦傪峴偆偙偲偼扤傕抦傞桼傕側偐偭偨偺偱丄偦偺尒夝偵懡偔偺恖乆偼嬃堎偲姶柫傪怺傔偨偲偄偆丅儐乕僋儕僢僪偺乽婔壗妛尨榑乿偵傛傞徹柧曽朄偲偼丄掕媊乕岞弨乕岞棟傪婎慴偵抲偔曽朄偱丄2000擭埲忋悢妛揑巚峫朄偺戙昞偲偝傟偰偒偨丅帺柧側恀棟偵婎偯偒丄捈姶傪攔偟偰榑棟揑偵悑峴偝傟偨寢壥偲偟偰偺婔壗妛偺抦尒偼掕棟偺宍偵惍棟偝傟丄巒傔偰恀側傞傕偺偲偟偰彸擣偝傟偨丅偟偐偟儐乕僋儕僢僪婔壗妛偵偼傑偩傑偩夦偟偘側捈姶偑暣傟崬傫偱偄偨丅1882擭僷僢僔儏偺乽怴婔壗妛島媊乿偵偍偄偰丄掕媊傪梌偊側偄婎杮奣擮偲掕媊偡傞桿摫奣擮偲偐傜婎杮柦戣乮岞棟偵憡摉乯傪峔惉偡傞丅婎杮柦戣偼弮悎偵榑棟揑悇榑乮墘銏乯傪壜擻偲偟丄懠偺栤戣偺徹柧偺慜採偲側傞丅僷僢僔儏偺曽朄偼僸儖儀儖僩偺曽朄偺愭嬱偲側傞偲偄傢傟傞丅偟偐偟側偑傜儐乕僋儕僢僪偺尨榑偵偟傠丄僷僢僔儏偺曽朄偵偟傠丄偦偺婎杮柦戣乮岞棟乯偵偼捈姶揑側傕偺偑埶慠偲偟偰崿擖偟偰偄偨丅嬻娫婔壗妛揑側捈姶傊偺埶懚傪彍偒丄偙傟偵戙偭偰榑棟揑娭學傪傕偭偰偡傞棫応偼僸儖儀儖僩偵傛偭偰偼偠傔偰摓払偟偊偨偺偱偁傞丅岞棟偼傕偼傗帺柧偺恀棟偨傞堄枴傪幐偄丄宱尡傪昞尰偡傞傕偺偱偼側偔丄偦傟偼偨偩妛棟寶愝偺偨傔偺婎慴奣擮偺娫偺娭學傪掕傔傞壖掕偵夁偓側偔側偭偨丅嵟弶偺栺懇帠偺忦審師戞偱擟堄偺婔壗妛偑惗傑傟傞偺偱偁傞丅壖掕偺岞棟偺婎慴偺忋偵抸偐傟傞懱宯偼丄偦偺撪梕傪栤戣偲偡傞偺偱偼側偔嬶懱惈傪拪徾偟偰摼傜傟傞壜擻側宍幃惈偱偁傞丅偩偐傜僸儖儀儖僩偵巒傑傞20悽婭偺尰戙悢妛偼宍幃庡媊偲屇偽傟偨丅偟偨偑偭偰僸儖儀儖僩偺曽朄偺崻杮栤戣偼乽柍柕弬惈乿埲奜偵偼側偄丅
岞棟宯偑枮懌偡傋偒忦審偲偟偰僸儖儀儖僩偼柍柕弬惈偺栤戣丄撈棫惈偺栤戣丄姰慡惈偺栤戣偺3偮傪枮偨偡傋偒偱偁傞偲偄偆丅杮彂戞2復仒9乽岞棟偺柍柕弬惈乿偵偍偄偰僸儖儀儖僩偼幚悢傕梡偄偰僨僇儖僩婔壗妛傪嶌傝丄婔壗妛偺岞棟偺柍柕弬惈偺栤戣傪幚悢偺岞棟宯偺柍柕弬惈偵揮壟偟偨丅杮彂晅榐偺乽悢偺奣擮偵偮偄偰乿偼堦偮偺夝摎偱偁傞偑丄埶慠偲偟偰栤戣偼巆偭偰偄傞丅婔壗妛偺岞棟揑曽朄偑惉棫偟偨偺偼僊儕僔儍帪戙偱偁傞偑丄嶼弍乮戙悢乯偺婎慴揑曽朄偲偟偰惗惉揑曽朄偑妋棫偟偨偺偼1867擭僴儞働儖偺乽暋慺悢宯偺棟榑乿偐傜偺偙偲偱偁傞丅悢偺巐懃墘嶼偺彅朄懃偡側傢偪寢崌棩丄岎姺棩丄暘攝棩偼乽宍幃晄堈偺尨棟乿傪妋棫偟丄嶼弍偼惗惉榑揑偲側偭偨丅僸儖儀儖僩偼嶼弍傕傑偨岞棟榑揑曽朄偺懳徾偲側傞偙偲傪帵偟偨丅偙傟偼暔棟妛偺岞棟榑偲摨偠偔嶼弍偺柍柕弬惈偑夝寛偟偨傢偗偱偼側偔丄屻擭僎乕僨儖偼乽晄姰慡惈掕棟乿傪敪昞偟偰嶼弍偺柍柕弬惈傪斲掕偟偨丅師偵廳梫側偺偼岞棟偺撈棫惈偲廬懏惈偺栤戣偱偁傞丅儐乕僋儕僢僪偺暯峴慄岞棟偺栤戣偱偁傞丅偙偺岞棟偼偳偙偐傜棃偨偺偩傠偆偐丅僨僨僉儞僩偼乽悢偲偼壗偧傗乿偵偍偄偰乽儐乕僋儕僢僪偺嶌恾偑楢懕嬻娫偵偍偄偰懚嵼偡傞傕偺偲偟偰丄戙悢揑悢偺晄楢懕惈偵慡偔婥偑晅偄偰偄側偄乿偲偄偆丅楢懕惈岞棟偼儐乕僋儕僢僪偺岞棟偐傜撈棫偱偁傞偲偄偆丅傑偨僸儖儀儖僩偼岞棟娫偺榑棟揑廳暋揑傪旔偗傞偲偄偆曽恓偱丄岞棟偺悢傪偱偒傞偩偗彮側偔偡傞偨傔丄暯峴慄偺栤戣傪岞棟偺柦戣憡屳娫偺榑棟揑娭學偺拞偵媧廂偟偨丅岞棟宯偺枮懌偡傋偒戞3偺忦審偲偟偰姰慡惈偑梫媮偝傟傞丅婔壗妛偺峔惉梫慺乮揰丄慄丄暯柺丒丒丒丒乯偺廤崌偑梌偊傜傟偨岞棟傪慡晹惉棫偣偟傔傞側傜偽丄偙傟埲忋偺梫慺偺奼戝偼晄壜擻偱偁傞偲偟偰岞棟嘪2偲偟偨丅幚悢偺柍柕弬惈偺栤戣偼僨僨僉儞僩偺愗抐丄僇儞僩乕儖偺婎杮楍偺奣擮偺摫擖偵傛傝丄廤崌榑偺曽朄傪梡偄偰帺慠悢偺棟榑偲側偭偨丅偦偙傊悢妛婎慴榑偺婋婡偑廝偭偨丅偦傟偼廤崌榑偵偍偗傞攚棟偺弌尰偱偁傞丅僸儖儀儖僩偼偙偺婋婡傪媬偆偨傔偵宍幃庡媊傪曇傒弌偟偨偺偱偁傞丅嶼弍偲榑棟妛偲傪摨帪偵岞棟壔偡傞曽朄傪庢偭偨丅1904擭戞3夞崙嵺悢妛幰夛媍偱乽榑棟妛偲嶼弍偺婎慴偵偮偄偰乿偺島墘傪峴偄丄偙傟偼杮彂晅榐偺乽岞棟榑揑巚堃乿偲側偭偨丅僸儖儀儖僩偺乽婔壗妛婎慴榑乿偺峔惉偼丄戞1復偼岞棟宯偺愝掕丄戞2復偼偦偺柍柕弬惈偲撈棫惈丄姰慡惈傪榑偠偨丅偦偟偰戞3復埲崀偼婔壗妛撪晹偺栤戣偑榑偠傜傟偰偄傞丅乮戞3復丗斾椺棟榑丄戞4復丗柺愊棟榑丄戞5復丗僨僓儖僌偺掕棟丄戞6復丗僷僗僇儖偺掕棟丄戞7復丗嶌恾乯丂偦偺棟榑揑揥奐偱巜摫揑尨棟偲偄偆傋偒師偺3偮偺摿挜偑偁傞丅杮彂傪傛偔撉傔偽丄師偺3揰偑偄偮傕偱偰偔傞偙偲偵婥偑晅偔偼偢偱偁傞丅
1) 丂暯峴慄岞棟偺彍奜丗丂岞棟慖戰偺忦審傪桳尷偺斖埻偵偺傒惉棫偡傞岞棟傪巊偆偲偄偆僋儔僀儞偺尒夝偵揔崌偡傞偨傔丅
2)丂楢懕岞棟偺彍奜丗丂楢懕惈岞棟偱偁傞傾儖僉儊僨僗偺岞棟傪旔偗偨旕傾儖僉儊僨僗悢懱
3)丂棫懱婔壗偲暯柺婔壗妛偺榑棟揑嵎暿丗丂暯柺婔壗妛傪嬻娫偵埶懚偣偢帺棩揑乮摿堎揑乯偵婎慴偯偗傞丅僨僓儖僌偺掕棟偼暯柺婔壗妛偱偼3妏宍偺崌摨掕棟傪昁梫偲偡傞丅
偦偟偰僸儖儀儖僩偺婔壗妛婎慴榑傪摫偔摑堦尨棟偲偄偆傋偒乽慄暘嶼乿偲偄偆奣擮偑偁傞丅偮傑傝婔壗妛岞棟偺壓偵岻柇偵悢偺岞棟傪帩偪崬傓傗傝曽偱偁傞丅偙傟傪婔壗妛偺戙悢壔丄懱偺婔壗妛偲屇偽傟傞丅偙偆偟偰偒傢傔偰傛偄尒捠偟偑摼傜傟傞丅
嘆壜姺揑戙悢壔丗丂楢懕岞棟傪彍偔暯柺岞棟偺婎慴偺壓偱僷僗僇儖偺掕棟偑徹柧偱偒傞丅乮戞3復乯丂偙偺壜姺揑戙悢偺婎慴偺忋偵丄僸儖儀儖僩偼楢懕偺岞棟側偟偵乮撈棫偵乯丄斾椺偺棟榑傪抸偄偨丅摨帪偵摍愊惈偺奣擮丄柺愊應掕偺懚嵼傪柧傜偐偵偟偨丅乮戞4復乯
嘇旕壜姺揑戙悢壔丗丂崌摨偺岞棟側偟偵丄備傞偄暯峴偺岞棟偲僨僓儖僌偺掕棟偲偺婎慴偺忋偵僨僓儖僌悢宯乮岎姺棩壜擻偱偼側偄乯偑嶌傜傟偨丅乮戞5復乯僨僓儖僌偺掕棟偼暯柺婔壗妛岞棟偱偼崌摨偺岞棟側偟偵偼徹柧晄壜擻偱偁傞丅戞2偺岎揰掕棟偱偁傞僷僗僇儖偺掕棟偼慄暘嶼偺忔朄偺岎姺棩偑惉傝棫偮偙偲偱偁傞丅乮戞6復乯丂
嘊憤懱幚悢懱丗丂僨僇儖僩偑夝愅婔壗妛揑榑朄傪摫擖偟偨偙偲偼丄庡偲偟偰嶌恾偺夝朄偲偟偰摑堦揑側戙悢妛偺曽朄傪墳梡偡傞偙偲偑栚揑偱偁偭偨丅乮戞7復乯偙偙偵偍偄偰傕戙悢揑奣擮偨傞憤懱揑幚悢懱偑廳梫側栶妱傪壥偨偡丅
僸儖傋儖僩偺慄暘嶼棟榑偼懱偺奣擮傪拞怱偲偡傞拪徾揑榑朄偱偁傞丅僸儖儀儖僩偺乽婔壗妛婎慴榑乿偼婔壗妛偲偄偆幚椺偵偍偄偰丄堦偮偺悢妛揑拪徾榑朄偺姰惉宍傪帵偟偨傕偺偲尵偊傞丅僸儖儀儖僩偺岞棟揑曽朄偼丄柍柕弬惈榑偵偼栤戣偑偁傞偲偟偰傕丄悢妛帺懱偺拞偵拪徾悢妛偺尠挊側敪尰偲敪払偺庬傪傑偄偨偲偄偆帠幚偼斲掕偟傛偆傕側偄丅
埲壓杮暥偵擖傞慜偵丄彉偵偁傞僸儖儀儖僩偺尵梩傪婰壇偟偰偍偒偨偄丅
傑偢僇儞僩乽弮悎棟惈斸敾乿傛傝丄乽偐偔偺偛偲偔恖娫偺偁傜備傞擣幆偼捈姶傪傕偭偰巒傑傝丄奣擮偵恑傒丄棟惈傪傕偭偰廔寢偡傞乿
彉傛傝丄乽婔壗妛偼嶼弍偲摨條偵偦偺柕弬側偒寶愝偺偨傔偵嬌傔偰彮悢偺丄娙扨側婎杮柦戣傪昁梫偲偡傞丅偙偺婎杮柦戣傪岞棟偲偄偆丅婔壗妛偺岞棟傪愝掕偟丄偦偺憡屳娭學傪尋媶偡傞偙偲偼儐乕僋儕僢僪埲棃榑偠傜傟偰偒偨偑丄変乆偺嬻娫揑捈娤傪榑棟揑偵暘愅偡傞偙偲偵懠側傜側偄丅杮尋媶偼婔壗妛偵懳偟偰堦偮偺姰慡偱偱偒傞偩偗娙寜側岞棟偺懱宯傪愝掕偟丄偙傟傛傝嵟傕廳梫側掕棟傪摫偒丄岞棟孮偺堄枴偲屄乆偺岞棟偐傜摫偒摼傞寢榑偺斖埻傪柧傜偐偵偣傫偲偡傞怴偟偄帋傒偱偁傞丅乿
埲壓杮暥偵擖傞傢偗偱偁傞偑丄儂乕儉儁乕僕惂嶌偺HTML暥朄偱偼丄恾宍傪昤偔偙偲傗悢幃傗曽掱幃傪彂偔偙偲偼崲擄偱偁傞丅偦偙偱僥僉僗僩乮暥復乯偺傒偱昞尰偡傞偙偲偵側傝丄棟夝偼偝傜偵崲擄偱偁傞偐傕偟傟側偄偺偱偛梕幫捀偒偨偄丅
婔壗妛偺峔惉梫慺偲偟偰丄嘆揰丄嘇捈慄丄嘊暯柺偺3偮傪峫偊丄揰傪捈慄婔壗妛偺峔惉梫慺丄揰偲捈慄傪暯柺婔壗妛偺峔惉梫慺丄揰丄捈慄丄偍傛傃暯柺傪棫懱婔壗妛偺峔惉梫慺偲偄偆丅乮峔惉梫慺偵偼側偤偐墌傗嬋慄傗媴懱丄懭墌懱側偳偑偑擖偭偰偄側偄丄夝愅婔壗妛偵擟偣偨偺偐乯
偦偟偰婔壗妛偺岞棟傪師偺5孮偵暘偐偮丅嘥1-8(寢崌偺岞棟乯丄嘦1-4乮弴彉偺岞棟乯丄嘨1-5乮崌摨偺岞棟乯丄嘩乮暯峴偺岞棟乯丄嘪1-2乮楢懕偺岞棟乯
岞棟孮嘥丗寢崌偺岞棟
嘥1丗丂2揰A,B偵懳偟丄偙傟傜偺2揰偺奺乆偲寢崌偡傞彮側偔偲傕堦偮偺捈慄偑忢偵懚嵼偡傞丅
嘥2丗丂2揰A,B偵懳偟丄偙傟傜偺2揰偺奺乆偲寢崌偡傞捈慄偼傂偲偮傛傝偼懡偔偼懚嵼偟側偄丅
嘥3丗丂1捈慄忋偵偼偮偹偵彮側偔偲傕2揰偑懚嵼偡傞丅1捈慄忋偵側偄彮側偔偲傕3揰偑懚嵼偡傞丅乮捈慄偼2揰偱婯掕偝傟傞乯
嘥4丗丂摨堦捈慄忋偵側偄擟堄偺3揰A,B,C偵懳偟丄偦偺奺揰偲寢崌偡傞侾暯柺兛偑懚嵼偡傞丅擟堄偺暯柺偵懳偟偙傟偲寢崌偡傞侾揰偑忢偵懚嵼偡傞丅乮A偼兛偺揰偱偁傞乯
嘥5丗丂摨堦捈慄忋偵側偄擟堄偺3揰A,B,C偵懳偟丄3揰A,B,C偺奺乆偲寢崌偡傞暯柺偼1偮埲忋偼懚嵼偟側偄丅
嘥6丗丂1捈慄a偺忋偵偁傞2揰A,B偑暯柺兛忋偵嵼傟偽丄a偺偡傋偰偺揰偼暯柺兛偺忋偵偁傞丅乮捈慄a偼暯柺兛偺忋偵偁傞乯
嘥7丗丂2暯柺兛丄兝偑1揰傪嫟桳偡傟偽丄偙傟傜偺暯柺偼偝傜偵傕偆1揰傪嫟桳偡傞丅
嘥8丗丂摨堦暯柺忋偵側偄彮側偔偲傕4揰偑懚嵼偡傞丅乮暯柺偼3揰偱婯掕偝傟傞乯
岞棟孮嘦丗弴彉偺岞棟乮娫偺掕媊乯
嘦1丗丂揰B偑揰A偲揰C偲偺娫偵偁傟偽丄A,B,C偼1捈慄忋偺憡堎側傞3揰偱偁偭偰丄偐偮B偼C偲A偺娫偵偁傞丅
嘦2丗丂2揰A偲C偲偵懳偟偰捈慄AC忋偵彮側偔偲傕1揰B偑懚嵼偟偰丄C偑A偲B偲偺娫偵偁傞丅
嘦3丗丂1捈慄忋偵偁傞擟堄偺3揰偺偆偪偱丄懠偺2揰偺娫偵嵼傝摼傞傕偺偼1揰傛傝懡偔偼側偄丅
嘦4丗丂A,B,C傪1捈慄忋偵側偄3揰丄捈慄a傪暯柺ABC忋偵偁偭偰A,B,C偺偄偢傟傪傕捠傜側偄捈慄偲偡傞丅捈慄a偑慄暘AB偺揰傪捠傟偽偙傟偼傑偨慄暘AC傕偟偔偼慄暘BC偺揰傪捠傞丅僷僢僔儏偺岞棟偲傕偄偆丅乮捈慄a偼3妏宍ABC偺2曈傪墶愗傞偙偲偑偱偒傞乯
岞棟孮嘨丗崌摨偺岞棟
嘨1丗丂A,B傪1捈慄a偺忋偺2揰偲偟丄偝傜偵A'傪摨偠捈慄傑偨偼懠偺捈慄a'忋偺揰偲偡傞偲偒丄捈慄a'偺A'偵娭偟偰梌偊傜傟偨懁偵忢偵彮側偔偲傕1揰B'傪尒弌偟丄慄暘AB偑慄暘A'B'偵崌摨傑偨偼憡摍偟偔側傞傛偆偵偡傞偙偲偑偱偒傞丅婰崋偱AB佭A'B'
嘨2丗丂慄暘A'B'偍傛傃慄暘A"B"偑摨堦偺慄暘AB偵崌摨側傜丄慄暘A'B'偼慄暘A"B"偵崌摨偱偁傞丅乮奺慄暘偑戞3偺慄暘偵崌摨側傜丄奺乆偼崌摨偱偁傞乯
嘨3丗丂AB偍傛傃A'B'傪捈慄a忋偺嫟捠揰偺側偄2慄暘丄偝傜偵A'B'偍傛傃B'C'傪摨偠捈慄傑偨偼懠偺捈慄a'忋偵偁偭偰摨條偵嫟捠傪傕偨側偄偲偡傞偲丄AB佭A'B'偐偮BC佭B'C'側傜偽丄偮偹偵AC佭A'C'偱偁傞丅乮壛朄偺壜擻偲偄偆乯
嘨4丗丂暯柺兛撪偵妏佢乮h,k)偑梌偊傜傟丄暯柺兛'撪偵1捈慄a偍傛傃a'偵娭偡傞堦偮偺懁偑巜掕偝傟偰偄傞側傜偽丄h'傪揰O'偐傜弌傞捈慄a'偵懏偡傞敿捈慄偲偡傞偲妏佢(h,k)佭妏佢(h',k')側傞敿捈慄k'偑偨偩堦偮偵尷偭偰懚嵼偡傞丅乮妏傪堏偡偙偲偑偱偒傞乯
嘨5丗丂擇偮偺3妏宍ABC偍傛傃A'B'C'偵偍偄偰崌摨娭學AB佭A'B'丄AC佭A'C'丄佢ABC佭佢A'B'C'偑惉傝棫偰偽丄佢ABC佭佢A'B'C丄佢ACB佭佢A'C'B''偲側傞丅(3妏宍偺崌摨娭學乯
岞棟孮嘩丗暯峴偺岞棟
嘩丗丂乮儐乕僋儕僢僪偺岞棟乯丂a傪擟堄偺捈慄丄A傪a奜偺1揰偲偡傞偲丄a偲A偑掕傔傞暯柺偵偍偄偰A傪捠傝a偵岎傢傜側偄捈慄偼偨偐偩偐傂偲偮懚嵼偡傞丅
岞棟孮嘪丗楢懕偺岞棟
嘪1: (寁應偺岞棟丄傾儖僉儊僨僗偺岞棟乯丂AB媦傃BC傪擟堄偺慄暘偲偟丄捈慄AB傪An-1An佭CD=a側傞扨埵慄暘a偱暘妱偡傞偲B偑A偲An偺娫偵偁傞傛偆偵偡傞偙偲偑偱偒傞丅a亊(n-1)亙AB亙a亊n乮捈慄偺岞棟乯
嘪2丗乮1師尦偺姰慡岞棟乯丂1捈慄忋偵偁傞揰偼丄慄忬掕棟丄崌摨岞棟嘨1丄偍傛傃傾儖僉儊僨僗偺岞棟傪曐偮尷傝偱偼乮偡側傢偪嘥1-2丄嘦丄嘨1丄嘪1乯傕偼傗偙傟埲忋奼戝晄壜擻側揰偺廤傑傝偱偁傞丅
岞棟孮嘥亅嘪傑偱傪忋弎偟偨偑丄杮彂偵偼岞棟偐傜徹柧偝傟傞寢榑偲偟偰偦偺堦晹傪掕棟偲偟偰徯夘偟偰偄傞丅岞棟孮嘥乮寢崌乯傛傝掕棟1丄掕棟2傪丄岞棟孮嘦乮弴彉乯傛傝掕棟3亅10傪丄岞棟孮嘨乮崌摨乯傛傝掕棟11亅29傪丄岞棟孮嘩乮暯峴乯傛傝掕棟30亅31傪丄岞棟孮嘪乮楢懕乯傛傝掕棟32傪嫇偘傞偵偲偳傔傞丅奺掕棟偼偡傋偰徹柧偑偮偄偰偄傞偺偱梕堈偵妋擣偱偒傞丅偙偙傑偱偼儐乕僋儕僢僪偺尨榑偲偝偟偰偐傢傜側偄丅偨偩拲堄偟偰傒傞偲擖岥偺忦審偱偁傞岞棟偺慖戰偼嬌傔偰廳梫偱丄廳暋傪旔偗丄偱偒傞偩偗彮側偄悢偺岞棟偵惍棟偟丄撈棫娭學傪尒捈偟丄壗傪帺柧偲偡傞偐偼帪戙偵傛偭偰曄慗偡傞偺偱丄僸儖儀儖僩偺宒娽偵宧暈偡傞偽偐傝偱偁傞偑丄偙傟傕栺懇帠偱愨懳揑恀棟偱偼側偄偺偱悢懡偔偺婔壗妛偑懚嵼偟偆傞偙偲偼娞偵柫偠側偗傟偽側傜側偄丅偩偐傜婔壗妛偼柺敀偄丅
5偮偺岞棟孮偑屳偄偺柕弬傪堷偒婲偙偝側偄偙偲傪丄偙傟傜偺岞棟偐傜榑棟揑偵堷偒弌偡偙偲偼偱偒側偄丅偦偙偱幚悢傪梡偄偰5孮偺岞棟傪偺偡傋偰偑枮懌偝傟傞暔偺廤傑傝傪峫偊傛偆丅偙偺廤傑傝傪椞堟兌偲偄偆戙悢揑悢懱偲偡傞丅巐懃墘嶼偲併乮1亄冎^2乯偺5偮偺墘嶼傪桳尷夞孞傝曉偟偰摼傜傟傞悢椞堟偱偁傞丅2師尦嵗昗傪慖傫偱丄乮x,y)偲(u:v:w)3悢偺斾偵偍偄偰ux+vy+w=0偑捈慄偺曽掱幃偲側傞丅岞棟嘥丄岞棟嘦乮弴彉乯偺惉棫偼梕堈偵傢偐傞丅偦偟偰夝愅婔壗妛偺廃抦偺曽朄偵傛偭偰丄暯峴堏摦丄愜傝曉偟丄夞揮側偳偺憖嶌傪戙悢墘嶼壔偡傞丅偙傟偵傛偭偰岞棟嘨乮崌摨乯丄岞棟嘩乮暯峴乯傕傑偨惉棫偡傞丅傾儖僉儊僨僗偺岞棟嘪1乮楢懕乯傕傑偨惉棫偡傞丅偟偐偟姰慡惈偺岞棟嘪2偼惉棫偟側偄丅偙偆偟偰椞堟兌偺戙傢傝偵偡傋偰偺幚悢偺椞堟傪庢傟偽暯柺僨僇儖僩婔壗妛偑摼傜傟傞丅僨僨僉儞僩愗抐偵傛偭偰怴揰傪嶌傞偲柕弬偲側傞偙偲偐傜丄暯柺僨僇儖僩婔壗妛偵偍偄偰偼姰慡惈偺岞棟嘪2傕惉棫偡傞丅岞棟嘥亅嘩丄嘪1傪枮懌偡傞婔壗妛偼柍悢偵偁傞偑丄姰慡惈岞棟嘪2傑偱枮懌偡傞婔壗妛偼僨僇儖僩婔壗妛偺傒偱偁傞丅師偵岞棟孮嘥丄嘦偩偗偼彅岞棟偺婎慴偲偟偆傞偑丄嘨崌摨偺岞棟丄嘩暯峴偺岞棟丄嘪楢懕偺岞棟偼屳偄偵撈棫偱偁傞偙偲傪帵偡丅偨偲偊偽媴柺傪偲偭偰僨僇儖僩婔壗妛偺曄姺傪峴偆偲丄偙偺旕儐乕僋儕僢僪婔壗妛偵偍偄偰偼岞棟嘩乮暯峴偺岞棟乯埲奜偼慡岞棟偑枮懌偝傟傞偙偲傪抦傞丅偲偔偵2偮偺儖僕儍儞僪儖偺掕棟偼丄儐乕僋儕僢僪婔壗妛偵偍偄偰傕旕儐乕僋儕僢僪婔壗妛偵偍偄偰傕摨帪偵惉棫偡傞掕棟偱偁傞丅
儖僕儍儞僪儖偺戞1掕棟丗丂嶰妏宍偺偺撪妏偺榓偼2捈妏傛傝傕彫偝偄偐丄偁傞偄偼偙傟偵摍偟偄丅
儖僕儍儞僪儖偺戞2掕棟丗丂偄偢傟偐偺傂偲偮偺嶰妏宍偵偍偄偰撪妏榓偑2捈妏側傜丄偁傜備傞嶰妏宍偺撪妏榓偼2捈妏偱偁傞丅
戞1掕棟偼妏偺戝彫偼懳曈偺戝彫偵傛偭偰寛傑傞偲偄偆曗彆掕棟傪棙梡偟偰丄偠偮偵濨枂側昞尰偱嶰妏宍偺撪妏榓偑2捈妏埲壓偱偁傞偙偲傪尵偆丅戞2掕棟偼暯峴偲偄偆奣擮傪巊傢偢丄捈妏嶰妏宍偲巐曈宍偺妏偑偡傋偰捈妏偲偄偆昞尰偱嶰妏宍偺撪妏榓偑2捈妏偱偁傞偙偲傪帵偡丅偮偓偵嘨崌摨偺岞棟偺嘨5丗丂擇偮偺3妏宍ABC偍傛傃A'B'C'偵偍偄偰崌摨娭學AB佭A'B'丄AC佭A'C'丄佢ABC佭佢A'B'C'偑惉傝棫偰偽丄佢ABC佭佢A'B'C丄佢ACB佭佢A'C'B''偲側傞丅(3妏宍偺崌摨娭學乯偼巆傝偺岞棟嘥丄嘦丄嘨1-4丄嘩丄嘪偐傜墘銏偱偒側偄偙偲傪帵偡丅傑偨岞棟嘪1乮傾儖僉儊僨僗偺岞棟乯偺撈棫惈偼丄暋慺悢椞堟兌(t)偵偍偄偰旕傾儖僉儊僨僗婔壗妛傪嶌傞偙偲偑偱偒傞丅旕傾儖僉儊僨僗偱旕儐乕僋儕僢僪婔壗妛偺堦偮偲偟偰儕乕儅儞乮懭墌乯婔壗妛偑偁傞丅傾儖僉儊僨僗偺岞棟傪壖掕偟側偗傟偽丄柍悢偺暯峴慄偑堷偗傞偙偲傪壖掕偟偰傕丄嶰妏宍偺撪妏榓偑2捈妏傛傝彫側傞偙偲偼徹柧偝傟側偄丅1揰傪捠傝1捈慄偵暯峴側柍悢偺捈慄偑堷偗偰丄儕乕儅儞婔壗妛偺彅掕棟偑惉傝棫偮婔壗妛傪旕儖僕儍儞僪儖婔壗妛偑懚嵼偡傞丅側偍1揰傪捠傝1捈慄偵懳偟偰柍悢偺捈慄偑堷偗丄偐偮儐乕僋儕僢僪婔壗妛偺掕棟偑惉傝棫偮敿儐乕僋儕僢僪婔壗妛偑懚嵼偡傞丅暯峴慄偼1杮傕堷偗側偄偲壖掕偡傟偽丄嶰妏宍偺撪妏榓偼偮偹偵2捈妏傛傝戝偲側傞丅
斾椺偼嶰妏宍偺憡帡偲偒傝棧偣側偄偟丄偐偮墘嶼偲枾愙側娭學偵偁傞丅幚悢偲偼師偺彅惈幙傪帩偮傕偺偺廤傑傝偱偁傞丅傂偲傑偢悢偺奣擮偺岞棟壔傪傔偞偡丅
寢崌偺掕棟(1-6)
侾丄乮壛朄乯丂a+b=c 丂偁傞偄偼丂c=a+b
2丄乮尭朄乯丂a+x=c丂傑偨偼丂y+a=b丂側傞偨偩堦偮偺x,y偑懚嵼偡傞丅
3丄乮僛儘偺懚嵼乯丂a+0=a 偁傞偄偼丂0+a=a
4丄乮忔朄乯丂ab=c丂偁傞偄偼丂c=ab
5丄乮彍朄乯丂ax=b丂傑偨偼丂ya=b丂側傞偨偩傂偲偮偺x,y偑懚嵼偡傞丅
6丄乮1偺懚嵼乯丂a丒1=a丂偐偮丂1丒a=a丂側傞妋掕偟偨悢偑懚嵼偡傞丅偙傟傪1偲偄偆丅
墘嶼偺朄懃(7-12)
7丄乮壛朄偺寢崌懃乯丂a+(b+c)=(a+b)+c
8丄乮壛朄偺壜姺懃乯丂a+b=b+a
9丄乮忔朄偺寢崌懃乯丂a(bc)=(ab)c
10丄乮暘攝懃乯a(b+c)=ab+ac
11丄乮暘攝懃乯(a+b)c=ac+bc
12丄乮忔朄偺壜姺懃乯丂ab=ba丂丂
弴彉偺掕棟(13-16)
13丄(戝彫娭學乯丂a亜b丂偍傛傃丂b亙a偺偄偢傟偐偱偁傞側傜丄a亜a丂側傞悢偼懚嵼偟側偄丅
14丄a亜b丂偐偮丂b亜c側傜偽丂a亜c偱偁傞丅
15丄a亜b丂側傜偽丂a+c亜b+c
16丄a亜b丂偐偮丂c亜0側傜偽丂ac亜bc
楢懕偺掕棟(17-18)
17丄乮傾儖僉儊僨僗偺掕棟乯丂a,b偑擟堄偺2悢偲偡傞偲丄a傪桳尷夞壛偊偰丂a+a+a丒丒丒丒+a亜b (na亜b)偵偡傞偙偲偑壜擻偱偁傞丅
18丄乮姰慡惈偺掕棟乯丂掕棟1亅17傪慡晹惉棫偝偣傞悢偼傕偼傗偙傟埲忋奼戝晄壜擻偱偁傞丅
惈幙1亅18偺偄偔偮偐傪枮懌偡傞傕偺偺廤傑傝傪暋慺悢宯偲偄偆丅忦審17傪枮懌偡傞悢傪傾儖僉儊僨僗揑丄枮懌偟側偄悢傪旕傾儖僉儊僨僗揑悢宯偲偄偆丅偲偵偐偔忦審17偼摿暿偵撈棫側惈幙偱偁傞丅
斾椺偲柺愊棟榑傪嘪1傾儖僉儊僨僗偺楢懕岞棟傪梡偄側偄偱丄儐乕僋儕僢僪偺斾椺榑偲媮愊榑傪偰傫偐偄偡傞傕偺偱偁傞丅偦偺偨傔偵婔壗妛偺峫嶡傪戙悢壔偡傞丅偨偲偊偽捈妏嶰妏宍偺幬曈傪c偲偡傞妏傪兛偲偟偰丄a=們亊cos乮兛乯偲偄偆娭學傪丄a=兛c偲昞偡丅兛丄兝傪捈妏嶰妏宍偺2偮偺塻妏偲偡傞偲丄兛兝c佭兝兛c偲偄偆墘嶼巕偺壜姺惈偑徹柧偝傟丄僷僗僇儖偺掕棟偑摼傜傟傞丅
掕棟40乮僷僗僇儖偺掕棟乯丗A,B,C偍傛傃A',B',C'偑偦傟偧傟3揰偯偮憡岎傢傞2捈慄忋偵嵼傝丄奺揰偼岎揰偵偼側偄偲偡傞偲丄CB'偑BC'偵暯峴乮CB'乤BC')偐偮CA'偑AC'偵暯峴乮CA'乤AC')側傜偽丄BA'偼AB'偵暯峴乮BA'乤BA')偱偁傞丅
偲偄偆掕棟偑墘嶼巕偺揥奐偺傒偱徹柧偝傟傞丅斾椺榑偺婎慴偯偗偵偼捈妏2摍曈嶰妏宍偲偄偆僷僗僇儖偺掕棟偺摿庩働乕僗傪梡偄傞丅側偍偙偆偄偆婔壗妛偵戙悢墘嶼傪摫擖偡傞偙偲傪寵偆恖偨偪偼乽墌榑乿傪惓摑側婔壗妛偲怣偠偰偄傞丅暋嶨側崅搙側嶌恾傪昁梫偲偡傞丅僷僗僇儖偺掕棟偼帤悢偵娭偡傞寁嶼朄懃偑偦偺傑傑惉棫偡傞偐偺偛偲偒丄慄暘傪尦慺偲偡傞寁嶼傪婔壗妛偵摫擖偡傞偙偲偵側偭偨丅偙傟傪僸儖儀儖僩偼乽慄暘嶼乿偲屇傫偩丅捈慄忬偺慄暘偵丄壛朄丄寢崌懃丄壛朄偺岎姺懁偑惉棫偡傞偙偲偼偡偖傢偐傞丅忔朄媦傃忔朄偺岎懃丄偦偟偰暘攝懃偑僷僗僇儖偺掕棟偐傜捈偪偵摫偐傟傞偙偲偼婔壗妛偺戙悢壔偺偡偛偝偱偁傞丅偙偺尒帠偝偵偼夵傔偰姶寖偟偨丅偙偆偟偰2偮偺嶰妏宍偺憡帡娭學偑摫偐傟傞丅
掕棟41(憡帡嶰妏宍偺偵偍偗傞斾椺娭學乯丂a,b偍傛傃a',b'傪擇偮偺憡帡嶰妏宍偵偍偗傞懳墳曈偲偡傞偲丄師偺斾椺偑惉傝棫偮丅a丗b=a'丗b'
夝愅婔壗妛偵傛偭偰丄捈岎幉傪庢傞偲尨揰傪捠傞捈慄偺曽掱幃偼丄捈慄偺孹偒偑偳偙偱傕摍偟偄偺偱丄x丗y=a丗b 丂亪bx-ay=o丄傑偨x=c偱墶愗傞捈慄偺曽掱幃偼b(x-c)-ay=0丂亪bx-ay-bc=0
偙偺復傕慜偺斾椺偺復偲摨偠岞棟乮嘥1-3,嘦丆嘨丆嘩乯偱丄慜復偺慄暘嶼傪梡偄偨僷僗僇儖偺掕棟傪嵦梡偡傞丅擟堄偺懡妏宍傪暘妱偟丄擇偮偺懡妏宍偑桳尷屄偺嶰妏宍偵暘偐偨傟丄懳墳偡傞2偮偯偮偺嶰妏宍偑崌摨側帪丄暘夝摍愊偲屇傃丄尦偺懡妏宍P,Q偵暘夝摍愊偱偁傞P',P"丒丒丒丄Q7,Q"丒丒丒傪晅壛偟偰儼P偲儼Q偑摍偟偔側傞偲偒丄偙傟傪曗廩摍愊偲屇傇丅掕棟44亅46偺摍愊惈偼梕堈偵徹柧偱偒傞丅
掕棟44丗丂摨掙丄摨崅偺暯峴巐曈宍偼屳偄偵曗廩摍愊偱偁傞丅
掕棟45丗丂擟堄偺嶰妏宍偼摨掙丄崅偝偑敿暘側傞暯峴巐曈宍偲暘夝摍愊偱偁傞丅
掕棟46丗丂摨掙丄摨崅偺嶰妏宍偼屳偄偺曗廩摍愊偱偁傞丅
偟偐偟偙傟偩偗偱偼柺愊應搙偼偱偒側偄丅擟堄偺嶰妏宍偺捀揰乮A,B,C)偐傜懳曈(a,b,c)偵崀傠偟偨悅慄(ha,hb,hc)偑嶌傞暘妱嶰妏宍(捈妏嶰妏宍偺懳墳撪妏偑偡傋偰摍偟偄乯偺憡帡惈偐傜丄斾椺娭學a丗hb=b丗ha偑摼傜傟丄a丒ha=b丒hb偡側傢偪掙曈偲崅偝偺愊偼偳偺曈偵偍偄偰傕摨偠偱偁傞丅惓偺夞揮曽岦乮慄暘AB偺塃懁乯傪帩偮嶰妏宍ABC偺柺愊應搙乵ABC乶偵娭偡傞掕棟偑摼傜傟傞丅
掕棟49丗丂嶰妏宍ABC偺奜偵揰O傪庢傞偲偒丄嶰妏宍偺柺愊應搙乵ABC]=[OAB]+[OBC]+[OCA]
偙偆偟偰曗廩摍愊側傞懡妏宍偼摨堦偺柺愊應搙傪桳偡傞丅僈僂僗偼懱愊偺棟榑偼暯柺柺愊榑偺傛偆偵偼備偐側偄偙偲偵拲堄傪懀偟偰偄傞丅巹偵偼偙偺柺愊棟榑偼彮偟偽偐傝晄枮懌偱偁傞丅懡妏宍傪暘夝偟偰嶰妏宍偵暘妱偟2偮偺懡妏宍偼摍愊惈偱偁傞偲偄偆偙偲偑徹柧偱偒偰傕柺愊傪媮傔傜傟傞偐偳偆偐偼暘偐傜側偄丅
杮復僨僓儖僌偺掕棟偲師復僷僗僇儖偺掕棟偱偼丄岞棟嘨崌摨偺岞棟偼壖掕偟側偄丄傑偨暯峴偺岞棟偼嫹偔偲傝丄偙傟傪嘩*偲偡傞丅僨僓儖僌偺掕棟偼暯柺岎揰掕棟偵堦偮偱偁傞丅憡帡側2偮偺嶰妏宍偺懳墳曈偺岎揰偑偑偁傞偄傢備傞乽柍尷墦捈慄乿偲屇傫偱摿暿帇偡傞乮摟帇恾朄乯帪偵惉傝棫偮掕棟傪乮偦偺媡傕乯僨僓儖僌偺掕棟偲屇傫偱偄傞丅
嘩*(嫹媊偺暯峴偺岞棟乯丗丂a傪擟堄偺1捈慄丄A傪偙偺捈慄忋偵側偄揰偲偡傞偲丄偙偺偲偒a偲A偺掕傔傞暯柺忋偱丄A傪捠傝a偵岎傢傜側偄捈慄偼偨偩堦偮偵尷偭偰懚嵼偡傞丅
掕棟53丂乮僨僓儖僌偺掕棟乯丗丂摨堦暯柺忋偵偁傞2偮偺嶰妏宍偵偍偄偰懳墳曈偑偦傟偧傟暯峴側傜偽丄懳墳捀揰偺楢寢捈慄偼1揰傪捠傞偐丄偨偑偄偵暯峴偱偁傞乮嶰妏宍偑崌摨側傜偽乯丅媡偵懳墳捀揰偺楢寢捈慄偑1揰偱岎傢傝丄2慻偺懳墳曈偑偦傟偧傟暯峴側傜偽丄嶰妏宍偺戞3曈傕傑偨偨偑偄偵暯峴偱偁傞丅
僨僓儖僌偺掕棟偼掕棟40偺僷僗僇儖偺掕棟媦傃屻偵弌偰偔傞掕棟61偐傜徹柧偝傟傞丅崌摨偺岞棟偵埶傜側偄僨僓儖僌偺掕棟傪壖掕偟偨慄暘嶼傪怴偟偔掕媊偡傞丅榓丄愊丄壛朄偺岎姺棩偲寢崌棩丄忔朄偺寢崌棩丄暘攝棩偺惉傝棫偮偙偲傪専徹偟丄怴慄暘嶼偵傛傞捈慄偺曽掱幃傪摼傞丅>br>
掕棟55丂擟堄偺1捈慄忋偵偁傞揰偺嵗昗乮x,y)偼偮偹偵丄ax+by+c=0偺慄暘曽掱幃傪枮懌偡傞丅媡偵忋偺偛偲偒惈幙傪桳偡傞擟堄偺侾師曽掱幃偼忢偵慄暘嶼偺婎慴偵偁傞暯柺婔壗妛偺捈慄偱偁傞丅乮忔朄偺岎姺棩偼惉傝棫偨側偄丅ax偼xa偲摨偠偱偼側偄乯
忔朄偺岎姺棩偲楢懕偺彅掕棟傪彍偔偡傋偰偺婯懃偑惉棫偡傞堦偮偺暋慺宯傪丄乽僨僓儖僌悢宯乿偲偄偆丅
僨僓儖僌偺掕棟乮掕棟53乯偼岞棟嘥寢崌丄岞棟嘦弴彉丄嘩*嫹媊偺暯峴偡側傢偪嬻娫偺岞棟傪梡偄偰丄嘨崌摨偺岞棟傪捛壛偡傞偙偲側偔徹柧偱偒傞丅僷僗僇儖偺掕棟乮掕棟40乯傕棫懱岞棟傪晅壛偡傟偽崌摨偺岞棟側偟偵徹柧偟偆傞偺偐偲偄偆栤戣偑偁傞丅偲偙傠偑僷僗僇儖偺掕棟偼僨僓儖僌偺掕棟偲堎側傝丄傾儖僉儊僨僗偺楢懕岞棟偑寛掕揑偵廳梫偵側傞丅偙偙偱傾儖僉儊僨僗偺岞棟傪尵偄側偍偡丅
嘪1*乮慄暘嶼偺傾儖僉儊僨僗偺岞棟乯丗丂1捈慄倗偺忋偵慄暘a偲2揰A,B偑梌偊傜傟偰偄傞偲偡傞丄桳尷屄偺揰A1,A2,A3丒丒丒,An-1,An傪尒弌偟丄B偑A偲An偲偺娫偵嵼傝丄偐偮怴慄暘嶼偺堄枴偵偍偄偰丄慄暘AA1,A1A2,丒丒丒An-1An傪a偵摍偟偔偡傞偙偲偑偱偒傞丅
掕棟57丗掕棟40偺僷僗僇儖偺掕棟偼岞棟嘥丆嘦丄嘩*丄嘪1偵婎偯偄偰丄偡側傢偪崌摨掕棟傪彍奜偟偰丄傾儖僉儊僨僗偺岞棟傪梡偄偰徹柧壜擻偱偁傞丅
掕棟58丗僷僗僇儖偺掕棟偼岞棟嘥丆嘦丄嘩*偵婎偯偄偰偼丄偡側傢偪崌摨岞棟偲傾儖僉儊僨僗偺岞棟傪彍偄偰偼徹柧晄壜擻偱偁傞丅
掕棟57偲58偺徹柧偼嶼弍偺墘嶼朄懃偺憡屳娭學偵婎偯偄偰偄傞丅傾儖僉儊僨僗悢宯偵偍偄偰偼掕棟59偵傛傝丄嶼朄偺岎姺棩偑惉棫偡傞乮ab=ba)丅旕傾儖僉儊僨僗悢宯偵懳偟偰偼掕棟60傛傝忣曬偺岎姺棩偼摉慠偺婣寢偱偼側偄丅僨僓儖僌悢宯偼忔朄偺岎姺棩偲楢懕偺岞棟傪彍偄偰惉棫偡傞暋慺悢宯偱偁傞丅掕棟57偼忔朄偺岎姺棩偼僷僗僇儖偺掕棟40偵懠側傜側偄偙偲傪尵偭偰偄傞丅僨僓儖僌悢宯兌(s,t)偱偼忔朄偺岎姺棩偼惉棫偟側偄偺偱丄偙傟傪旕僷僗僇儖婔壗妛偲偄偆丅旕僷僗僇儖婔壗妛偼偡側傢偪旕傾儖僉儊僨僗婔壗妛偱偁傞丅掕棟61偵傛傝丄僨僓儖僌偺掕棟乮掕棟53乯偼崌摨岞棟嘨偍傛傃楢懕岞棟嘪1傪梡偄傞偙偲側偔丄僷僗僇儖偺掕棟乮掕棟40乯偐傜徹柧偡傞偙偲偑偱偒傞丅