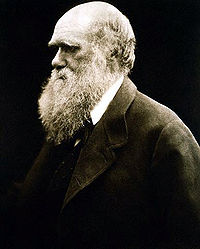
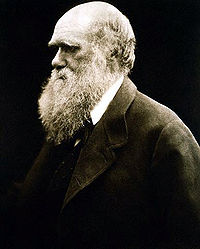
今年2009年はダーウィン生誕200年にあたる。そこで本書に入る前に、蛇足だとは思うが少しビーグル号航海にでるまでのダーウィンや生物学の進化論についておさらいをしておこう。チャールズ・ロバート・ダーウィン(1809年2月12日 - 1882年4月19日)はイギリスの自然科学者。 全ての生物種が共通の祖先から長い時間をかけて、彼が自然選択と呼んだプロセスを通して進化したことを明らかにした。自然選択の理論が進化の主要な原動力と見なされるようになったのは半世紀後の1930年代であり、自然選択説は現在では進化生物学の基盤の一つである。また彼の科学的な発見は生物多様性に一貫した理論的説明を与え、現代生物学の基盤をなしている。16歳(1825年)の時に父の医業を助けるため親元を離れエディンバラ大学で医学を学ぶが、挫折し興味を失う。博物学・植物学を学び当時ヨーロッパで最大のコレクションを誇ったエジンバラ大学博物館で研究を手伝った。父はダーウィンを牧師とするために1827年にケンブリッジ大学クライスト・カレッジに入れ、神学や古典、数学を学ばせた。神学の権威ウィリアム・ペイリーの『自然神学』を読み、デザイン論(全ての生物は神が天地創造の時点で完璧な形でデザインしたとする説)に納得し信じた。1831年にケンブリッジ大学を卒業すると、恩師ヘンズローの紹介で、同年末にイギリス海軍の測量船ビーグル号に乗船することになった。ロバート・フィッツロイ艦長の会話相手のための客人としての参加だった。ビーグル号乗船後は本書の受け持ち範囲である。
進化論とは、生物の進化に関する科学的理論の体系のこと。生物が不変のものではなく長期間かけて次第に変化してきたという考えに基づいて、現在見られる様々な生物は全てその過程のなかで生まれてきたことを説明する。進化が起こっているということを認める判断と、進化のメカニズムを説明する理論という2つの意味がある。現代的な進化論は単一の理論ではない。それは適応、種分化、遺伝的浮動など進化の様々な現象を説明し予測する多くの理論の総称である。生物で言う進化には、進歩する、前進する、より良くなるなどの意味はない。現代の進化理論では、「生物の遺伝的形質が世代を経る中で変化していく現象」だと考えられている。進化は実証の難しい現象であるが、生物学のあらゆる分野から進化を裏付ける証拠が提出されている。人文社会学や宗教の分野においては議論があるが、自然科学の内部では進化が事実であるかどうかの議論はない。本書は紙面の関係で「性選択説」は取り上げない。また本書は自然哲学の本であるため、ダーウィンの生物学に限定しており、人文科学的に面白い話題である社会思想への影響、なかでも 優生学や 社会ダーウィニズムはダーウィンの責任ではないので取り上げない。
進化論は19世紀のイギリスで誕生した。ダーウィン以前の進化論を見ると、1830年から33年にかけてチャールズ・ライエルは『地質学原理』を著し、激変説の代替理論として斉一説を提唱した。ライエルは実際の地層は天変地異よりも、現在観察されているような穏やかな変化が非常に長い時間積み重なって起きたと考える方が上手く説明できると論じた。ライエルは進化に反対したが、彼の斉一説と膨大な地球の年齢という概念はチャールズ・ダーウィンら以降の進化思想家に強く影響した。
ジャン=バティスト・ラマルクは、最初は生物が進化するという考えを認めていなかったが、無脊椎動物の分類の研究を進めるうち、19世紀になって、生物は物質から自然発生によって生じると考え、著書『動物哲学』で進化の考えを発表した。ラマルクの仮説は科学的手続きによって検証される最初の進化論であり、ラマルクは進化のしくみについて、使用・不使用によって器官は発達もしくは退化し、そういった獲得形質が遺伝する。従って非常に長い時間を経たならば、それは生物の構造を変化させる、つまり進化すると考えた。ラマルクのこの説を用不用説と呼ぶが、生物にとって適切な形質が進化するという意味では適応説と考えてよい。彼は、進化は常に単純な生物から複雑な生物へと発展していくような、一定の方向をもつ必然的で目的論的な過程だと考えた。
1844年にスコットランドの出版業者ロバート・チェンバースは匿名で『創造の自然史の痕跡』を出版した。これは幅広い関心と激しい論争を引き起こした。この本は太陽系と地球の生命の進化を提案した。彼は化石記録が人間に繋がる上昇を示しており、他の動物は主流を外れた枝だと論じた。進化が定められた法則の発現であるとする点でグラントのより過激な唯物論より穏やかであったが。人間を他の動物と結び付けたことは多くの保守派を激怒させた。『痕跡』に関する公的な議論は進歩的進化観を含んでおり、これはダーウィンの認識に強く影響した。
本書に入る前に最後に、著者内井惣七氏のプロフィールを紹介する。内井 惣七(1943年香川県高松市生まれ )氏は、日本の哲学者(科学哲学)・科学史家である。京都大学名誉教授。Ph.D.(ミシガン大学、1971年)。京都大学工学部卒業後文学部学部入学という回り道をした。大阪市立大学を経て1990年京都大学教授に就任、2006年定年退職した。主な著書に「科学哲学入門」、「進化論と倫理学」(世界思想社)、「アインシュタインの思考を辿る」(ミネルヴァ書房)、「空間の謎・時間の謎」(中公新書)などがある。内井氏のウェブサイトには、[Uchii Index]、[Uchii's Sites]がある。著者は理系から文系に転じた「科学哲学者」あるいは「科学史家」であり、本書で「ダーウィンの思想の本質に迫る」のが目標であるという。そしてその手法はチャールズ・ライエルの「地質学原理」に導かれて自然淘汰説にいたる思想形成に先ず着目する。そしてその自然淘汰説の同時発見者ウォーレスとの決定的的な違いを「種の起源」を精読して「分岐の原理」に求めた。これは多様性が生存に適するということである。そしてダーウィンの道徳起源説である「人間の由来」において、人間と動物を連続的に扱おうとしたダーウィンの姿勢に著者は感銘するのである。今では常識に属することであるが、「人間のみが持つ意識や道徳も動物社会から説明できる」とするダーウィンがすごい。
1) ビーグル号航海から「自然淘汰説」まで(1831-1858年)ダーウィンがビーグル号で南米への航海に出たのは1831年12月であった。ダーウィンは地質学や博物学の学徒としてイギリス海軍ロバート・フィッツロイ艦長のお話し相手として乗り込んだ。フィッツロイ艦長よりチャールズ・ライエル著「地質学原理」をプレゼントされ、航海中はこの本を勉強して諸島の実地調査を行い博物学者としての地位を固めたようだ。「地質学原理」の正式タイトルは「地質学の諸原理、地球の表面における過去の変化を、現在活動している原因によって説明する試み」という。過去も現在も支配する地質学の原理は同じだという「斉一説」で、ノアの箱舟のような「神の意図」や全く違った原理だ働いたとする「激変説」を排するのである。ライエルの地質学における3つの方法論とは①自然の基本法則恥館を通じて不変、②現在見るべき原因によって地質学変化を説明、③今も昔もその原因の強さは変わらないとするものであった。ライエルの「地質学原理」第2卷はラマルクの進化論批判である。ここにいう進化論批判とは「進歩説批判」であった。進歩説(プログレッショニズム)とは「より単純な生物がより複雑な生物で置き換えられるとか、断絶ごとに新たな生物が創造される」という意味で、進化論は「種がかわってゆく」ということで、当時は「転成説」といわれた。ラマルクは進歩説に転成説を持ち込み、ある種が次の時代に進歩した別の種で置き換えられるというだけでなく、下等な種が高等な種へと連続的に変化するという主張をした。キリンの首が長くなった原因を「用・不用説」とか「獲得形質の遺伝」で説明した。ライエルは「或る動植物が徐々に絶滅し,新しい種が次々に導入される」ということは自然の規則的で定常的な秩序であるといい、すでに「種の起源」の問題まで提起していた。ダーウィンはガラパゴス諸島で種の安定性に疑問を抱き資料を集めたが、動物学資料を不注意で捨てるなどミスが目立った。地質学上の興味が主で、動植物学はまだ専門外であった。
ダーウィンがビーグル号航海から帰国したのは5年後の1836年の事であった。ビーグル号航海時から帰国後1938年までに書きとめた「ノートブック」はA-Nまで整理されている。これらのノートがダーウィンの思想形成に重要な位置を占める。ダーウィンはマルサスの「人口論」を読んで自然淘汰説のヒントを得たという証拠がノートに記されている。生存に食糧などの圧力がかかるという「人口論」は生き残る者と死ぬ者との比率、つまり生存率の差が適応を生むのではないかという第一の発見に繋がった。生存に有利な形質を備えた種が長い間に多数を占める。これが種の変化を支配する法則だという姿が見えた。ダーウィンはマルサスの「人口論」を読んで、さらに道徳感覚を学んだという。「ミツバチの巣がミツバチの本能なしでは存続できないように、社会は道徳感覚がなければ存続し得ない」という「人間の由来」に発展する第二の発見である。ダーウィンは「ノートブック」の仕事が一段落した後、ついに「種の起源」の素描に入る。それが1842年の「スケッチ」と呼ばれる40ページ足らずの鉛筆書きの手稿である。そして2年後1844年まとまった「エッセイ」という原稿が書かれた。一人の超絶者を仮定して、生物界を支配する進化の法則を一気に演繹的に記述することで理論の大まかな全体像を得た。これを著者は「ダーウィンのデモン」と呼ぶ。ここでダーウィンのデモンは選択(淘汰)をするのである。選択の要素は偶然で生まれたものであっても、選択が積み重ねられた結果一定の方向に向かう。ここがミソだ。擬人化が好ましくないなら、「ダーウィンのデモン」とは自然そのもののことである。1844年進化説を説くロバート・チェインバーズの著作「創造の自然史の痕跡」という匿名の本がダーウィンを驚愕させた。進化と発生段階の系列が相似するという説で、同じ発生過程のうちで適当な段階で横路にそれてそれ独自の進化を遂げれば、動物のすべての形態が生まれるくる。つまり種の転成(進化)の法則は、発生過程の法則から示唆されるという。かれは最初の生物から魚類、爬虫類、鳥類・・・哺乳類と進化してきた痕跡が胎児の発生過程にみられるとした。ダーウィンは同じことを考える人が居る事を知って驚愕した。「先を越された」という印象を持ったといわれる。さてこのころ「具体的な分類の仕事に携わった事がない人間には、種の問題を論じる資格はない」という友人フッカーの言葉に示唆されて、1846年から8年間、ダーウィンはフジツボとまん脚類の分類に深くたずさわわることになった。
2) 分岐の原理と「種の起源」(1859年)ダーウィンはフジツボの形態研究から性の分化の移行段階(本書では扱わない)を見出し、それは進化のシナリオに見事に合致するものであった。ところがダーウィンの背後に「自然淘汰」の同時発見者ウォレスがひたひたと迫っていた。ウォーレスは独学の生物学者でボルネオ島のサラワクで、1855年「新種の導入を規制してきた法則について」という論文を書いた。ウォレスの「サラワクの法則」というのは「あらゆる種はそれに先立って存在してきた近縁種と、空間的にも時間的にも重なり合って出現した」という。これはライエルの「地質学の原理」と一致するので、ライエルの弟子ダーウィンは自分と全く同じ発想をしている人間の存在に気が付いた。ウォレスの論文の要点は、①網や目といった大きな分類グループは地球上に広く分布するが、科や属はしばしば限定された地域に限られる。②広く分布する科に属する属はたいてい分布範囲は限定され、広く分布する属の中で目立った特徴を持つ種はそれぞれの地域に特有である。③近縁の種は近接する地域にも見出される。④物理的に隔てられた2つの地域では同じような気候であれば、対応する科、属、種が見られる。⑤生物の時間的分布は、現在の空間的分布と良く似ている。⑥大きなグループは殆ど地質年代を通じて存在し、小さなグループもいくつかは存在する。 ⑦各地質年代に特有なグループが存在する。⑧同じ地質年代の種或いは属は近縁である。⑨「サラワクの法則」 以上の証拠付きの所見はダーウィンのスケッチやエッセイに極めてよく似ていた。この法則によってウォレスは「真の分類体系の形式」が定まるとして、樹状系統分類図(現在では遺伝子類似性から系統図の枝分かれが論じられるほど真理である)を提唱した。ダーウィンの師ライエルがウォレスの論文を読んだのは1985年11月ごろで、ダーウィンに面会をして「急がないと先を越される」と警告をしたといわれる。
どちらが先に自然淘汰の説を発表したかは本書では詮索しないが、1958年7月1日ウォレスとの同時発表論文を書いたといわれる。著者はダーウィンのオリジナリティを「分岐の原理」に置いているが、その言葉が始めて出てきたのは1857年8月のフッカー宛の手紙である。そしてダーウィンは1859年「種の起源」を著わした。ダーウィンの「種の分岐」にはいる前に、ウォレスの「テルテナ論文」で種の分岐がどのように扱われているかを見ておこう。テルテナ論文の題名は「変種が元のタイプから限りなく離れてゆく傾向性」というものである。ウォレスは生物の自然状態が不断の生存競争である事を論証し、あくまで自然淘汰が統計的な原理で、個体差と環境条件の適応関係において長い目で個体数が決定されるとした。一つの変種が新しい種に移行するためには、環境の変化が必要であるとしたことが重要である。ここまでのウォレスの分岐の原理はダーウィンと同じである。すなわち「自然淘汰の作用による異なる環境への適応」という。しかしダーウィンは一歩進んで「もし変種がが本当の種にまで移行するには、差異の拡大は自然界では常に起こっていなければならない」とした。環境の変化だけでなく、環境の変化がなくとも分岐を進ませるよう因果必要だというのだ。分岐の原理によるダーウィンの定式化はこうだ。「ある種から生まれた変種の子孫が、その構造、体質、習性において多様に分岐していればいるほど、かれらは自然界でより多く大きく異なった場所を占めることができ、それによって個体数を増やすことが出来る」 そこが決定的にウォレスと違う。
1861年ダーウィンはランの研究に没頭する。昔からランは形や色の多様性が好まれ栽培種の王様である。自然淘汰の過程は、ランダムな変異をふるいにかけ,ある器官が特別な目的のために設計されたかの様に見事な機能を果たすことが出来る。こうして生物学的な「目的」、「機能」そして「設計」という、普通は目的論的に理解される諸概念が自然淘汰説の中で意味づけされれば、神はいらないのである。ランの形態という詳細は省くが、蜜を吸いに来る虫による他家受粉のために発達した器官の摩訶不思議をダーウィンが徹底して研究した。因果的な過程で説明できれば、目的論は入り込む余地はない。このような変化と新たな適応の達成を成し遂げるメカニズムは自然淘汰しかない。
3) 動物と人間の連続と「人間の由来」(1871年)ダーウィンは晩年の大著「人間の由来」で、進化論を人間に適用し、道徳という社会性の起源と、性分化による種の進化を論じた。1863年師ライエルは「人間の古さ」という古人類学の著書を発表し、人間は特別な位置にあるといった。また人間の進化を研究していたウォレスは1869年「人間の進化には自然淘汰は及ばない」と主張し始めた。これを契機にダーウィンは1838年ノートブックに示した「ミツバチと同様に、人間社会は道徳感覚がないと存続し得ない」という長年の難しい問題に結論を出さざるを得なかった。人間の絶対性、霊性、神の存在はこの問題の克服なしには突破できないからだ。つまり人間と動物は連続しており、人間は動物であると云う今では当たり前の原理を証明することである。「人間の由来」の第1章で「人間がより下等な生物から由来した証拠」と題して、①他の動物の身体的類似性、②発生学から胎児の発達や成長過程に見られる事実、③いろいろな痕跡器官・構造をあげる。そして第2章では「動物と人間の心的能力」と題して、人間の聖域とみなされてきた霊性について「人間と高等哺乳類との間には、心的能力において根本的な違いはない」ことを証明する。感情、好奇心、模倣能力、注意力、記憶力、想像力、知性といったことを網羅的に考察する。これらの課題は今日の脳科学の格好の研究テーマとなっている。詳細は省くがダーウインが行った戦略は素朴であるが、動物と人間の行動と性質を自覚すると明らかな相似性が見られる事例を積み重ねて経験的に裏付けることである。人間のみに備わっているとされる能力について吟味し「動物にも萌芽的な形で備わっている能力と人間の能力には超えがたいギャップはない」という。最後まで残ったのは人間の社会性である道徳性であった。第3章において「道徳感覚の起源」を考察した。ダーウィンは人間を動物界へ投げ返したのである。
道徳性の命題をダーウィンは次に定義した。①動物にも社会性がある。本能のほかに共感と奉仕が自分の所属する群の中に向けられる。②社会的本能と他の本能の間で葛藤が見られる。動物も衣食足りて礼節をしるのだ。③社会的規範と共感。言葉がなくとも共同の行動を気にかけ、共感を意識する。 ④習慣が社会的本能を強化する。ダーウィンは「仮想心理学」のように記述しているが、自然淘汰が長い間ふるいにかけ選別してゆく行動特性や心的特性のことを語っている。ダーウィンのシナリオが目標とするのは、最終的に道徳感覚や良心を備えた動物に進化するということである。利他行動を生き残り戦略から説明する「進化ゲーム理論」、懲罰や評判を気にする「進化心理学」、感情移入など高度な共感をとく「行動動物学」など、いまやサルの社会研究で有名な京大人文科学研究所の研究で花盛りである。とにかく人間と動物は連続するという観点が普遍的になったのはダーウィンの功績である。