
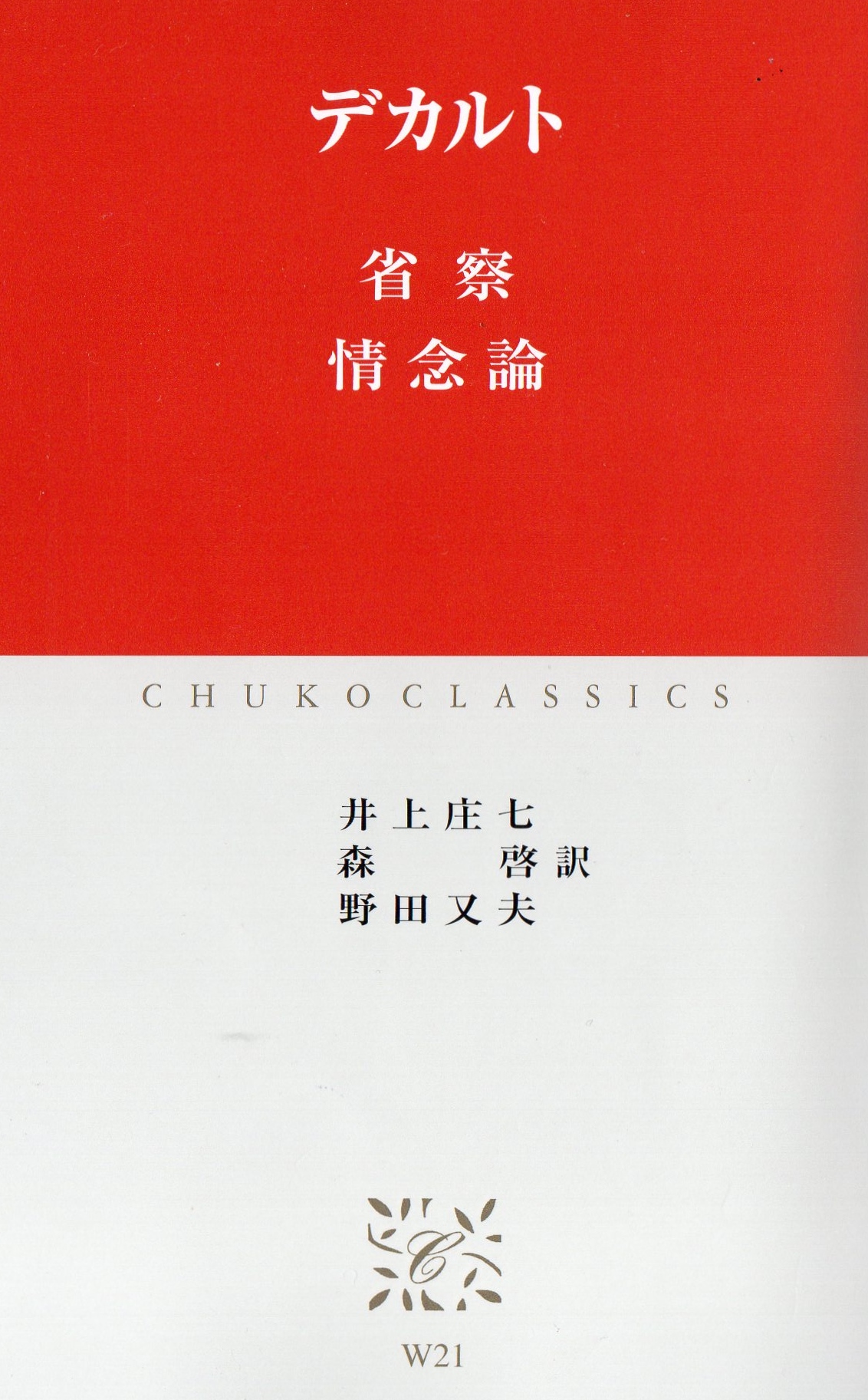
ルネ・デカルト 省察・情念論(中公クラシック)

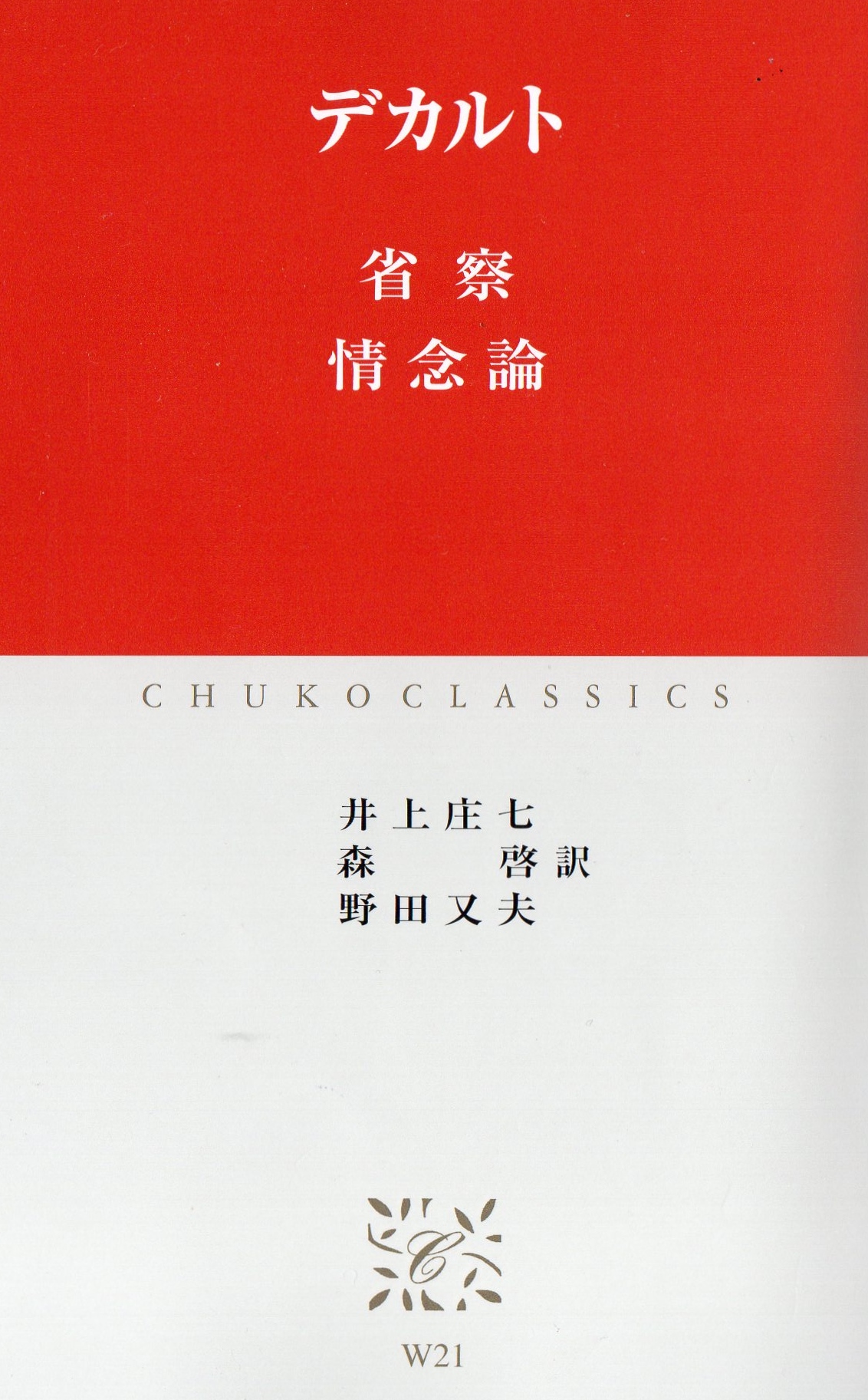
ルネ・デカルト 省察・情念論(中公クラシック)
今更言うまでもないことであるが、ルネ・デカルト(1596年3月31日 - 1650年2月11日)は、フランス生まれの哲学者、数学者である。合理主義哲学の祖であり、近世哲学の祖として知られる。本書「省察、情念論」に入る前に、デカルトの概要をおさらいしておこう。考える主体としての自己(精神)とその存在を定式化した「我思う、ゆえに我あり」は哲学史上でもっとも有名な命題の1つである。そしてこの命題は、当時の保守的思想であったスコラ哲学の教えであるところの「信仰」による真理の獲得ではなく、人間の持つ「理性」を用いて真理を探求していこうとする近代哲学の出発点を簡潔に表現している。デカルトが「近代哲学の父」と称される所以である。初めて哲学書として出版した著作『方法序説』(1637年)において、冒頭が「良識はこの世で最も公平に配分されているものである」という文で始まるため、思想の領域における人権宣言にも比される。また、当時学術的な論文はラテン語で書かれるのが通例であった中で、デカルトは『方法序説』を母語であるフランス語で書いた。その後のフランス文学が「明晰かつ判明」を指標とするようになったのは、デカルトの影響が大きいともいわれる。
レナトゥス・カルテシウスというラテン語名から、デカルト主義者はカルテジアンと呼ばれる。デカルトを代表する著作を以下に列記する。
① 1628年 『精神指導の規則』 未完の著作。デカルトの死後(1651年)公刊される。
② 1633年 『世界論』 ガリレオと同じく地動説を事実上認める内容を含んでいたため、実際には公刊取り止めとなる。デカルトの死後(1664年)公刊される。
③ 1637年 『方法論序説および3つの試論(屈折光学・気象学・幾何学)』 「みずからの理性を正しく導き、もろもろの学問において真理を探究するための方法」で、序説単独で読むときは「方法論序説」と呼ばれる。
④ 1641年 『省察』
⑤ 1644年 『哲学の原理』
⑥ 1648年 『人間論』 公刊はデカルトの死後(1664年)である。
⑦ 1649年 『情念論』
デカルトの思想の概要を述べよう。まず最初は哲学の体系である。『哲学の原理』の仏語訳者へあてた手紙の中に示されるように、哲学全体は一本の木に例えられ、根に形而上学、幹に自然学、枝に諸々のその他の学問が当てられ、そこには医学、機械学、道徳という果実が実り、哲学の成果は、枝に実る諸学問から得られる、と考えた。デカルトの哲学体系は人文学系の学問を含まない。これは、『方法序説』第一部にも明らかなように、デカルトが歴史学・文献学に興味を持たず、もっぱら数学・幾何学の研究によって得られた明晰判明さの概念の上にその体系を考えたことが原因として挙げられる。次に哲学の方法であるが、ものを学ぶためというよりも、教えることに向いていると思われた当時の論理学に替わる方法を求めた。そこで、もっとも単純な要素から始めてそれを演繹していけば最も複雑なものに達しうるという、還元主義的・数学的な考えを規範にして、以下の4つの規則を定めた。
① 明証的に真であると認めたもの以外、決して受け入れないこと。(明証)
② 考える問題を出来るだけ小さい部分にわけること。(分析)
③ 最も単純なものから始めて複雑なものに達すること。(総合)
④ 何も見落とさなかったか、全てを見直すこと。(枚挙 / 吟味)
哲学の根に相当する形而上学であるが、方法論的懐疑から「コギト・エルゴ・スム」という命題を見出し、神の存在証明に及んだ。そしてデカルト主義の二元論である心身合一の問題に一つの矛盾に突き当たるのである。方法的懐疑についてであるが、幼児の時から無批判に受け入れてきた先入観を排除し、真理に至るために、一旦全てのものをデカルトは疑う。
この方法的懐疑の特徴として、2点挙げられる。1つ目は懐疑を抱くことに本人が意識的・仮定的であること、2つ目は一度でも惑いが生じたものならば、すなわち少しでも疑わしければ、それを完全に排除することである。つまり、方法的懐疑とは、積極的懐疑のことである。この強力な方法的懐疑は、もう何も確実であるといえるものはないと思えるところまで続けられる。まず、肉体の与える感覚(外部感覚)は、しばしば間違うので偽とされる。また、「痛い」「甘い」といった内部感覚や「自分が目覚めている」といった自覚すら、覚醒と睡眠を判断する指標は何もないことから偽とされる。この方法的懐疑の特徴は、当時の哲学者としてはほとんど初めて、「表象」と「外在」の不一致を疑ったことにある。方法的懐疑を経て、肉体を含む全ての外的事物が懐疑にかけられ、純化された精神だけが残り、デカルトは、「私がこのように“全ては偽である”と考えている間、その私自身はなにものかでなければならない」、これだけは真であるといえる絶対確実なことを発見する。これが「私は考える、ゆえに私はある」である。ラテン語ではコギト・エルゴ・スム と呼ばれる。コギト・エルゴ・スムは、方法的懐疑を経て「考える」たびに成立する。そして、「我思う、故に我あり」という命題が明晰かつ判明に知られるものであることから、その条件を真理を判定する一般規則として立てて、「自己の精神に明晰かつ判明に認知されるところのものは真である」と設定する(明晰判明の規則)。神の存在証明では、欺く神 ・ 悪い霊を否定し、誠実な神を見出すために、デカルトは神の存在証明を行う。
第一証明 - 意識の中における神の観念の無限な表現的実在性(観念の表現する実在性)は、対応する形相的実在性(現実的実在性)を必然的に導く。我々の知は常に有限であって間違いを犯すが、この「有限」であるということを知るためには、まさに「無限」の観念があらかじめ与えられていなければならない。
第二証明 - 継続して存在するためには、その存在を保持する力が必要であり、それは神をおいて他にない。
第三証明 - 完全な神の観念は、そのうちに存在を含む。(アンセルムス以来の証明)
このような「神」は、デカルトの思想にとってとりわけ都合のよいものである。ブレーズ・パスカルはこの事実を指摘し、『パンセ』の中で「デカルトの神は単に科学上の条件の一部であって、主体的に出会う信仰対象ではないと批判した。
物体の本質と存在の説明も、デカルト的な自然観を適用するための準備として不可欠である。三次元の空間の中で確保される性質(幅・奥行き・高さ)、すなわち「延長」こそ物体の本質であり、これは解析幾何学的手法によって把捉される。一方、物体に関わる感覚的条件(熱い、甘いetc.)は物体が感覚器官を触発することによって与えられる。なにものかが与えられるためには、与えるものがまずもって存在しなければならないから、物体は存在することが確認される。しかし、存在するからといって、方法的懐疑によって一旦退けられた感覚によってその本質を理解することはできない。純粋な数学・幾何学的な知のみが外在としての物体と対応する。このことから、後述する機械論的世界観が生まれる。1643年5月の公女エリーザベトからの書簡において、デカルトは、自身の哲学において実在的に区別される心(精神)と体(延長)が、どのようにして相互作用を起こしうるのか、という質問を受ける。この質問は、心身の厳格な区別を説くデカルトに対する、本質的な、核心をついた質問で「心身合一の問題」と呼ばれる。デカルトは情念はどのように生じ、どうすれば統御できるのか、というエリーザベトの問いに答える著作に取り組んだ。それは1649年の『情念論』として結実することになる。『情念論』において、デカルトは人間を精神と身体とが分かち難く結びついている存在として捉えた。心(精神)と身体を結ぶのは現医学では神経系であるが、デカルトは古い医学を採用し結び目は脳の奥の松果腺において顕著であり、その腺を精神が動かす(能動)、もしくは動物精気によって動かされる(受動)ことによって、精神と身体が相互作用を起こす、と考えた。デカルトが(能動としての)精神と(受動としての)身体との間に相互作用を認めたことと、一方で精神と身体の区別を立てていることは、論理の上で、矛盾を犯している。後の合理主義哲学者(スピノザ、ライプニッツ)らはこの二元論の難点を理論的に克服することを試みた。哲学の幹に相当するのが自然学である。デカルトは、物体の基本的な運動は、直線運動であること、動いている物体は、抵抗がない限り動き続けること(慣性の法則)、一定の運動量が宇宙全体で保存されること(運動量保存則)など、(神によって保持される)法則によって粒子の運動が確定されるとした。この考えは、精神に物体的な風や光を、宇宙に生命を見たルネサンス期の哲学者の感覚的・物活論的世界観とは全く違っており、力学的な法則の支配する客観的世界観を見出した点で重要である。更にデカルトは、見出した物理法則を『世界論』(宇宙論)において宇宙全体にも適用し、粒子の渦状の運動として宇宙の創生を説く渦動説を唱えた。ニュートンの万有引力にはまだ気が付いていないので、デカルトはガリレオとニュートmmを結ぶ科学史上の位置に置かれる。数学の分野では、2つの実数によって平面上の点の位置(座標)を表すという方法は、デカルトによって発明され、『方法序説』の中で初めて用いられた。この座標はデカルト座標と呼ばれ、デカルト座標の入った平面をデカルト平面という。デカルト座標、デカルト平面によって、後の解析幾何学の発展の基礎が築かれた。
「デカルトの概略年譜」
1596年 中部フランスの西側にあるアンドル=エ=ロワール県のラ・エーに生まれた。父はブルターニュの高等法院評定官であった。母からは、空咳と青白い顔色を受け継ぎ、診察した医者たちからは、夭折を宣告された。母は病弱で、デカルトを生んだ後13ヶ月で亡くなる。母を失ったデカルトは、祖母と乳母に育てられる。
1606年 10歳のとき、イエズス会のラ・フレーシュ学院に入学する。中でもフランス王アンリ4世自身が邸宅を提供したラ・フレーシュ学院は、1604年に創立され、優秀な教師、生徒が集められていた。デカルトは学院において従順で優秀な生徒であり、教えられる学問(論理学・形而上学・自然学)だけでなく占星術や魔術など秘術の類(たぐい)のものも含めて多くの書物を読んだ。そして、学問の中ではとりわけ数学を好んだ。
1614年 18歳で学院を卒業する。その後ポワティエ大学に進み、法学・医学を修めた。1616年 20歳のとき、法学士の学位を受けて卒業する。この後2年間は、自由気ままに生活したと考えられる。
1619年4月 三十年戦争が起こったことを聞いたデカルトは、この戦いに参加するためにドイツへと旅立つ。フランクフルトでの皇帝フェルディナント2世の戴冠式に列席し、バイエルン公マクシミリアン1世の軍隊に入る。
1619年10月 自分自身の生きる道を見つけようとウルム市近郊の村の炉部屋にこもる。そして11月10日の昼間に、「驚くべき学問の基礎」を発見し、夜に3つの神秘的な夢をみる。
1623年から1625年にかけて、ヴェネツィア、ローマを渡り歩く。旅を終えたデカルトはパリにしばらく住む。その間に、メルセンヌを中心として、亡命中のホッブズ、ピエール・ガッサンディなどの哲学者や、その他さまざまな学者と交友を深める。そして教皇使節ド・バニュの屋敷での集まりにおいて、彼は初めて公衆の面前で自分の哲学についての構想を明らかにすることになる。
1628年 オランダ移住直前に、『精神指導の規則』をラテン語で書く。未完である。
1628年 オランダに移住する。その理由は、この国が八十年戦争でも安定し繁栄した国で、不便なく「孤独な隠れた生活」を送ることができるためであった。32歳のデカルトは、自己の使命を自覚して本格的に哲学にとりかかる。この頃に書かれたのが『世界論』(『宇宙論』)である。1633年にガリレイが地動説を唱えたのに対して、ローマの異端審問所が審問、そして地動説の破棄を求めた事件が起こる。これを知ったデカルトは、『世界論』の公刊を断念した。
1641年 デカルト45歳のとき、パリで『省察』を公刊する。この『省察』には、公刊前にホッブズ、ガッサンディなどに原稿を渡して反論をもらっておき、それに対しての再反論をあらかじめ付した。『省察』公刊に前後してデカルトの評判は高まる。その一方で、この年の暮れからユトレヒト大学の神学教授ヴォエティウスによって「無神論を広める思想家」として非難を受け始める。
1643年5月 プファルツ公女エリーザベト(プファルツ選帝侯フリードリヒ5世の長女)との書簡のやりとりを始め、これはデカルトの死まで続く。エリーザベトの指摘により、心身問題についてデカルトは興味を持ち始める。
1644年 『哲学原理』を公刊する。
1645年 ヴォエティウスとデカルトの争いを沈静化させるために、ユトレヒト市はデカルト哲学に関する出版・論議を一切禁じる。
1649年 『情念論』を公刊する。
1649年 スウェーデン女王クリスティーナから招きの親書を3度受け取る。そして、4月にはスウェーデンの海軍提督が軍艦をもって迎えにきた。女王が冬を避けるように伝えたにも関わらず、デカルトは9月に出発し、10月にはストックホルムへ到着した。
1650年1月 女王のために朝5時からの講義を行う。朝寝の習慣があるデカルトには辛い毎日だった。2月にデカルトは風邪をこじらせて肺炎を併発し、死去した。デカルトの遺体はスウェーデンで埋葬されたが、1666年にフランスのパリ市内のサント=ジュヌヴィエーヴ修道院に移され、その後、フランス革命の動乱を経て、1792年にサン・ジェルマン・デ・プレ教会に移された。
「方法論序説」(谷川多佳子訳 岩波文庫1997年)
「方法序説」は1637年(デカルト41歳)のとき、無署名で出版した本「理性を正しく導き、学問において真理を探究するための方法序説、加えてその方法の試みである屈折光学、気象学、幾何学」という、全体で500頁を越える大著の最初の78頁(この岩波文庫本で約100頁)が「方法論序説」である。つまり3つの科学論文の短い序文という位置づけである。デカルトがなぜ著者名なしで出版したかというと、ガリレオが法王庁宗教裁判所で異端判決を受けたばかりで、ガリレオを尊敬していたデカルトは筆禍の難を遁れるため無署名で出版し、同じく「世界論」という書物を書き終えていたが、生前は出版を見送ったといういきさつがある。デカルトの「方法論序説」にはその第5部に「世界論」のエッセンスが示されているので、大きな危険性を孕んでいたというべきであろう。また本書はラテン語ではなくフランス語で書かれ、学術書ではなく一般教養書として出版した。本書の序にデカルトが内容の概要を語っている。100頁ほどの「方法序説」を6部に分けて、
第1部は、学校で学んだ人文学やスコラ学などの諸学問を検討し、それらが不確実で人生に役立つものではないことが確認されたという。学校を卒業後書物を捨て旅に出るまでのことを述べている。
第2部は、ドイツにおいて思索を重ね、学問あるいは自分お思想の改革の為の方法が4つの規則として提示される。すなわち、①明証、②分析、③総合、④演繹である。これらの規則は数学の難問を解く際に効力を発揮し、自然学の諸問題にも有効で、数世紀先のことかもしれないが諸学問の普遍的な方法になりうることが期待できる。
第3部は、真理の全体は把握できな状態でも人として守るべき行動の原理、すなわち道徳の諸問題についてである。3つの規則として述べられている。ストア派の道徳は暫定的な仮のものとして位置づけているが、デカルトは道徳の問題をこれ以上発展させることはしなかった。
第4部は、形而上学の基礎である。方法的懐疑をへて、「精神としての私」、「神」、「外界の存在」を示し、哲学史上有名な「コギトエルゴスム」、心身二元論といった重要な概念が語られ、誤りなき最終真理としての神の存在の証明が述べられる。
第5部は、公刊することができなかった「世界論」のエッセンスが述べられている。宇宙や自然の現象、機械的な人体論として心臓と循環器系の説明(今では間違いであるが)、動物と人間の本質的な違い(知性の存在)が論じられる。
第6部は、ガリレオ宗教裁判断罪事件に発するデカルトの心境がみられ、「世界論」の公刊を中止したいきさつとこの論文を後世に残す理由が語られる。学問の展望、人間を自然の支配者と見なす哲学、自然研究の意味を語る。
デカルトの歩みは慎重かつ確実である。学問の真理に至る道筋を、提示している。出発点は「私」であり、体系の基礎となる二元論、精神と神の形而上学、宇宙や自然、人体の見方が述べられた。当時例外的にフランス語で書かれたこの作品は、近代フランス精神の魁となった。普遍的な学問の方法、新しい科学や学問の基礎を示す広い意味での哲学の根本原理、自然学の展望と意味を述べた序説である。本書は、近代の意識や理性の原型、精神と物質(主体と客体)の二元論、数学を基礎とする自然研究の方法、科学研究の発展といったデカルト精神が近代合理主義の普遍的原理となった記念碑的作品である。
「哲学の原理―第1部形而上学」(山田弘明ら訳 ちくま学芸文庫2009年)
デカルトの「哲学原理」は全4部からなるが、本書は「人間的認識の原理について」と題する第1部の形而上学のマトメだけを対象としている。これまで刊行された訳書は第1部の形而上学と第2部の自然学を紹介し、第3部と第4部の自然学各論は省略する場合が多かった。本書がなぜ第1部だけなのか、その趣旨はスコラの形而上学との関連を捉えることであった。当時の優れたスコラ哲学の教科書は、ユスタッシュ・ド・サン・ポールの「弁証論、道徳論、自然学および形而上学にかかわる事柄についての哲学大全四部作」(1609年)が有名である。デカルトは明確にこのスコラ哲学大全を読んでおり、かつその形式を踏まえたうえで自身の著書「哲学原理」を書いたものと考えられる。デカルトはスコラ哲学から大きな影響を受けており、多くの点でスコラ哲学を痛烈に批判した。ニュートンはデカルトの「哲学原理」をよく読んでおり、デカルトの「哲学原理」も形而上学というよりも「形而上学に基づく自然哲学の原理」といった方が正しい。デカルトの「哲学原理」の狙いはスコラに代わる新自然学の体系的な展開にあったというべきであろう。「哲学原理」はラテン語で書かれ(本書はフランス語版を基にした)、全体は4部からなる。
第1部 「人間的認識の原理について」 思惟する精神は存在とは区別されるという第1原理ですべては演繹される。
第2部 「物質的事項の原理について」 自然を機械論的な展開と見る。運動量保存則など力学について述べた。
第3部 「可視的世界について」 地球と天体の運動を述べた。宇宙生成論(進化論)を提案した。
第4部 「地球について」 空気、燃焼、磁気など記述した。しかし今ではおかしな推論が多い。
第5部 「動物、植物の状態について」と第6部「人間の本性について」は予定されたのみで書かれなかった。
デカルト「哲学原理」第1部 形而上学「人間的認識の原理について」は第1から第76節に分けてある。ちくま学芸文庫の訳者らは本書の各節ごとを「訳文」、「解釈」、「参照」と3段構成とした。ちくま学芸文庫本の特徴は「解釈」でスコラ「哲学大全」との関連と、デカルトの言いたいことを述べ、ライプニッツの批判など多数の哲学者のコメントを記して理解を深める。「参照」では「哲学原理」の言葉が、他の書物1.「方法論序説」 2.「省察」 1641年 3.「真理の探究」 ではどう扱われているかを検証する。
本書、デカルト著「省察 情念論」(中公クラシック2002年)という本は次の4部からなる。①神野慧一郎著「デカルトの道徳論」(40頁) ②デカルト著「省察 第1-第5」(134頁) ③デカルト著「情念論 第1-第3部」(180頁) ④書簡集 (50頁)である。では各々について内容を検討してゆこう。
1)神野慧一郎著「デカルトの道徳論」「省察」の訳者は井上庄七氏、森啓氏であり、「情念論」と「書簡集」の訳者は野田又夫氏である。そしてこの総論あるいは解説とも言うべき本章を著したのは神野慧一郎氏である。この4名の共通点は京都大学文学部哲学科卒業ということである。生年は井上氏が1924年、森氏が1935年、野田氏が1910年で、神野氏は1932年である。神野慧一郎氏の専門は英国の経験論哲学者・歴史家ヒューム(1711-1776年)のモラリスト研究である。中公クラシックの本書を構成するのは、「省察」、「情念論」そしていくつかの書簡である。書簡はデカルトとエリザべトの間にかわされた書簡の一部である。デカルトからエリザべト王女へ2通、エリザべト王女からデカルトへ2通、デカルトからスウェーデンのフランス公使シャニュへの長い手紙1通である。そしてこれらの書簡や『省察』、『情念論』の著述がまとめられている意味は、本書全体がデカルトの道徳論を構成するからである。もちろん「省察」は彼の哲学の基本的枠組みすなわち形而上学を示すものであるが、道徳論を直接扱うものではない。「省察」で述べられていることは「心身分離」の二元論である。「心身分離」の説を一方の極に置き、対極にある「心身合一」の次元の道徳論をいかに解明するかが本書の狙いである。哲学の基本的課題は、真理とは何か、どのようにして知るかという認識論と、我々はこの世界においていかに生きるかという道徳論の二つが課題である。『方法論序説』は認識論であり、『情念論』は道徳論である。デカルトの哲学では認識と道徳は別のことではない。形而上学と道徳学が一つになって、いかに生きるべきか、正しい判断に意思を従わせるという課題が含まれているのである。デカルトは道徳論について纏まった著作を遺すことなく、スウェーデンに客死した。道徳論の骨組みは本書の書簡集に示されている。その道徳は『哲学の原理』完成後の考えであり、「決定的道徳」と考えられる。『省察』の形而上学から道徳論を論じるには、もうワンステップが必要でその準備段階に当たるのが『情念論』である。形而上学次元とは心身分離の次元であった。「考える自分」の存在を確かなものにした「コギト・エルゴ・スム」、つまりまず我々は精神として存在すことを示した。道徳の次元は日常的生の世界であり、自己と他人の存在が基本である。それゆえ道徳の次元は心身合一の次元である。『省察」において精神が存在することを示し、神の存在証明を経て、『省察』第6で外界の存在を証明する。そしてそれはデカルトの自然学に繋がる。彼の自然学は機械論的力学的宇宙論の形をとっており、『哲学の原理』に詳述されている。人間と「動物機械」を区別するものは、『方法論序説』では第1に理性的言語の使用であり、第2に理性的行動であると述べている。デカルトの形而上学において心身問題についての矛盾を指摘したのが王女エリザベトであった。形而上学的にはデカルトは心身の「実在的区別」を主張したが、日常的生において精神は「松果腺」(現代医学でも間違っている)において身体と一体化するという説を述べるに至っては、むしろ「身体合一」ではないかという疑問である。精神が物体と能動し受動することは『情念論』を導いた。デカルトは王女エリザベトの指摘に、問題があることを認めながら心身関係にはあまり重要視しなかった。それにはデカルトの時代背景とデカルト哲学の趣旨が絡んでおり、もう一つの哲学史家の問題が絡んでいた。デカルトにおいては、心身問題という次元より、良く生きるという道徳次元の問題が優先する、次元を異にする問題であった。この時代は情念論が流行していた。理性の時代と言われる17世紀以降において、情念について論じる哲学者は多くはない。ヒュームの「情念論」(人間本性論第2巻)やルソーくらいである。啓蒙の時代と言われる18世紀の哲学者の興味は理性やモラリスト的問題ではなく社会制度的問題(政治体制)に集中した。近代の哲学者が情念論を書いたホッブスやスピノザの例を無視する事からして、デカルトの情念論が無視されるのは不思議ではないそうだ。近代哲学史の流れで見るとデカルトは合理性を重視し情念を排除した哲学者ということになっている。17世紀の情念論は「人々の心を知る方法」(今でいえば心理学、人間行動学)として為政者の人心制御技術とみなされた。情念や情動はその強い力と気まぐれのため哲学者の扱うべき問題とは見られなかったようだ。17世紀初めフランスのモラリストの大物であったピエール・シャロンが『智恵について』を著わした。モンテーニュ-も情念の退治法を述べている。1643年6月28日のエリザべト王女への手紙で、デカルトは精神と知性、物質、身体合一の3つの次元があり、それは次元を異にした問題であると回答している。知性によって一度到達した形而上学的な結論は記憶や心情に留めて置けがいい、そして我々は日常的生の中に生きるべきだという。心身問題の論理的構造は4つの関係(①身体は物質的、②心は精神的、③心と身体は相互作用がある、④精神と物質は別のもの)にあり、全部同時に成立すると矛盾する。結局は今日の医学常識でいえば、大脳皮質の中枢神経系は精神(理性)を、情念は大脳周縁系神経を、知覚末梢神経は信号を大脳におくって身体的情報から画像判断や危険判断を行う。その立場で判断すればいいことでデカルト的二元論で立ち往生して苦しむ必要は全くないといえる。要するに全部が物質的で機能が異なるだけである。
これまでデカルトは道徳を論じた哲学者とは見なされず、専ら認識論と近代的自然観を確立した哲学者と考えられてきた。『哲学の原理』の序文でデカルトは「哲学は知恵の探求を意味する」と述べた。智恵は知識とは違い自分の知りうるあらゆることについての完全な知識(良く生きるという道徳を含む)をも指す。デカルトは学問の本来の目的はよい生き方をすることであるという。『方法論序説』における「暫定的道徳」の発想からもそれは明らかである。デカルトは若いころから読書よりも世間という大きな読書をすると宣言し、立派な行動人たらんと務めた。デカルトはストア派哲学を学んだが、デカルトとストオ派には違いも多い。ストア派は理性の行使が自然に従って生きることつまりよく生きることであった。デカルトは理性の使用とは方法論序説の到達点に従うことである。自然科学の成果は宇宙、医学と密接に関係し、デカルトは近代科学思想の祖と言われ。人間本性の理解が道徳論に大きく関係することは言うまでもないが、アリストテレスやスコラ哲学、ストア派哲学は、人間本性を「理性的」とする一面を強調するきらいがあった。デカルトの人間理解は理性だけでなく、感覚や知覚、情念をも日常的人間存在の中に入れ、心身の合一を認めることにより道徳論を展開した。心身の合一の次元こそ道徳の次元である。『情念論』は人間の情念や情動の生理学的基礎をあたえることに言葉を費やしている。デカルトの情念論は、人間の意識そのものを論及し、意識、中でも情念が我々の道徳的生の実質を為すと考えるのである。広い意味では情念とは我々の受動的意識のことであり、精神の意思の働き(能動的)でないものすべてを含むのである。情念や情動はさまざまな生理的状態によって引き起こされる「心の受容」である。外感(外部感覚)、内感(身体の内部感覚)、情念(受動的意識)と3つに分かたれる。脳における出来事と精神(心)に生じる意識をつなぐ場所がデカルトのいう「松果腺」である。動物精気(神経信号伝達)の制御の中心とデカルトは見なしている。我々は意識を直接的に制御していると思っているが、受動的な意識の働きは精神の直接的な制御下にはない。動物行動学と人間行動学の差異がここにある。すなわちアリストテレス的徳に行動学的、生理学的基礎を与えるものである。デカルトは『情念論』において、六つの基本的な情念を選んだ。「驚き」、「愛」、「憎しみ」、「欲望」、「喜び」、「悲しみ」である。『情念論』は三部から成り立っており、第一部では情念一般、第二部では六つの情念について、第三部は特殊情念の説明である。もっとも重要とされる「高邁(けだかさ)」である。第一部で我々の意識の底にある受動性を、知性と意思の能動性によって支配しようということである。デカルトはアリストテレス―スコラの情念論の必然性を排し、心中の矛盾と考えられるものを心と身体の働き合いとして客観的にみるべきだという。デカルトは魂が肉体の消滅後も残るということによってキリスト教的神学も満足させた。では心の能動性を高めるにはどうしたらいいかという問いには、真実に基づく決意すなわち真なる判断力であるという。エリザベト王女とデカルトの出会いは1642年であり、王女がデカルトに「心身関係の矛盾」の問いを発したのは1643年5月であった。本書に収められた二人の書簡は1945年のもので、道徳の問題に集中した交信であった。『情念』の出版は1649年であった。デカルトが己の進むべき道としたのは、もちろん真理探求そのものであったが、彼は自らの情念を真と偽に見分けることに集中した。デカルトは『情念論』の最終項に「人生の善と悪のすべては、ただ情念のみに依存する」といった。「実際的哲学、すなわち情念によって最も多く動かされる人が、この世において最も多くの楽しみを味わう」が彼の結論である。
2)「省察」本書の題名は「第一哲学についての 省察 神の存在および人間精神と身体との区別が証明される」がフルネームである。1641年に刊行された。本文に入る前に、ソルボンヌ大学神学部に宛てた献呈書簡、および「読者へのまえおき」が挿入されている。ソルボンヌ大学神学部に宛てた献呈書簡には、神についての問題と精神についての問題の二つは、神学によってよりは哲学によって論証されなければならないと宣言しています。神が存在するということは、宗教なき人々には自然的理性によってあらかじめ証明して見せなければならない。この書物によって、もはや世間には神の存在についても、人間の精神と身体との実在的な区別について、あえて疑問を差し挟む人はいなくなるでしょうと自信のほどを大学関係者に述べている。「読者へのまえおき」は省察の概要の紹介であるので、理解の助けとして紹介しておこう。1637年に公刊した『方法論序説』にたいする反論の一つは、「人間精神はその本性・本質がただ考えるものだけにある」ということに対し、他の何物も私の本質に属していないという帰結が分からない、もう一つの反論は私より完全なものの観念(神)を持つからと言って、私より完全であるという帰結が分からないということであった。そこで神と人間精神とについての問題を、そして第1哲学全体の基礎を論ずることが本書の目的とした。以下の六つの省察のあらましを述べる。
第1省察: 物質的なものへの疑いうる理由を示す。懐疑は我々から先入観から解放し、精神を感覚から切り離す道を開く。そうして我々が真であると見極めるものは、もはや疑いえないようにしてくれる。
第2省察: 懐疑する精神は確かに存在していることに気が付く。こうして知性的本性に属するものと、物体に属するものをたやすく区別するようになる。精神の不死問題は第1省察から帰結するものではないが、神によって創造された精神はその本性上不可滅である。人間の精神は偶有性からなっているものではなく、純粋な実体であることが分かる。こうして精神と物体は分離される。
第3省察: 神の存在を証明する。この上なく完全な存在者の観念は大きな表現的実在性を持つ。
第4省察: 我々が明晰に判明に認知できるものはすべて真であることが証明される。虚偽の根拠を説明した。そこで考察されるのは信仰あるいは実生活の事柄ではなく、認識的思弁的な心理のみである。
第5省察: 一般の理解される物体的本性が説明され、神の存在が論証される。幾何学など自然学の証明も神の確実性に依存する。
第6省察: 悟性の作用が想像力の作用と区別される。人間の精神は密接に身体と結ばれており、一体化していることが示される。同時に物質的事物の存在も結論される。神と精神の認識に導く根拠こそ、人間精神によって知られうるすべてのもののうち最も確実で最も明証的である。
省察1 「疑いをさしはさみ得るものについて」
デカルトは学問においていつか堅固でゆるぎないものを打ち立てようとするなら、一生に一度はすべてを根こそぎに覆し、最初の土台から新たに始めなければないと宣言する。これは近代哲学の幕開け宣言となった。ただすべてが偽であると証拠立てるもの必要はない、理性に問いかけて確実で疑う余地がないわけでなければ、明らかに偽と思うくらい用心してかかる必要がある。同意は差し控えるべきである。これを「方法論的懐疑」の態度という。自らに問うて怪しいところがあれば疑ってかかり、不用意に「真」とは見なさない慎重な態度という意味であろう。常識や錯覚によって、確かに感覚は我々をして誤らせることがある。覚醒と睡眠の境界も怪しい。夢を見ていたのかもしれないともいえる。一般的には身体的なことは幻ではなく真として存在する。これらに属するものは(大きさ、色、数、場所、時間など)、物体的本性一般と呼ぶ。そういう意味では自然学、物理学、医学その他は確かに疑わしいことが多いが、数学、幾何学等は単純ものしか取り扱わない。疑いをはさみ得るもの、偽であるものには決して同意はしないことを認識の第1前提としよう。
省察2 「人間の精神の本性について 精神は身体より容易に知られること」
アルキメデスは確固不動の一点があれば、地球でも動かして見せるといった。しかしそのような確固不動なものは地球上には何一つない。そこで私が見るものはすべて偽であると仮定しよう。私は身体や感覚器官にしっかり繋がれていて、それなしには存在しえない。すべてのことを余すことなく考えた末に「私は在る、私は存在する」と結論せざるを得ない。この命題は精神によって捉えるたびに必然的に真である。私の存在は身体によって支えられ、身体の活動の源は精神にあると考えた。自分を動かす力、感覚する力、あるいは考える力を持つということは、決して物体の本性に属することではない。精神に属することの本質は考えることである。私は考えること(疑い、理解し、肯定し、否定し、意志し、想像し、感覚する)以外の何物でもない。言い換えれば私とは精神、知性、悟性、理性に他ならない。想像力は物体的なことを思い描くことである。やはり人間精神無くしては物体をとらえることはできない。私が物体を見ることから、私自身も存在することは明らかである。本来、物体は感覚あるいは想像の力によって捉えられるものではなく、ただ理性によってのみ他と区別されて把握されるのである。物体は感覚で把握されるのではなく、専ら理解によって把握されるのである。
省察3 「神について 神は存在するということ」
私は考えるものであるということを、私は確信している。私が極めて明晰に認知するところのものはすべて真であるということを、一般的な規則として確立することができる。そもそも神というものがあるかどうかさえ十分には知られていない。私の意識のうちあるものは、ものの像であって観念という名で呼ばれている。神もそうである。私の意識は像の形以外にも、あるものは意思あるいは感情と呼ばれ。他のものは「判断」と呼ばれる。判断のうちに見いだされる誤りは、私のうちのある観念が私の外にある何者かに似ていると判断するところからきている。これら観念の真の起源は外来か生得か作為かを見極めてはいない。これらの観念が単に意識様態である限り、それら観念の間にいかなる差別も認めない。観念において表現されている実在性を「表現的実在性」をそれ自体に含んでいる。私が神を理解する観念(永遠、無限、全知、全能、創造者)は、有限な実体を表示する観念(形相的実在)よりも、はるかに多くのものを含んでいる。多くのものを実在性をそれ自体に含むものは、不完全なものからは生じない。私自身は観念の原因ではない、その神の観念の原因であるところの何か他のものもまた存在することが帰結される。私自身と物体的な事物と神についての観念から複合されたものである。物体的観念を構成しているすべての観念は私自身の観念から取り出された。残るはただ一つ神の観念だけは、私自身から出た者ではない。だから神は必然的に存在していると結論しなければならない。この神の観念は、それ自身によって真である観念、虚偽ではないかという疑いを免れている観念は無い。この観念はこの上なく明晰であり実在的で真であることを、また完全性を備えていることを私が明晰にかつ判明に認めるのである。有限者である私によっては把握できないということが、無限者の無限者たる所以である。私の存在は私自身から出たものではない。私の一生は無数に分解が可能で、各部分はいささかも関係していない。私が私とは違ったある存在に依存するということを、際めて明証的に認識できる。それとは反対に神のうちにあるすべてのものの統一性、単純性、不可分離性こそは、神のうちにあると理解する完全性の一つである。私が現にあるごとき本性のものとして存在すること、すなわち神の観念をわがうちに持つものとして存在することは、実際に神も存在するものでなくては不可能であると私は承認する。
省察4 「真と偽について」
精神を感覚から切り離すことによって、私の思惟を純粋な悟性(理性)の対象であるものに向けることができた。私が疑うということ、すなわち私が不完全で依存的な存在であることに注意すると、独立で完全な神の観念が明晰に浮かんでくる。神の観念を有する私が存在する。真なる神の観念から、その他のものの認識に至る道筋が見通すことができた。私のうちにある判断能力があることを経験するが、これは神から授かったものである。それにも関わらず私は誤謬に満ちた存在である。神と非存在の中間者なのであろう。神から得た判断能力が私においては無限ではなく不完全なのである。だからと言ってそんな私を作った神の存在を疑ってはならない。私の誤謬は認識能力と判断能力の不完全に由来するのである。理性の能力とは理解、記憶、想像のことでいずれも貧弱で限られている。ただ意思だけは自由であってこれこそ神の影像に似ているのである。意志の本質は肯定と否定、追求と忌避のところの自由のみに存在し、外力には決定されないのである。意思が悟性よりも広い範囲(正しく理解していない対象)に及ぼそうとするところに、私の誤謬が始まるのである。自由意志のこの正しくない使用法のうちにこそ、誤謬の形相すなわち欠如が内在する。理性(悟性)が有限である本質が原因である。考慮されるはずの事柄のすべてに明証的な知識に依存するやり方では、誤謬を防ぐことはできない。つまり判断を下すことは控えなくてはいけない。我々の誤謬と虚偽の原因を突き止めたことはこの省察の成果である。
省察5 「物質的事物の本質について 再び神は存在するということ」
物質的事物の存在を問う前に、意識の中にあるそれらの事物の観念を考察しなければならない。私は判明に形や量や数、運動を認識する。これらは私によって作り出された観念ではなく、真実な不変の本性を持っている。感覚の観念の中にあっても、形や量、算術、純粋に抽象的な数学に属する明証的な真理は、最も確実な真理だと認めていた。明証的にかつ判明に認知できるものが、実際そのものに属するならば、神の存在の証明となる論証が得られると考えられる。神の完全性の観念が明晰に私の中に存在する。従って数学の真理が確実であるように、神の本質は明晰である。すなわち詭弁に聞こえるかもしれないが、私の理性が事物に必然性を課するのではなく、事柄自体の必然性が、神の存在の必然性を導き、私を決定するのである。実際神の観念が私の思惟に依存するところの、仮構された何ものかではなく、真実で不変な本性の像であることが理解される。幾何学の原理のように自分でこの上なく明証的に認知してことすら時々誤ることがある。神は完全で誤りはないことから、私が明晰判明に認知しているものはすべて必然的に真である。私は、あらゆる知識の確実性と真理性とが、もっぱら真なる神に依存することを明らかに見る。
省察6 「物質的事物の存在および精神と身体との実在的な区別について」
残る命題は物質的事物が存在するかどうかを吟味することだけである。物質的事物は純粋数学の対象である限り存在することが可能である。それらは明証的に判明に認識できるからである。物質的事物に注目する時、想像の能力を用いることを経験する。想像の能力とは、認識能力に直接依存するところの物体に対する能力であるからだ。理性と想像の違いは、想像力はある特別な心の緊張を用いるが、これは理解とは関係ない働きである。理解する時には、精神はいわば自己を自己自身に向け、精神そのものに内在する観念のあるものを考察する。想像する時には精神は自己を物体に向け、その物体のうちに精神によって理解された観念を直感するのである。物体的本性は知覚、感覚、欲望、情念など身体的傾向をフル動員して、すべての性質の観念が私の意識に表示される。外部感覚は誤る場合がある。私の中に、思惟する能力、感覚する能力、想像する能力がある。感覚的事物の観念を受容し認識するのは受動的な能力である。しかし能動的な能力の指示がなければ感覚的能力は働かない。この能動的な能力は身体的な私の中にはない。私とは別の実体にある。この実体は物体的本性かあるいは神である。かくして物体的事物は存在する。私はこの身体と極めて密接に結ばれ、混合され、身体と一体になっている。精神と身体との合成体としての私に神が付与したのである。精神と身体との間には、身体はその本性上常に可分的であり、精神は反対に不可分的である。心は身体の各部分からは直接に支配されることは無い。身体と精神の共通感覚が宿るといわれる松果腺からの働きかけである。
この書には、情念(感情)の百面相を述べているが、その原因論を心理学と生理学との強引なこじつけに終始しており、体液および松果腺を基にする生理学は現時点ではほとんど間違っている。従ってここに要約をする必要性は認めないが、何を論じているかは歴史的に興味があるので、目次・題目だけは記す。
第1部 「情念一般について そして人間の本性について」1) ある主体に関して受動であるものは、他の主体に関しては常に能動であること:
2) 精神の情念を知るには、精神の機能を身体の機能から区別しなければならないこと:
3) そのために従うべき規則:
4) 肢体の熱と運動は身体から生じ、思考は精神から生ずること:
5) 精神が身体に運動と熱を与えると考えるのは誤りであること:
6) 生きている身体と死んだ身体との間にどういう相違があるか:
7) 身体の諸部分およびいくつかの機能についての簡単な説明:
8) これらすべての機能の原理は何か:
9) 心臓の運動はどのようにして起こるのか:
10) いかにして脳のうちに動物精気が生じるのか:
11) 筋肉の運動はいかに起こるのか:
12) 外部の対象が感覚器官に如何に働きかけるのか:
13) 外部の対象のこの働きが、様々なしかたで精気を筋肉に送りうること:
14) 精気そのものの持つ多様性もまた精気の流れ方を多様ならしめうること:
15) 精気の多様性の原因は何か:
16) 身体部分のすべては、精神の助けなしに、感覚の対象と精気によって、動かされることができること:
17) 精神の機能は何か:
18) 意思について:
19) 知覚について:
20) 精神自ら作る想像およびその他の考えについて:
21) 身体のみから起こる想像について:
22) 他のもろもろの知覚の間に存する相違について:
23) 我々が外的対象に関係づける知覚について:
24) 我々が自分の身体に関係づける知覚について:
25) 我々が自分の精神に関係づける知覚について:
26) 精気の偶然的な運動のみに依存する想像も、神経に依存する知覚と同じ意味で真の受動でありうること:
27) 精神の情念の定義:
28) この定義の前半の説明:
29) 後半の説明:
30) 精神は身体のあらゆる部分をひっくるめた全体に合一していること:
31) 脳のうちには一つの小さな腺があり、精神は他の部分よりも特にこの腺において、自らの機能を働かせること:
32) この腺が精神のおもな座であることはいかにして知られるか:
33) 諸情念の座は心臓にあるのではないこと:
34) 精神と身体はどのように互いに働きかけるか:
35) 対象のさまざまな印象が、脳の中心にある腺において合一するしかたの例示:
36) 諸情念が精神内に引き起こされるしかたの例示:
37) 情念がすべtの精気のある運動によって引き起こされることの明示:
38) 情念に伴いかつ精神からは独立な、身体運動の例:
39) 同じ原因でも、人が違えば、違った情念を引き起こしうること:
40) 情念の主な効果は何か:
41) 精神の身体に対する支配力はどういうものか:
42) 人は思いだそうとするものを、記憶のうちにどのようにして見出すか:
43) いかにして精神は想像したり、注意したり、身体を動かしたりすることができるのか:
44) いちいちの意志作用は、自然によって腺のある一つの運動に結合されているけれども、工夫または習慣によって他の運動に結合することができる:
45) 情念に対する精神の支配力はどういいうものか:
46) 精神が情念を完全には支配できぬようにしている理由は何か:
47) 精神の低い部分と高い部分との間にあると普通に想像されている戦いとは何か:
48) 精神の強さと弱さは何において認められるか、最も弱い精神の持つ不幸はどういうものであるか:
49) 精神の強さだけでは十分ではなく、真理の認識も必要であること:
50) いかに弱い精神でも、よく導くなら情念に対する絶対権を必ず獲得しうること:
51) 情念の第一原因は何か:
52) 情念の効用は何か、情念をどのようにして数え上げうるか:
53) 驚き:
54) 尊重と軽視、高邁と高慢、謙遜と卑屈:
55) 尊敬と軽蔑:
56) 愛と憎み:
57) 欲望:
58) 希望、懸念、執心、安心、絶望:
59) 不決断、勇気、大胆、負け嫌い、臆病、恐怖:
60) 内心の不安:
61) 喜びと悲しみ:
63) 自己に対する満足、後悔:
64) 好意と感謝:
65) 憤慨と怒り:
66) 誇りと恥:
67) 嫌気、残りおしさ、うれしさ:
68) 諸情念のこの枚挙が、普通に行われている快挙と違うのはなぜか:
69) 基本的情念は六つしかない:
70) 驚きについて、その定義とその原因:
71) この情念においては、心臓にも血液にも、何の変化も起こらないこと:
72) 驚きの力はどういう点にあるのか:
73) 驚愕とは何か:
74) あらゆる情念は何に役立ち何に害があるのか:
75) 驚きは特に何の役に立つのか:
76) どういう点で驚きは害があるのか、またどのようにして驚きの不足を補い、その過度を正すことができるのか:
77) 最も驚きやすい者は、最も愚かな者でも最も賢い者でもない:
78) 驚きの過度はそれを正さない出おくと、習慣になりうる:
79) 愛と憎みの定義:
80) 自らの意思によって合一したり分離したりするということはどういうことか:
81) 普通に行われている欲望の愛と好意の愛との区別について:
82) 非常に異なる多くの情念が愛を分有する点で一致すること:
83) たんなる愛情と友情と献身との区別について:
84) 憎みには愛ほど多くの種類はない:
85) 愛好と嫌悪:
86) 欲望の定義:
87) 欲望は反対を持たない情念であること:
88) 欲望の様々な種類は何々か:
89) 嫌悪から生まれる欲望とはどういうものか:
90) 愛好から生じる欲望はどういうものか:
91) 喜びの定義:
92) 悲しみの定義:
93) これら二つの情念の原因は何か:
94) 喜びと悲しみとの情念が、身体のみに関係する、善と悪とによってひき起こされるのは、どうしてか。快感と苦痛とはどう違うのか:
95) 喜びと悲しみとはまた、精神のものでありながら精神の気付いていない善や悪によっても、引き起こされうる。例えば危険を冒す快さとか過去の悪を思いおこす快さかとか:
96) 前の五つの情念を引き起こすところの、血液と精気との運動はどういうものか:
97) 愛における血液と精気との運動を知るに役立つ主要な経験的事実:
98) 憎みについての同様な事実:
99) 喜びについての同様な事実:
100) 悲しみについての同様な事実:
101) 欲望についての同様な事実:
102) 愛における血液と精気との運動:
103) 憎みにおける血液と精気との運動:
104) 喜びにおける血液と精気の運動:
105) 悲しみにおける血液と精気の運動:
106) 欲望における血液と精気の運動:
107) 愛における血液と精気の運動の原因はどういうものか:
108) 憎みにおける血液と精気の運動の原因:
109) 喜びにおける血液と精気の運動の原因:
110) 憎みにおける血液と精気の運動の原因:
111) 欲望における血液と精気の運動の原因:
112) これらの情念の外的表徴は何か:
113) 眼と顔との働きについて:
114) 顔色の変化について:
115) 喜びはどうして顔色を赤くするのか;
116) 悲しみはどうして顔色を青くするのか:
117) 悲しい時でも、しばしば顔が赤くなるのはどうしてか:
118) ふるえについて:
119) 無気力について:
120) 無気力は愛と欲望によって引き起こされる:
121) 無気力はまた他の情念によっても起こされる:
122) 気絶について:
123) なぜ人は悲しみによっては気絶しないのか:
124) 笑いについて:
125) 笑いが最も大きな喜びには伴わない理由:
126) 笑いの主要な原因は何か:
127) 憤慨における笑いの原因は何か:
128) 涙の出る源について:
129) どういうふうにして蒸気は水に変わるか:
130) 眼に痛みを起こさせるものが涙を流させること:
131) 悲しみが涙を流させる:
132) 涙に伴ううめきについて:
133) どうして子供と老人は泣きやすいか:
134) どうしてある子どもは泣かずに青くなるか:
135) ため息について:
136) ある個人に特有な情念の結果はどうして生じるか:
137) 前に説明した五つの情念の身体に関する限りでの効用について:
138) 情念の欠陥とそれを正す手段とについて:
139) 同じ五つの情念の精神に属する限りでの効用について、第1「愛」:
140) 憎みについて:
141) 欲望、喜び、悲しみについて:
142) 喜びと愛を悲しみと憎みと比較すること:
143) 欲望に関するかぎりでの前の四つの情念について:
144) その目指す結果が、我々自身の力にのみ依存するところの欲望について:
145) 他の原因のみに依存する欲望について、偶然の運とは何か:
146) 我々自身にも他のものにも依存する欲望について:
147) 精神の内的感動について:
148) 徳の実行は情念に対する最高の救治法であること:
149) 尊重と軽視とについて:
150) これらの二つの情念は驚きの種にほかならない:
151) 人は自己自身を尊重し、または軽視することができること:
152) いかな理由によって人は自己を尊重するのか:
153) 高邁とはどういうことか:
154) 高邁の心は他人を軽視しない:
155) 善き謙遜とはどういうことか:
156) 高邁の特性は何か、それはいかにして情念のあらゆる錯誤を救いうるか:
157) 高慢について:
158) 高慢の産む結果は高邁の生む結果とは反対であること:
159) 悪しき謙遜について:
160) これらの情念における精気の運動はどういうものであるか:
161) いかにして高邁の心は獲得されるか:
162) 尊敬について:
163) 軽蔑について:
164) 尊敬と軽蔑との二つの情念の効用について:
165) 希望と懸念とについて:
166) 安心と絶望とについて:
167) 執心について:
168) いかなる場合に執心は適切であるか:
169) いかなる場合に執心はとがめられるべきか:
170) 不決断について:
171) 勇気と大胆について:
172) 負け嫌いについて:
173) 大胆と希望に基づくこと:
174) 臆病と恐れとについて:
175) 臆病の効用について:
176) 恐れの効用について:
177) 内心の不安について:
178) 嘲りについて:
179) 最も欠陥ある人々が嘲りを最も好むのが常であるのはなぜか:
180) からかいの効用について:
181) からかいにおける笑いの効用について:
182) 羨みについて:
183) 羨みはどのようにして正しくあったり、不当であったりしうるのか:
184) 羨みを抱く人々の顔色が鉛色になりがちなのはなぜか:
185) 憐れみについて:
186) 憐れみに最も動かされやすい人々はどういいう人か:
187) 最も高邁な人々もこの情念に動かされるのはどうしてか:
188) 憐れみを感じないのはどういう人々か:
189) なぜこの情念は人を泣かせるか:
190) 自己自身に対する満足について:
191) 後悔について:
192) 好意について:
193) 感謝について:
194) 妄想について:
195) 憤慨について:
196) 憤慨がときには憐れみと結合し、ときには嘲りと結合するのはなぜか:
197) 憤慨はしばしば驚きをともない、また喜びとも相容れなくはないこと:
198) 憤慨の効用について:
199) 怒りについて:
200) 怒りによって赤くなる人々は、怒りによって青くなる人々よりも恐ろしくはないのはなぜか:
201) 二種の怒りがあり、善意の人は第一種の怒りに傾く:
202) 第二種の怒りのとらえられるのは、弱く卑しい精神である:
203) 高邁の心が、怒りの過度を防ぐ策として役立つ:
204) 誇りについて:
205) 恥について:
206) 誇りと恥日二つの情念の効用について:
207) 恥知らずについて:
208) 味気なさについて:
209) 残念について:
210) うれ史さについて:
211) 情念にたいする一つの一般的な救治法:
212) 人生の善と悪とのすべては、ただ情念のみに依存すること: